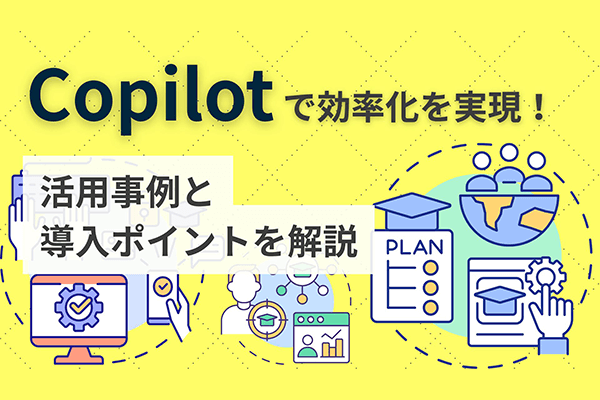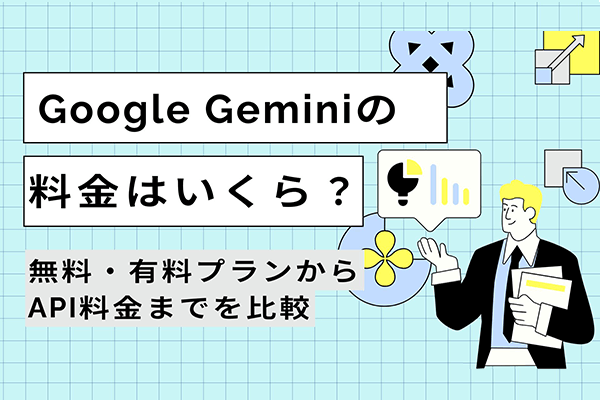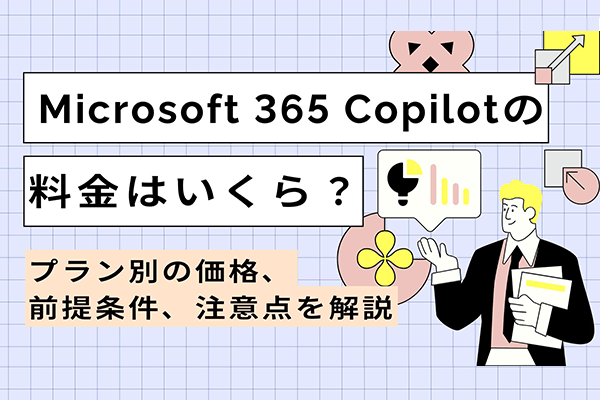DX時代に求められる「顧客視点の業務効率化」とは:DXコラム
- 公開日:2022年4月11日

これからの業務効率化に求められる「顧客視点」の重要性とその効果、実現の為に必要な人材育成について解説します。
目次
① 今後の企業経営に不可欠な業務効率化
新卒採用の「2022年問題」をご存じですか?
少子化の影響で大学卒の新卒採用に相当する22歳の人口が、2022年を境に、急激に減少していきます。
ここ数年、127万人前後で推移してきたところ、約3万人減少し、それ以降も減少の一途を辿っています。
2019年4月に法改正に伴い設けられた労働時間の上限規制もあり、「働く人数」と「働く時間」は、もはやこれまで通りのやり方で仕事を続けていては、持続可能性に乏しいと言えます。
その中で注目を集めているのが、「IT・デジタル技術による業務効率化」です。
ロボティクス、AIなどを用いて、人の業務を置き換え、自動化や効率化しようという取り組みが進められています。
IT技術を用いた業務効率化は、歴史上何度も繰り返されてきた事であり、「今更か」と思われるかもしれません。実際に、2000年頃に日本企業で注目され始めた、ITを用いた業務効率化が、既に7割以上の企業で取り組まれているという調査結果も出ています。
一方で、半数以上の企業が失敗又は、目標に到達しなかったという調査結果もあります。いったいなぜ成果が上がらないのでしょうか?
業務効率化の失敗例としては、「ツールを導入したけれども、現場が使ってくれずに成果が出ない」といった事象や、「業務効率化で累計数千時間を削減したはずが、気が付いてみればいまだに現場は忙しく、経営上の明白な効果が出ていない。」という事象が挙げられます。これらの事象はなぜ起きているのでしょうか?
それは、失敗した取り組みの多くが、「社内目線の業務効率化」にとどまっているからです。
社内業務を効率化するのに、社内目線で何がいけないのか?と思われるでしょう。
社内目線を持つことは悪い事ではありませんが、そこに欠けているのが「顧客視点の業務効率化」なのです。
② 顧客視点の業務効率化
顧客視点の業務効率化とは、どういう事でしょうか?
Amazonの創業者ジェフ・ベゾスが紙ナプキンに書いたと言われる、ビジネスモデル図はご存じですか?
良質な顧客体験がトラフィックに繋がり、販売者を集めて品揃えを改善させるというループ図と、これによる企業の成長を低コスト体質につなげ、低価格を実現し、良質な顧客体験につなげるという、現在のAmazonのビジネスモデルを一つの図に表したものです。

ここで重要なのが、Amazonは顧客に低価格という顧客体験を届けるという顧客視点を持った上で、デジタルを用いた徹底的な効率化や自動化により、低コストを実現しようとしている事です。
ただコストを削減して利益を増やすという、社内目線だけではないのです。
業務効率化によってコストを削減して利益を増やそうとしても、当然売上という上限があり、売上以上の利益を生み出すことはできません。
日本のGDPは20年以上停滞しており、同じ商品を同じように売り続けても、飛躍的に成長することは難しいでしょう。
また、グローバル市場においても、コモディティ化した商品は人件費の安い国に勝つことはできず、高価格・高付加価値製品においても、日本企業は後塵を拝しているという実情があります。
あらたな価値を生み出さなければ、日本企業に成長は無いと言っていいでしょう。
一方で、業務効率化で得られた低コスト体質により、顧客により安く商品を届けたり、いち早く商品を提供することは顧客価値に繋がり、Amazonのように、コストを削減するだけでなく売上を伸ばすことにもつながるでしょう。
皆さんの職場でこれまで行われている業務効率化は、社内のみに目を向けていませんか?
社内のみを見て推し進める業務効率化では、生み出される価値は限定的です。
以下の3つの観点を持って業務効率化を考えてみましょう。
- デジタルを用いて効率化し、コストを削減して低価格化。
- デジタルを用いて効率化し、顧客に必要な商品やサービス、情報をいち早く届ける。
- デジタルを用いて効率化し、より品質の高い商品やサービスを届ける
低価格化をしても、より多くの人が買ってくれれば売上を上げることが出来るでしょうし、いち早く届けることや品質が高いことは差別化に繋がり、同業他社と同じサービスであっても優先的に選択してくれ、高価格でも購入してくれるかもしれません。
Amazonを利用したことがある方は多いと思いますが、安さの他にも、翌日配送などの速さがAmazonの魅力と考えている方も多いのではないでしょうか。この顧客にとっての「速さ」は、仕入れ・発注や倉庫の自動化といった社内の業務効率化により実現したものです。
このように、顧客視点を持った業務効率化を行った結果として、コスト削減だけでなく、売上増を実現することが出来たのです。
③ 顧客視点の業務効率化に必要な人材とは
顧客視点を持った業務効率化と言っても、簡単なことではなく、企画を行い、成功させるためには、業務知識、デジタルリテラシー、顧客視点といった、3つの知識・スキルを持った人材が欠かせません。
まず、業務効率化を進めようとするときに、該当の業務に関する知識は欠かせません。業務のそもそもの目的やあるべき姿、業務知識や利害関係者の存在、現在の業務が抱える課題などの知識、経験が重要となってくるでしょう。
もし現場で働いている方ではない、システム部門の方が企画を立てるときは、徹底的に現場を見て、長年その現場で働いている人に話を聞いて回るという事が必要になるでしょう。
続いて、IT・デジタルリテラシーです。
一つのデジタル技術を深めるのではなく、まずはあらゆるIT・デジタルリテラシーを網羅的に学びましょう。体系的に学ぶために、ITパスポートやデータサイエンティスト検定といった資格試験などを取得いただく事も推奨されます。
プログラミングなど、それぞれの技術を「使える」ことよりも、まずはそれぞれの技術要素がどのようなビジネス上の価値があるのか、導入時の進め方や注意点などを把握しておくことが求められます。
ロボットによる無人化やAIによる顧客の価値向上などデジタルで出来ることは日々増えています。一度学んで終わりではなく、継続的に新技術と技術の適応事例を学ぶことも求められます。
最後に、顧客視点です。各々の業務は業務自体を遂行することにより最適化されており、必ずしも顧客にとって嬉しい仕事が出来ていないという事が多々あります。
本当に顧客が求めている仕事が出来ているのかを測る手段が、「顧客をデータで見る」という事です。
どの商品がいつ何点売れた、というPOS(販売時点)データを管理することは、多くの企業で出来ている事でしょう。しかし多くの企業が、どのような属性や背景の人が買ってくれたのか、購入後も継続して使用してくれているか、満足してくれているかといったデータを見ることが出来ていないのです。
業務視点、デジタル技術、顧客視点、この3つを行き来しながら、顧客視点のデジタルによる業務効率化施策を立てていくことと、そのための人材育成が、労働者が減り、市場も停滞してきた日本企業において、不可欠なことであると言えるでしょう。
業務効率化を進めるためは?

業務効率化を進めるために、以下の手順を行いましょう。
- 業務における問題点を洗い出す
- 改善策を立てる
- 改善策の実施後、PDCAを回す
1. 業務における問題点を洗い出す
まず、業務における問題点を洗い出すために、業務の全体像を見える化し、問題点を明確にしつつ現状を把握しましょう。
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| ビジネスプロセス全体像の把握 |
|
| リソースの可視化 |
|
| 時間管理 |
|
| 品質管理 |
|
| コミュニケーション |
|
このように、業務工程のフローや必要なツール・スキル、各工程にかかる所要時間まで把握できれば明確な問題点を洗い出せます。
2. 改善策を立てる
課題を見つけられたら、以下の方法を用いて改善策を立てましょう。
- 自動化する
- マニュアル・フローチャートを作成する
- データベースを活用する
- アウトソーシング・業務委託をする
- 無駄な業務をなくす・まとめる
自動化する
業務の中で繰り返し行われる作業を自動化することで、作業時間の短縮やヒューマンエラーの軽減が期待できます。業務の内容や目的に応じて最適なツールを選定するため、複数のツールを比較検討することが大切です。
マニュアル・フローチャートを作成する
マニュアルやフローチャートを作成することも有効です。業務の流れを明確にすることで、作業の効率化や品質の向上が期待できます。また、マニュアルやフローチャートは、教育やトレーニングにも役立ちます。
データベースを活用する
データベース業務に必要な情報を集約することで、情報の共有化や検索の効率化が可能になります。また、データベースによって業務の見える化をすると、業務の改善にもつながります。
アウトソーシング・業務委託をする
アウトソーシングや業務委託をすることも一つの手段です。外部の専門家に業務を任せることで、業務の効率化やコスト削減が期待できます。また、外部の専門家によって、業務の改善に対して提案を受けられるのも利点です。
無駄な業務をなくす・まとめる
無駄な業務をなくすことも大切です。業務の見直しや改善を行うことで、無駄な時間やコストを削減できます。また、業務をまとめることで不要なプロセスを省き、業務の効率化が可能になります。
3. 改善策の実施後、PDCAを回す
改善策を実施した後は、PDCAサイクルを回すことが重要です。
- Plan(計画)
- Do(実施)
- Check(評価)
- Action(改善)
効果を評価するためには、Checkの段階で定量的・定性的なデータを収集し、問題点を洗い出して再度改善策を立てることが大切です。
このように、PDCAサイクルを回すことで業務プロセスの改善が継続的に実施でき、より効率的かつ効果的な業務運営が実現できるでしょう。
業務効率化のため活用すべきツール

業務効率化のため活用すべきツールは、以下が挙げられます。
- RPA
- タスク管理ツール
- ペーパーレス化ツール(クラウド)
- コミュニケーションツール
RPA
RPAとは、Robotic Process Automationの略称で、人間が行っているルーティン業務を自動化するためのツールです。例えば、Excelファイルのデータ入力や、PDFファイルのテキスト抽出などが可能です。
RPAを導入することで、人間の手作業によるミスを防ぐことができ、作業時間の短縮にもつながります。
タスク管理ツール
タスク管理ツールは、日々の業務で行うべきタスクを管理するためのツールです。タスクの優先度や進捗状況を一元管理することができ、業務の優先順位を明確にできます。
また、共同作業が必要な場合には、タスクを共有することでチーム全体での業務効率化が図れるでしょう。
ペーパーレス化ツール(クラウド)
ペーパーレス化ツールは、紙で行っていた業務をデジタル化するためのツールです。クラウド上にデータを保存することで紙の書類を保管する場所を必要としなくなり、スペースの節約につながります。
また、データの共有が容易になるため、業務の円滑化にも役立ちます。
コミュニケーションツール
コミュニケーションツールは、チーム内でのコミュニケーションを円滑にするためのツールです。メールやチャット、音声通話など、さまざまな手段で社内のコミュニケーションを活発化できます。
チーム全体で情報共有ができるため、業務の進行状況を把握しやすくなるのも利点です。
まとめ

DX時代に求められる業務効率化には、顧客視点が欠かせません。顧客にとって必要なものを提供することでコスト削減だけでなく、売上増にもつながります。そして、業務効率化に必要な人材は、業務知識、デジタルリテラシー、顧客視点の3つの知識・スキルを持った人材です。
また、業務効率化を進めるためには問題点を洗い出し、改善策を立て、PDCAサイクルを回すことが重要です。RPA、タスク管理ツール、ペーパーレス化ツール(クラウド)、コミュニケーションツールなどのツールも活用しましょう。
ディジタルグロースアカデミアでは、顧客視点を持った業務効率化に必要な人材の育成体系や研修プログラムをパッケージとして提供しています。
デジタル人材育成体系の策定から、人材教育、DXを実現するための伴走コンサルティングまで、一貫したサポートを提供することで、DX人材の育成を早期に実現すると共に、迅速なDXでの効果創出を実現します。
資料・研修動画ダウンロード申し込みページ
DXに関する様々な資料や動画がダウンロード可能です。