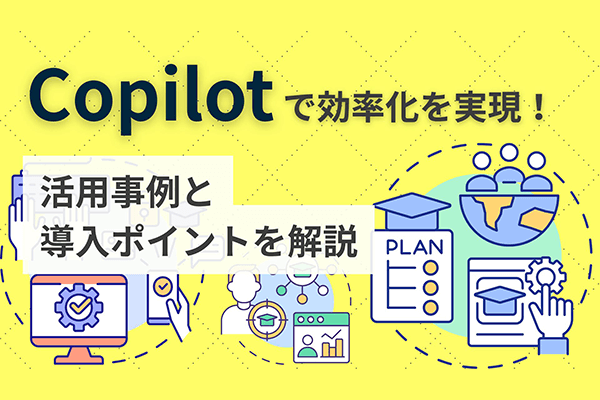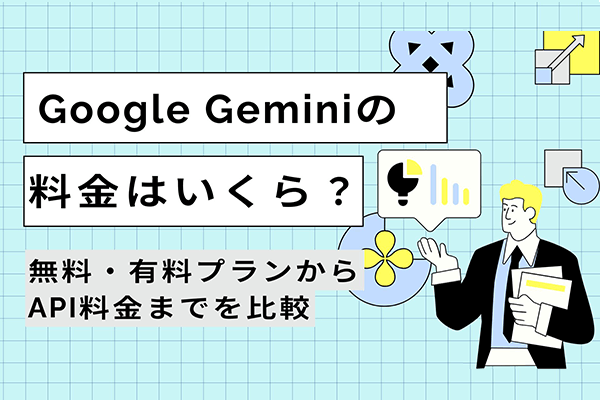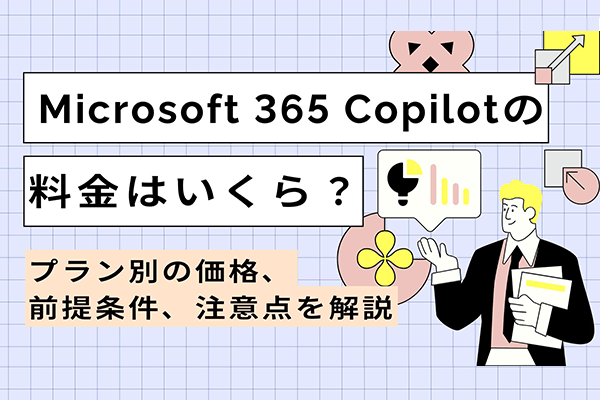行政・自治体DXの目的とは?事例やシステム標準化の対象17業務についても紹介
更新日:2022年11月21日

DXとは「Digital Transformation(デジタル・トランスフォーメーション)」の略で、デジタル技術によって、企業のビジネスや地域住民の生活を発展させるための変革を行うことを指します。
現代では幅広い地域・業界でデジタル技術の活用が求められており、さらなる社会貢献や競争力の維持・強化のためにもDX推進は欠かせません。
DXを進めるのは企業だけでなく行政・自治体でも同様で、国をあげてDX推進のための計画が策定されています。
目次
行政DX・自治体DXとは

行政DX・自治体DXとは、デジタル技術やデータの活用によって公務員の業務効率化を図り、住民の利便性をより向上させるための取り組みのことです。
政府は、行政・自治体がDXを進めていくための施策として、「自治体DX推進計画」を公表しています。
この計画は、自治体DXによってデジタル社会の実現と成功に導くために行政・自治体が実行すべきことが具体的に示されています。
自治体がDXを進めることは、各行政機関が抱える多くの問題の解決に役立つはずです。
行政・自治体がDX成功のために打ち出し実行を進めている施策として、デジタル庁の発足、クラウドサービスの活用に向けた検討などがあります。
デジタル庁の発足により、今後急速に行政・自治体DXが進むことが期待できるでしょう。
行政が抱える課題│総務省がDX推進する理由

行政・自治体がDXを進めるにあたって抱えている課題としては、以下のようなものが挙げられます。
- 人材不足
- アナログ文化
- DXに関する知識不足
- 財政難
人材不足
行政がDXを進めるにあたり、大きな課題は人材不足です。
日本全体で少子高齢化が進んでおり、日本の約1700の自治体が2040年には約半数が消滅の危機を迎えるとされています。
労働力人口の減少に伴い、DXを進められる人材も不足しているという現状があるのです。
DX人材はIT企業に多いため、行政・自治体にはDXを担える人材がそもそも不足しています。
とくに地方においては労働力人口の不足や減少は顕著で、大きな課題となっています。
アナログ文化
行政・自治体では、旧態依然の組織体制であることが広く知られていますが、この体制自体にも問題があります。
たとえば、紙文化が根強く、手続きがオンライン化に対応していなかったり、各省庁や自治体でシステムの内容が異なりシステム連携が困難となっていたりする点が課題です。
なかでも、住民が記入した申請書や届け出を職員が手作業でシステムに転記するようなケースが多く見受けられますが、これでは二度手間となってしまっています。
FAXを使った事務連絡や印鑑による承認作業などのアナログ業務が抜けきっていない点で、行政・自治体はDX実現を目指すにはハードルが高いことがわかります。
DXに関する知識不足
行政においては、DXに関する知識や理解が不足していることも大きな課題の1つです。
民間企業ではライバル企業との競争のためにも、新しいデジタル技術を次々取り入れていく姿勢が見受けられますが、自治体は現状維持でも内部で大きな問題が起こりにくい業界といえます。
そのため、行政・自治体では、DXを進めるための具体的なアイデアが浮かばず、知識をつけるためのモチベーションも湧きにくいのです。
財政難
DXを導入するためには、高額な費用や時間がかかるため、行政の財政難がDXを進められない原因の1つでもあります。
全国で多くの自治体が財政難に悩まされており、財政破綻してしまう自治体もあるほどです。
そもそも財政状況が悪化している状態で、DXを進めるための予算を割り当てられないのが大きな問題として挙げられます。
自治体DX推進計画システム標準化の対象「17業務」とは

情報システムの標準化とは、業務のオンライン化と並び、住民サービスの向上や行政の効率化を達成するための計画です。
システムの標準化を目指すことで自治体DXをより円滑に進めていくことが可能となるため、以下17業務に関しては原則2025年度末までに実施することを目標としています。
- 住民基本台帳
- 選挙人名簿管理
- 固定資産税
- 個人住民税
- 法人住民税
- 軽自動車税
- 国民健康保険
- 国民年金
- 障害者福祉
- 後期高齢者医療
- 介護保険
- 児童手当
- 生活保護
- 健康管理
- 就学
- 児童扶養手当
- 子ども・子育て支援
住民基本台帳はすでに標準仕様が策定済みですが、今後はその他の業務についても新システムへの移行が進められるでしょう。
標準システム導入のフローとしては、国が定めた標準仕様に沿って、企業が要件を満たすシステムを開発し、自治体が導入・運用をしていくというものです。
税金や保険関係、子どもに関するものがメインで、住民の生活と密接につながる業務が多く挙げられていることがわかります。
これら17業務のシステム移行が完了するだけでも、職員の事務負担を大幅に削減できることが期待されています。
さらに、住民側にも窓口の待ち時間を短縮することや、手続きのための申請書記入にかかる時間を削減するなど、さまざまなメリットがあるのです。
たとえば自治体をまたぐ転居が必要となった場合に、新しい自治体へ届け出なくてはなりません。
現状では、転居に伴う手続きに必要な書類の様式がすべての自治体で統一されているわけではないため、機械で自動的に情報を読みとれない仕組みであることが大きな課題として挙げられるでしょう。
そのため、住民が転入先の自治体で書類を書き込み提出しにいくことや、その情報を職員が手入力するといった負担が生じています。
この場合、情報の確認や入力を自動で行えないことで人的ミスが起きやすいというのが問題として上がっており、早急な解決が求められます。
こうした問題もデジタルツールの導入を進め、ツールを職員が自治体ごとに最適な形で使用できれば、大幅な業務削減や情報の取り扱いミスの防止など、さまざまな課題の解決に繋げられるでしょう。
行政DXの事例

行政DXが進んでいる事例として、以下3点について紹介します。
- AIによる住民対応
- オンラインでの手続き
- オンラインによる情報提供
AIによる住民対応
市区町村において、代表的な業務に窓口対応があります。
窓口での案内においては時間や手間がかかるものですが、この業務をAIに任せることで、来庁者の対応がスムーズになりました。
AIによる案内によって、職員は窓口での住民対応の時間を削減できることから業務が円滑に進みます。
結果、住民は長時間待たされるケースが激減する上、職員も効率的に業務を遂行できることで、住民の悩みを解決するための取り組みに力を入れられるというメリットがあります。
オンラインでの手続き
AIによる案内だけでなく、窓口で行う手続き自体をオンライン化する取り組みも進んでいます。
たとえば、住民はわざわざ窓口を訪れなくても、スマホや庁舎外の端末などで手続きを済ませることが可能となっており、本人確認はスマホへの電子証明書の取り込みで簡素化できている自治体があります。
このようなオンライン化が進めば、住民にとっても利便性向上はもちろんのことですが、マイナンバーの活用や職員のテレワークが推し進められることで、職員にとっても働きやすい環境を構築できるようになるでしょう。
オンラインによる情報提供
災害情報や農林水産業に関する情報提供も、オンライン化が進められています。
たとえば、災害情報や農林水産業情報をloTセンサーで収集したり、防災マップや避難所マップなどをインターネット上に掲載したりすることで、オンラインでの情報提供が実現しています。
また、リスクがある場所では人間が24時間の監視体制を敷くことは困難ですが、こうしたモニタリングもデジタルデータを取得するセンサーの活用によって常時対応が可能です。
オンラインによる情報提供には通信環境の整備も欠かせないため、企業との協力も必要不可欠な要素であるといえます。
まとめ

行政DXが進めば職員の業務効率の向上により、住民が抱える課題を解決するための取り組みにもより力を入れられるでしょう。
ただし、DXを進めるにはDX人材や理解の不足が大きな課題となっています。
DX人材育成会社のデジタルグロースアカデミアでは、DXに関する研修が充実し、いつ・どこにいても受講できるe-ラーニングの整備から自治体に合わせたコンサルティングまで、幅広いサポートを提供しています。
行政DXを進めるためには、ぜひデジタルグロースアカデミアへご相談ください。
【監修】
日下 規男
ディジタルグロースアカデミア マーケティング担当 マネージャ
2011年よりKDDIにてIoTサービスを担当。2018年IoTごみ箱の実証実験でMCPCアワードを受賞。
2019年MCPC IoT委員会にて副委員長を拝命したのち、2021年4月ディジタルグロースアカデミア設立とともに出向。
資料・研修動画ダウンロード申し込みページ
DXに関する様々な資料や動画がダウンロード可能です。