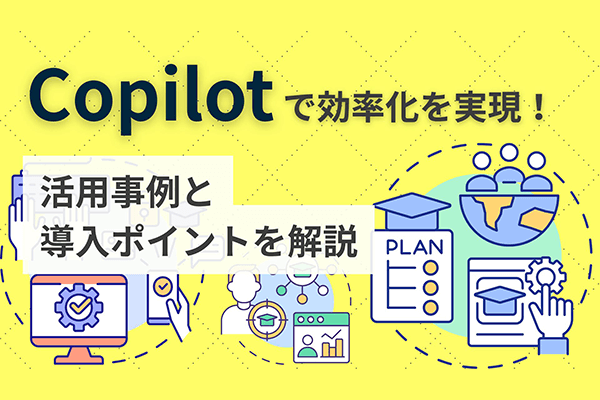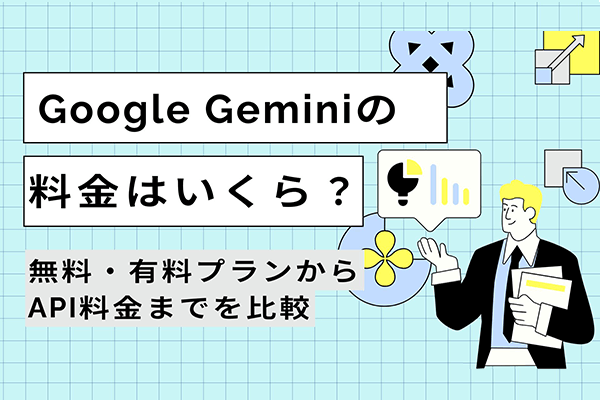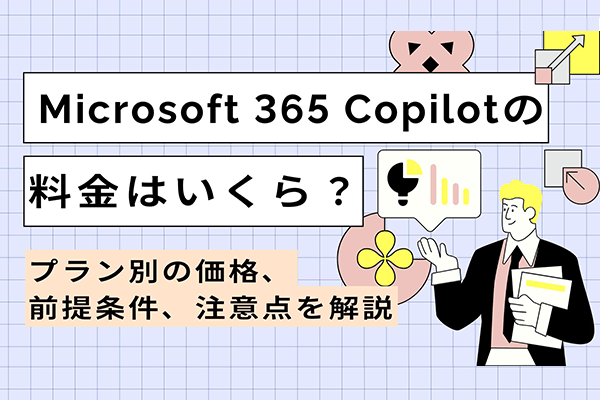なぜDXの内製化が必要?そのメリット・デメリットや課題を紹介
更新日:2023年12月12日

DXとは、デジタルトランスフォーメーション(Digital Transformation)の略称のことです。企業や組織がデジタル技術を活用して業務プロセスやビジネスモデルを変革し、持続的な成長や競争力の向上を図る取り組みを指します。
DXは、今やビジネスの必須条件となっていますが、その実現には多くの課題があります。 そこで、DXの内製化という選択肢が注目されています。
この記事では、DXの内製化によるメリットとデメリットについて解説しています。基本的な知識や実践的なノウハウを活用し、DXを推進する参考にしてください。
目次
DXの内製化の概要

DXの内製化とは、企業が自社のリソース(人材、技術、データなど)を使ってDXを推進することです。内製化には、社内でDXを完全に実行する方法と、戦略を自社で立案し、一部の業務を外部に委託する方法などがあります。
内製化に注目が集まる理由は、DX推進とデジタル活用の必要性が高まったことに起因します。例えば、ビジネスとITの統合、データの活用、そして社内外の変化への対応能力が重要視されたり、コロナ禍でオンライン化やテレワークが加速したりしたことなどです。
なお、DXの内製化には多くのメリットがありますが、同時にデメリットも存在します。そのため、日本企業の内製化に成功するためには、従来の意識を変え、投資と成長を重視する必要があります。
DXの内製化がもたらすメリット

DXの内製化がもたらすメリットは、以下が挙げられます。
- 変化に対する柔軟性と速度が向上
- コスト削減
- カスタマイズと適合性
- スキルの向上
- 長期的なビジネス戦略
変化に対する柔軟性と速度が向上
DXの内製化は、変化に対する柔軟性と速度を向上させます。ビジネスや業務に合わせてデジタル技術を選択や導入できるため、変化に柔軟に対応できるためです。
一方で、外部ベンダーに依存すると、システムの改修やアップデートの遅れが想定されます。その結果、市場のニーズに適応できなくなる可能性が出てくるでしょう。そのため、DXの内製化はリスクを回避しながら柔軟性と速度を高める有効な手段と言えます。
コスト削減
DXの内製化は、長期的にはシステム開発や保守に関するコストも削減される可能性があります。一貫した内製プロセスを通じて効率が向上することで、外部ベンダーに支払う費用を減らせるからです。
例えば、外部のベンダーやコンサルタントに依存すると、サービス料や保守費用などがかかります。また、提供するデジタル技術は、自社のビジネスや業務に過剰あるいは不十分な場合もあります。
DXの内製化は、こうしたコストを削減できるだけでなく、自社でシステムやサービスを開発することで、品質やセキュリティの管理も簡素化することが可能です。
カスタマイズと適合性
加えて、DXの内製化は、カスタマイズと適合性も高めます。自社で開発する場合は、自由度が高く、効果的なデジタル戦略の実行が可能です。
外部ベンダーに依頼する場合は、自社の要望を正確に伝えることや、納期や予算などの調整が必要です。また、同社を利用する他社と差別化できない場合もあります。
自社でDXを推進すると、自分たちのビジネスや業務に最適なデジタル技術をカスタマイズ・開発できるため、適合性や独自性を高めることができます。
スキルの向上
他にも、DXの内製化は、スキルの向上にも寄与します。外部に依存すると、自社の従業員はデジタル技術に関する知識や経験を得る機会を失ってしまいます。
一方で、内製化では、社員がデジタル技術やビジネスプロセスに関する知識を深めることで、社内の専門知識を自然に増やすことが可能です。その結果、デジタル変革を推進するために必要な人材育成に貢献します。
また、自社でカスタマイズや開発したデジタル技術は、自社の従業員にとって使いやすい場合が多いことも、実践形式で学ぶきっかけとなりスキル向上に役立つでしょう。
長期的なビジネス戦略
最後に、DXの内製化は、長期的なビジネス戦略としても優秀です。DXは一時的なプロジェクトではなく、長期的なビジネス戦略です。そのため、自社でデジタル技術を常に最新の状態に保ち、自社のビジョンや目標に沿って展開する必要があります。
しかし、内製化を一気に自社内で進めると、ノウハウやスキルが不足します。このことから、スタートは外部のベンダーを効率よく使いながら、最終的に自社のみで完結するという方法が一般的です。
このように、経営層のコミットメントと全社的な取り組みによって内製化できれば、DXを成功させるための文化的な基盤を築くことができます。
DXの内製化がもたらすデメリット

DXの内製化がもたらすデメリットは、以下が挙げられます。
- 高い初期投資とランニングコスト
- 多くの時間とリソース
- 技術の進化に追いつけないリスク
高い初期投資とランニングコスト
DXの内製化では、高い初期投資とランニングコストがかかります。自社の開発チームやIT部門を強化する必要があるためです。
具体的には、人材の採用や教育、開発環境やツールの導入や更新、セキュリティや品質管理などのコストがかかります。特に、DX人材の育成にかかる教育関連費は高くなる傾向があります。
また、DXの内製化は一度で終わるものでなく、継続的な改善や更新によるランニングコストも高くなります。
多くの時間とリソース
DXの内製化を行うためには、多くの時間とリソースを割く必要があります。内製化の場合、システム開発にかかる費用、開発にかかる時間や人件費、効果測定に至るまでが不確定要素となるためです。
DXの内製化は長期的な取り組みであり、すぐに成果が出るものではありません。もちろん、その間にも市場や顧客ニーズは変化します。そのため、初期段階では正確なコスト試算が困難となります。
技術の進化に追いつけないリスク
最後に、長期的に実施する内製化では、技術の進化に追いつけないリスクも存在します。技術は日々進化しており、専門的な知識の不足や市場変化への適応の難しさから、育成するには長い時間がかかります。
そのほか、属人化によってシステムが使えなくなったり、経験や知識、技術力などの面でベンダー企業と比較して劣る場合、品質の低下が事業において致命的になったりすることも考えられます。
DXの内製化に伴う課題と解決策

ここまで触れたデメリットに挙がっている課題を解決するためには、以下の方法が効果的です。
- 計画と段階的な導入
- 外部リソースの活用
- 継続的なアップデートとトレーニング
- リスクの分散化
計画と段階的な導入
DXの内製化では、確かな計画と段階的な導入を実施します。一気に行うとコストがかかりすぎる可能性もあるためです。
そのため、上流フェーズ(企画や設計など)から内製化し、コストを段階的に分散させ、内製化に必要なリソースやスキルを段階的に構築します。また、IT部門やベンダーの支援を受けながら、ローコード/ノーコードツールなどを活用し、現場主導の体制構築を進めましょう。
外部リソースの活用
DXの内製化は、自社の人材や技術だけで行うことは難しいため、外部リソースの活用も必要です。コンサルタントやベンダーなどの専門家や研修を活用することで、自社にない知識や経験を得ることができます。
その結果、自社のビジネスや業務を深く理解している社員が、デジタル技術やプロジェクトマネジメントのスキルを身に着けることが可能です。また、外部リソースを活用すると、スタート時点で発生する人材不足や技術不足を補うこともできます。
継続的なアップデートとトレーニング
さらに、内製化では、継続的なアップデートとトレーニングが必要です。一度行ったら終わりではなく、常に最新の技術やトレンドへの対応が求められるからです。
内製化においては、自らデジタル・IT化の企画を立て、実行できることが重要です。そのため、先述したように外部リソースを活用しながら、継続的なアップデートとトレーニングを継続しましょう。
こうした取り組みは従業員のスキルの向上につながり、自主的にデジタル化を推進する基盤を作ります。
リスクの分散化
最後に、DXの内製化に伴うリスクの分散化も検討します。例えば、技術的な問題やセキュリティの問題などは、各プロジェクトで発生する代表的なリスクです。
こうしたリスクを分散させるためには、ひとつの大規模なプロジェクトに依存せず、複数の小規模なプロジェクトを立ち上げる方法が有効です。複数に分散することで、いずれかのプロジェクトに問題が発生しても、他のプロジェクトへの影響を減らすことができます。
また、他のプロジェクトで発生したリスクと対策で新たに学びを得られる環境も作り上げられます。
DXの内製化を進めるステップ

DXの内製化を進めるステップは、以下の7つです。
- 現状を把握
- 目標の設定
- デジタル化戦略の策定
- 組織体制の構築
- 必要な技術とリソースの確保
- 開発とテスト
- 評価と改善
1. 現状を把握
DXの内製化を進めるには、まず現状を把握し、問題点を洗い出します。問題点を洗い出すときには、以下の観点から分析するとよいでしょう。
- 外部ベンダーや企業に依存している部分
- 自社のIT人材の能力不足
- 業務プロセスやシステムの効率性
- コスト、品質、セキュリティ
また、問題点を可視化することで、改善の優先順位や方向性を明確にできます。可視化する方法としては、KPIやダッシュボードなどのツールを活用すると便利です。
2. 目標の設定
次に、DXの内製化に向けて具体的な目標を設定します。目標を設定する際には、SMART原則に従って、以下に該当することが望ましいです。
- 測定可能で達成可能か
- 関連性が高いか
- 期限が明確か
また、目標を設定するときには、ビジネス戦略や経営方針との整合性や関連性を確認しておきましょう。
3. デジタル化戦略の策定
さらに、DXの内製化に向けて、どのようにシステムやサービスを内製化するかを含めたデジタル化戦略を策定します。
デジタル化戦略を策定する際には、短期的な目標やアクションから長期的なビジョンやロードマップまでを含み、段階的な計画の立案が必要です。
4. 組織体制の構築
戦略を策定できれば、DXの内製化に関わる人材やチーム、役割や責任、コミュニケーションや協働など、内製化に向けての組織体制の構築を行います。
具体的には、以下が挙げられます。
- 人材の育成や採用
- ビジョンや目標を共有するリーダーシップの発揮
- DXの内製化に関する意思決定
- 情報共有を円滑にするガバナンスの確立
体制構築には、経営層までコミットメントし、人的資源や組織文化を形成しましょう。
5. 必要な技術とリソースの確保
体制を構築した後は、必要な技術とリソースを確保し、社内でDX人材が育つ環境を整えます。具体的には、DXの内製化のために、自社でシステムやサービスの開発・保守運用を行うために必要な技術と人材を確保します。
6. 開発とテスト
開発とテストでは、実施に内製化するシステムを開発し、期待通りに動作するかをテストします。アジャイルやデザイン思考などの開発手法やツールを活用し、ユーザーのニーズやフィードバックを反映しながら迅速かつ柔軟に開発しましょう。
必要に応じて外部リソースを活用するなど、実現性の高いプランで進めることが大切です。
7. 評価と改善
最後に、DXの内製化に向けて評価と改善も必要です。評価と改善では、KPIやダッシュボードなどのツールを活用し、定量的かつ定性的な指標で効果や問題点を測定します。
その後、PDCAサイクル
を回して改善策を実施します。また、常に最新の市場動向や技術トレンドに合わせて調整しましょう。まとめ

DXの内製化とは、企業が自社のビジネスプロセスやサービスをデジタル化するために、外部のベンダーやパートナーに頼らずに、自社の開発チームやIT部門で行うことです。
内製化には、柔軟性や独自性などのメリットがありますが、高い初期投資やランニングコスト、多くの時間とリソース、技術の進化に追いつけないリスクなどのデメリットもあります。
内製化を成功させるためにも、まずは人材の育成を進めましょう。ディジタルグロースアカデミアでは、人材育成に必要な研修を取りそろえています。まずは、お気軽にお問い合わせください。
資料・研修動画ダウンロード申し込みページ
DXに関する様々な資料や動画がダウンロード可能です。