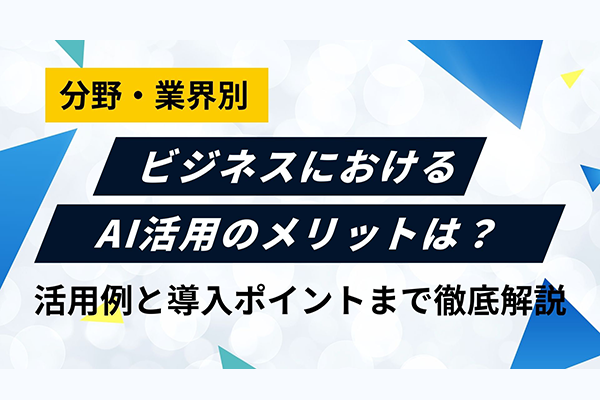【現場直送コラム】
AI導入が定着しないのは“社員のせい”ではない
~<前編>プロンプト教育はなぜ無理ゲーなのか?~
更新日:2025年10月9日
株式会社ディジタルグロースアカデミア
カスタマーサクセス スーパーバイザー 柴田 佳幸

目次
AI活用が定着しない本当の理由とは?
「AI研修を実施したのに現場に定着しない。」
これは、多くの企業でAI導入を任された担当者の共通の悩みです。
その原因を「社員のリテラシー不足」や「AI研修不足」と片づける声もありますが、本当にそうでしょうか?
実は、問題の根っこにあるのは「社員」ではなく、AI導入時の“誤った前提”なのです。
誤った前提①:
「AI研修でプロンプト教育すれば十分?実は定着しない理由」
多くの企業が「AI研修の一環としてプロンプトを学べばAI活用が進んで定着する」と考えています。
しかし実際には、社員は「教わった通りにプロンプトを書けない」「正解が分からない」とすぐに挫折してしまいます。
書籍『その前提が間違いです。』(講談社、清水勝彦 著)が説くように、出発点の前提が誤っていれば、どんな努力も空回りするのです。 「プロンプトとは何か?」の基礎を知ることは大事ですが、「生成AI研修でプロンプト教育を行えば十分」という考え方自体が、誤った前提になってしまいます。
誤った前提②:
「プロンプト集を配布してもAI活用が進まないワケ」
「プロンプト集を配布すれば生成AI研修の効果が上がる」という発想も、典型的な誤解といえます。
一見便利に見えますが、実際は「状況が違ってそのまま使えない」「結局アレンジできない」という壁に直面します。
これはまるで、料理初心者に難解なレシピ本を渡して「同じ味を出せ」と言うようなもの。
結果として社員は挫折感を感じてしまい、「AI活用はやっぱり難しい」と思って使わなくなってしまいます。
誤った前提③:
「AIは命令だけで動く?現場での落とし穴」
さらに根深いのが「AIは命令だけで正しく動く」という前提です。
人間同士で考えれば分かりやすいでしょう。
上司が部下に「これやっとけ」と命令しても、背景や意図が共有されなければ誤解や反発が生じます。
AIに対しても同じで、命令だけを急に投げても文脈が欠けていれば期待通りの成果は得られません。
AI活用が定着しない典型的な失敗事例
実際に私の目の前でも、こんなケースがありました。
ある社員が、お客様に送るレターの原稿をAIにアップロードし、
「この原稿を評価してコメントしてください」とだけ命令しました。
AIは何とか答えようとしますが、ペルソナや用途、目的といった前提条件を一切共有していなかったため、的外れなコメントばかり。
修正して上司に提出しても「ピンとこない、やり直し」と突き返され、
再びAIに直させる → またダメ出し → AIに戻す…という 「AIと上司の無限ループ」 に陥りました。
結局、原稿は一向に完成しませんでした。
原因は明白で、「前提を共有せず命令だけで済ませようとした」こと。AIに命令一辺倒で臨むという前提が、典型的な失敗を招いたのです。
初心者に完璧なプロンプトは無理ゲー ― 失敗の根本原因
ここで強調したいのは、初心者に“最初から完璧なプロンプトを書け”というのは、1000%無理ゲーだということです。
- ゴールが完全に見えていて
- 言語化スキルも高く
- 問題を構造的に整理できている
そんなプロンプトを最初から書ければ、期待したアウトプットをAIから得られるでしょう。
しかし、それはかなり思考が整理された、“人間の完成形”でないと成立しない要求記述ではないでしょうか?
しかし、現実には到底ムリ。
だからこそ「できない社員が悪い」のではなく、「前提が間違っている」ことに気づく必要があります。
もちろん、最終的にAIが的確に動くためには「AIに最適化されたプロンプト」が役立つのも事実です。
ただし、それは“いきなり初心者に求めるもの”ではなく、AIとの会話を通じて整理された内容の出口として生まれるのが本来の姿です。
結果:社員がつまずきAI活用は定着しない
「生成AI研修でプロンプトを学べば十分」「プロンプト集を配布すれば十分」「AIには命令すれば十分」という3つの前提は、すべて誤りです。
この間違った前提のせいで、社員は入口でつまずき、嫌になり、結局AI活用は定着しません。
これは社員の能力不足ではなく、「AIの導入設計そのものの誤り」に原因があります。
まとめ:AI研修・プロンプト教育の誤解を超えるために
AI活用が広がらないのは「社員が努力しないから」ではなく、「誤った前提に縛られているから」。
特に「初心者がプロンプトを書けるはず」という前提は、まさに1000%無理ゲーと考えた方が良いでしょう。
では、社員が自然にAIを使える“正しい前提”とは何か?
そこにこそ、これからのAI定着のカギがあります。
AI導入を任されたご担当者は、AI活用の定着に苦心されていることと推察します。
もし、なかなか上手く行ってない場合には、「前提が誤っていたかも?」と思い返してみては如何でしょうか?
AIをどう位置づけ直すかがカギになります。
その答えは「会話から共創する」という新しいフレームを考えることです。
「後編」のご紹介
コラム前編では、プロンプト教育が無理ゲーで終わってしまう理由を「前提の誤り」に意識を向けてみました。
後編では、映画『ターミネーター』に例えながら、正しいAI共創のヒントとフレームを語ります。
ぜひ、ご覧下さい。
後編はこちら

映画 『ターミネーター』 に学ぶAI共創のヒントとフレーム
~<後編>プロンプト教育はなぜ無理ゲーなのか?~ AIを命令する相手にとどめるのか、会話から共創する相棒に育てるのか。映画『ターミネーター』に例えながら実体験と共に、AI活用を定着させる正しい前提を解説します。
弊社の生成AIサービスにご興味のある方は、以下の専用サイトをご覧ください。

DX推進でお悩みの方へ