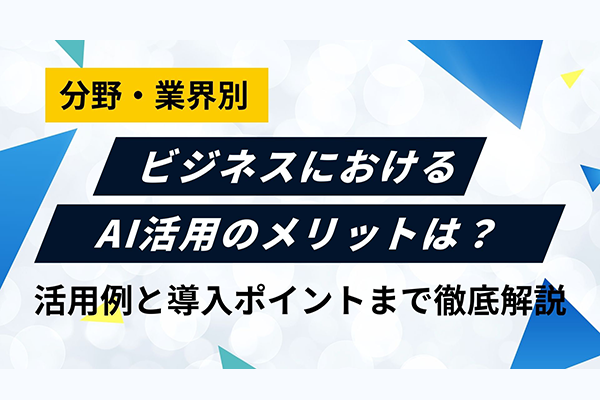【現場直送コラム】
映画 『ターミネーター』 に学ぶAI共創のヒントとフレーム
~<後編>プロンプト教育はなぜ無理ゲーなのか?~
更新日:2025年10月9日
株式会社ディジタルグロースアカデミア
カスタマーサクセス スーパーバイザー 柴田 佳幸

目次
導入:映画『ターミネーター』に学ぶAI活用の前提
映画『ターミネーター』(監督:ジェームズ・キャメロン)を覚えていますか?
シリーズ化され大人気のSF映画です。 本コラムで着目するのは、第1作と第2作の違いです。
同じアーノルド・シュワルツェネッガーが演じるターミネーターでも、第1作と第2作ではまったく異なる存在として描かれています。
- 第1作目のターミネーター: 「ジョン・コナーを殺せ」という命令を遂行するだけのマシン。人間との会話もなく、与えられたプログラムを実行するだけ。
- 第2作目のターミネーター: 「ジョン・コナーを守れ」という指令を受けつつ、ジョンとの会話を通じて人間性を学び、文脈を理解していく存在に変化して行く。最終的には命令を超えた自己判断(自己犠牲)に至ります。
この対比は、私たちがいま直面している「AI活用の前提」と、とてもよく似ていると感じます。
AIを「命令実行機械」とみなすのか、それとも「会話から共創する相棒」とみなすのか。
この違いが、AI定着の成否を分ける1つになるのです。
前編の振り返り:AI研修・プロンプト教育の誤った前提
前編では、AI導入においてよくある“誤った前提”を整理しました。
- 「AI研修でプロンプトを学べばAI活用が定着する」
- 「プロンプト集を配布すれば十分」
- 「AIには命令を投げれば動く」
これらはいずれも誤りです。特に、初心者に完璧なプロンプトを書かせるのは1000%無理ゲー。
では、正しい前提とは何か? 後編では、その答えを「喋る → サマる → 構造化する」という共創フレームで考えて行きます。
正しい前提:AIは命令でなく“会話から共創する相棒”
AIは単なる命令遂行型の機械としての存在だけではありません。
むしろ「曖昧な段階から一緒に考えられる存在」であり、共創の相棒として向き合うことで更に真価を発揮します。
そのための実践プロセスが、
「喋る → サマる → 構造化する」 という3ステップです。
ステップ1:AI活用は“喋る”から始めよう
曖昧でも喋ることでAI活用が進む
AI活用の入口で最も重要なのは、「喋る」ことです。
最初から完璧なプロンプトを書く必要はありません。むしろ曖昧な状態でいいのです。
AIに対して「とりあえず壁打ち」することで、心理的ハードルが下がり、会話の中で「自分は何をしたいのか」に自分自身が気づいていきます。
これはまさに、前編で問題視した「無理ゲープロンプト」の逆をいく体験です。
ターミネーター2との比較でわかるAIとの会話の価値
ターミネーター2のT-800が、ジョン・コナーとの会話を通じて人間性を学んだように、AIもまた会話を通じて文脈を理解します。(※)
命令を超えて「背景」「意図」「ゴール」を共有していくことで、AIはただの機械ではなく、思考を支える相棒へと変わっていくのです。
【体験談】契約書AI作成で見えた“文脈の力”
私自身も、サービス利用契約の作成をAIと一緒に進めた経験があります。
契約書は、単なる法律文書ではないと私は考えています。「契約書はお客様との物語」だと位置づけています。
- 何を提供するのか
- どのような条件で行うのか
- もしトラブルがあった場合はどう対処するのか
こうした「関係性の物語」を、文章として形にしたものが契約書です。
ところがAIに「契約書を作れ」と命令するだけでは、この物語はまったく反映されません。
私が実際にAIと会話したのは、背景や条件、想定されるリスクやお客様との関係性をAIに丁寧に説明し、会話を重ねながら作っていくプロセスでした。
するとAIは、ただのテンプレートではなく、私とお客様の物語を反映した契約書を提案してくれるようになったのです。
まさに「喋る」ことによって、AIが相棒として機能した瞬間でした。
AIを相棒として作成した契約書は、最終的には弁護士の先生(人間)に確認して最終版になりますが、弁護士からは「出来の良い契約書ドラフトだ」と感想を頂戴しました。
→ このアプローチは契約書に限りません。企画書、提案書、報告書、さらには日常のメール文まで、AIに文脈を伝えることは、あらゆる“文章作成”に共通して活かせる方法です。(※)
ステップ2「サマる」/ステップ3「構造化する」:AIに任せる最適化
次に重要なのは「サマる」と「構造化する」です。
- サマる:会話の内容をAIにいったん要約させて、お互いに理解違いの有無を確認する。
- 構造化する:サマリーを基に、AI自身に構造化を任せる。
人間が苦労して“立派なプロンプト”を書く必要はありません。
むしろAIに「この要約をもとに、最適な指示文(プロンプト)にして」と頼むことで、AIが自ら“AIが読み易い形”に変換してくれます。
ここで大切なのは、最初から人間がプロンプトを完璧に書こうとしなくても良いという気づきです。
プロンプトは人間が書くものではなく、AIが生み出すものだという前提に立つと、成果物の精度は一気に高まります。
まとめ:あなたのAI活用は命令型か、それとも共創型か?
最後にもう一度、映画『ターミネーター』の比喩に戻りましょう。
- ターミネーター1型扱い:命令を遂行するだけの機械 → 誤った前提 → 挫折と定着失敗へ。
- ターミネーター2型扱い:会話を通じて文脈を理解する相棒 → 正しい前提 → 共創と定着へ。
私たちがAIをどう使うかは、前提の置き方次第です。
命令型にとどめてしまうのか、会話型に育てるのか。
その選択が、AI活用の結果を大きく変えるのです。
→ まずはAIに向かって、今日の仕事の悩みを雑談してみてください。
曖昧な話題でも「喋る」ことで思考が整理され、自然に「サマる」「構造化する」ステップにつながっていきます。
今回ご紹介した「喋る・サマる・構造化する」という正しい前提は、前編で整理した“誤った前提”と対比することで一層理解が深まります。
ぜひ、前編『AI導入が定着しないのは“社員のせい”ではない~<前編>プロンプト教育はなぜ無理ゲーなのか?~』もあわせてご覧ください。
前編はこちら
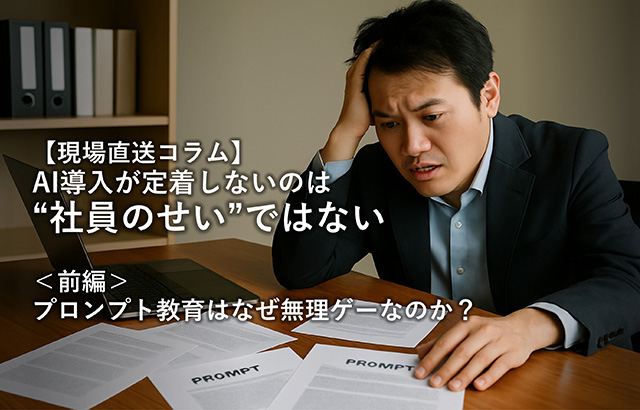
AI導入が定着しないのは“社員のせい”ではない
~<前編>プロンプト教育はなぜ無理ゲーなのか?~ AI導入の担当者がプロンプト教育に頼ってもAIは定着しません。今のやり方で成果が出ない理由と、その背景にある誤った前提を解き明かし、解決策を探って行きます。
弊社の生成AIサービスにご興味のある方は、以下の専用サイトをご覧ください。

※参照情報:AIに対する“文脈”の重要性に関する海外レポート
- 人間の状況・背景・意図を理解するには、文脈の共有が不可欠
- 単純な命令文だけでは、AIの理解がズレてしまう
- セルフ紹介・状況説明をAIに語ること自体が成功の鍵
「AIは“前提”を自動で察知する存在ではない。文脈を渡すのは人間の責任。」
PromptEngineering.org:「会話型と構造化のハイブリッドで思考を深める」- 会話型プロンプト:柔軟で直感的、初心者にもやさしい
- 構造化プロンプト:再現性が高く、応用領域に強い
- 初期は会話でAIと一緒に考え、後から構造化して整理するのが現実解
「プロンプト設計は“成果物”でなく、“思考過程”である」
DX推進でお悩みの方へ