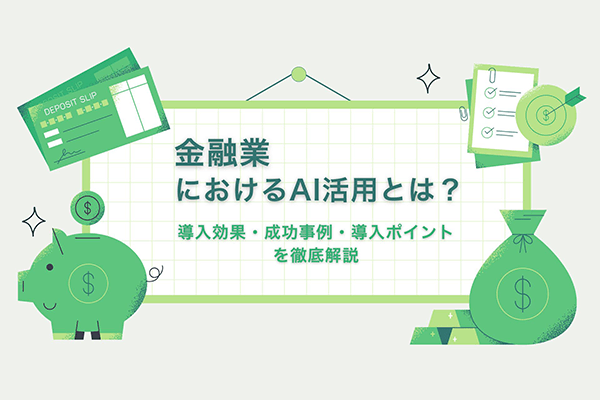AI時代の教育予算は“行動変化と成果”でみられる
──予算がつく提案の条件と再設計のヒント
更新日:2025年11月27日
株式会社ディジタルグロースアカデミア
カスタマーサクセス スーパーバイザー 柴田 佳幸

毎年やってくる、教育予算の検討時期。
「今年は何をやる?どの研修を?どこに頼む?」
そんな会話の裏で、あなたはふと感じていないでしょうか。
——このお金、本当に“成果”につながっているのか?
——現場は、何か変わったのか?
——経営層に、どんな成果説明をして、次の予算を通そうか?
一方で、経営者が本当に求めているのは、たった一言。
「Show me the money.(成果を見せてくれ)」
成果が見えない教育に、もはや予算はつけられない——それが今の時代のリアルです。
その問いに、あなたの施策と予算提案は応えられそうですか?
教育の“遂行率”や“受講率”ではなく、行動と成果を生み出し、それを説明できる設計になっているでしょうか。
このコラムでは、教育担当、DX・AI推進担当であるあなたが、
「今年こそは違うアプローチをしたい」と思える視点と仕組みを整理していきます。
今こそ、あなたのモヤモヤを言語化し、AI時代の教育を“再設計”するタイミングです。
目次
(この動画は本コラム原稿を元に、NotebookLMで生成しています。)
教育の努力はした、でも成果は?──教育担当のリアル
教育担当、DX・AI推進担当、あるいは人材開発の事務局——
あなたは、この役割を任されたとき、「限られた予算」「限られた時間」「協力を得にくい現場」
……そんな条件の中でも、工夫を重ねながら、社員教育を前に進めてきたことでしょう。
しかし今、時代は大きく変わろうとしています。
AIが業務の進め方を一変させ、仕事の成果とスピードに圧倒的な差を生み出し始めているのです。
そんな時代において、社員教育もまた、「何をやったか」ではなく、「社員の何が変わったか」が、
より厳しく問われるようになってきました。
本当に現場は変わっているか?
この研修が、あの施策が、行動を変え、成果を生み出しているか?
もし、自信を持って「YES」と言えないのだとしたら——?
これからの教育は、「とにかくやればいい」ものではありません。
AI時代を迎えた今、経営者ははっきりとこう考え始めています。
「教育予算をかけるなら、必ず“成果が出る投資”でなければ意味がない」
だからこそ今、教育担当であるあなた自身が、“教育を成果に確実に変える仕組み”の設計に、
もう一度向き合う時が来ています。
これはもはや、避けることのできないテーマなのです。
カルビー元CEO 松本晃氏が突きつけた、たった一言の本質
「Show me the money.」
カルビーをV字回復させた名経営者・松本晃氏が、幹部や社員に常に伝えていた言葉です。
意味はシンプル——「成果を見せてくれ」。
どれだけ頑張っても、どんなに良い研修をしても、経営者が最後に問うのはただ一つ
——「で、何が変わったのか?」
松本氏がカルビーで実践した、「教育=成果を出すための投資」という思想は、明確な成果を生みました。
- 売上高:1.8倍
- 最終利益:6倍
- 国内シェア:75%
そして、営業利益率は10%超を維持するまでの、強靭な経営体質へと進化したのです。
その成長を支えたのは、特別な手法や高額な研修ではありません。
「人を信じ、機会を与え、成果を問う」——たったこれだけの思想です。
そしてそれを貫く、シンプルかつ本質的な“仕組み”でした。
松本氏の経営は、温かく、そしてドライ。
一人ひとりのポテンシャルを信じながら、成果には徹底的にこだわる。
だからこそ彼は、「教育とは、“行動を変え、成果を生み出す仕掛け”である」と言い切れたのです。
この考え方は、AI時代の今こそ、ますます重みを増しています。
AIが仕事を加速させ、人の成果がますます可視化される時代に、
教育だけが“プロセス評価”で許される時代ではありません。
「Show me the money.(成果を見せてくれ)」
——それは、経営からあなたへのプレッシャーであり、同時に、教育の本質を再定義するヒントです。
成果が見えない教育にさよならを──これからの“投資基準”
「それっぽいことは学んだ。でも、何が変わったかはよくわからない」
——残念ながら、多くの現場から聞こえてくる教育施策への本音です。
これまでは、「受講者数」「理解度テスト」「アンケート満足度」などが主な評価指標でした。
しかし、それではもはや“経営の会話”になりません。
経営者はシビアに、こう問いかけて来るでしょう。
「行動が変わったのか?成果に影響が出たのか?」
成果が見えない。行動が変わらない。効果が測れない。
そんな教育は、AI時代において“最も投資対効果が低い支出”に映ってしまうでしょう。
ここで、私たちが問い直すべきことは明確です。
- なぜこの教育をやるのか?
- 誰の、どんな行動を変えたいのか?
- その変化が、どの成果にどう結びつくのか?
教育という“手段”の議論から、「成果に至るプロセス設計」の議論へ——
今改めて、従来施策を振り返り、そして、必要ならば変えるべきときです。
その際に必要なのは、研修や教材といった教育手段そのものよりも、
「どうすれば社員が“やってみたくなるか?”」という動機設計であり、
「どうすれば現場が“変化を歓迎するか?”という組織設計です。
そしてもうひとつ、欠かせないのが、教育施策の効果を判断する“投資基準”のアップデートです。
- 行動変化があったか
- 業務効率やミス削減に影響したか
- 現場が「続けたい」と感じているか
このような“経営につながる評価軸”を持たない限り、来年度以降の教育予算は、確実に削られていくでしょう。
今こそ、「効果が見えない教育」は潔く見直し、「行動変化と成果が見える教育」へとドライに選び直す時です。
来年度予算の再構築
──「従来型の教育費」から「AI時代の投資原資」へ
教育費——この言葉には、どこか「使い切らなければいけないもの」「余れば翌年削られるもの」
といった感覚が染みついていそうです。
でも今、見直すべきはその“予算の前提”です。
教育とは、“費用”ではなく“投資”である。
これは、先ほど紹介したカルビー元CEO・松本晃氏の明快な考え方でもあります。
そして投資である以上、「成果が出るところにこそ、お金を使う」ことが鉄則です。
成果が出ない教育は、たとえそれがどんなに数年続いてきたものであっても、
今こそ勇気を持って見直すタイミングに来ています。
特に今年度、AIという“成果を生み出す加速装置”が多くの企業に導入され始めた今、
教育もまた、こう問われています。
「AIを活かす仕組みとして、教育に投資するのか?」
「それとも、旧来の研修形式に“慣れ”でお金を払い続けるのか?」
来年度予算を再設計するにあたり、以下の3つの視点を提案します。
① 成果起点で予算配分を組む
- 「何に使うか」ではなく「何が変わるか」で予算根拠を説明する
② 教育“単体”ではなく、“仕組み+支援”に投資を振り向ける
- 教育動画+活用支援/現場サポート/成功事例の社内共有など
- 「どう活かされるか?」まで設計されて初めて、教育は“投資”になる
③ “継続されるかどうか”を予算評価の指標にする
- 一過性ではなく、「次年度も使いたい」と思われるものだけを残す
- 毎年ゼロから探すのではなく、「積み上がる資産」に予算をつける
これからの教育予算は、年度で“使い切るもの”ではありません。
“成果を生み、行動が変わり、積み上がっていく投資原資”として扱うものです。
それこそが、あなたの予算提案に対して、経営が「YES」と言いたくなる——新しい時代のロジックです。
まとめ──“成果で語れる教育”へ。あなたがその一歩を踏み出そう
これまで、あなたは真面目に、誠実に、社員の教育を考えてきたはずです。
受講者を集め、研修を企画し、レポートを整え、毎年の予算を通してきた。
その姿勢も、努力も、決して否定されるものではありません。
でも——時代は変わりました。
AIが生み出すスピード格差、成果の可視化、成長の加速。
教育という取り組みも、「理解」や「満足度」ではなく、「行動変化」や「業績改善」を問われる時代へと突入しています。
カルビーの松本晃氏は、こう言いました。
「Show me the money(成果を見せてくれ)」
経営からのこの一言は、今や“当たり前の前提”となりつつあります。
来年度の予算は、その問いに応えられるものでなければ、生き残れません。
あなたの中にも、ずっと感じていた違和感があるのではないでしょうか?
- 「この教育、本当に意味があるのか?」
- 「これを続けていて、会社は良くなるのか?」
そして、最後にもうひとつ、大切な問いを投げかけさせてください。
——その挑戦を支える“教育のパートナー”は、本当に今のままで大丈夫ですか?
あなたがこれから求められるのは、「成果を出す教育」の設計と実行です。
その要請に、今の教育業者、研修会社、支援パートナーは確実に応えられそうですか?
これまで続けてきた、教材、eラーニング、講義型研修……
もし、そこに少しでも「違和感」を感じているのなら、
ここまで読んできたあなたの“モヤモヤ”を無視せず、見直すタイミングは“今”です。
「Show me the money(成果を見せてくれ)」
それこそが、AI時代の社員教育における新しいゴールなのです。
私ども、ディジタルグロースアカデミアも「教材、eラーニング、研修」を提供しています。
ただし、提供して終わりではありません。
- デジタルツールを1人でも多くの社員が当たり前に使えるようになること
- 使えるようになって、社員の働き方が変わること
- 社員が変わって、組織と会社が変わって事業が成長すること
これにひたすらお客様と共に取り組んでいます。
「成果」にこだわり、人を育てる…、それが私どもが提供するサービスです。

できるひな形を入手する!! このひな形を元に上司に提案して、今年の教育設計を一歩進めましょう。
DX推進でお悩みの方へ