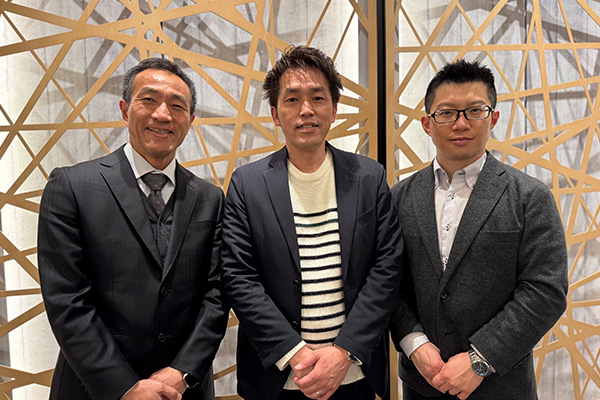育成の先の“成果”を現場が一丸となって生み出す
─センコーユニバーシティの実践型DXワークショップ

センコーグループホールディングス様

(左から1番目)藤井信茂様 九州センコーロジ株式会社 代表取締役社長
(左から2番目)⽥原清治様 九州センコーロジ株式会社 ⿃栖倉庫営業所 所⻑(取材当時)
(左から3番目)石井綾子様 九州センコーロジ株式会社 場内荷役事業部 基山LC
(左から4番目)一色智行様 センコーグループホールディングス株式会社 人材組織開発部 センコーユニバーシティ 係長(取材当時)
(左から5番目)南里健太郎様 センコーグループホールディングス株式会社 人材組織開発部 センコーユニバーシティ 部長(取材当時)
(左から6番目)大平祐輔 株式会社ディジタルグロースアカデミア
※クリックで動画が再生します。
「次の100年を作る人材育成」
──センコーユニバーシティの設立とミッション
― 今回のDXワークショップ実施の背景について教えてください。
 南里健太郎様
南里健太郎様- 南里様:
-
我々「センコーユニバーシティ」は2016年、センコーグループ創業100周年の節目に創設されました。次の100年に向けた新たな価値を創出するための人材を育てることが目的です。物流という労働集約型ビジネスを主軸とする我々にとって、人こそが最大の資産であり、そこに投資することが成長の鍵だと考えています。
私たちはオペレーションスキルの教育という「右手」だけでなく、イノベーションを生む「左手」としての役割にも力を注いできました。これは、オライリー氏が提唱する“両利きの経営”にも通じる思想です。新しい価値を創造するために、リスクを取ってチャレンジすることができる人材を育てたいと考えています。
―「センコーユニバーシティ」の一環として、DXワークショップを実施されたきっかけは何でしょうか?
- 南里様:
-
本格的な転機となったのはコロナ禍でした。デジタルが生活とビジネスの中心に一気に躍り出たことで、「できたらいい」ではなく「やらなければならない」フェーズに移ったと感じました。2016年から準備していたものの、本格的に加速したのは2020年以降です。
しかし我々には、そもそもどこから手を付ければよいのか分からないという課題もありました。内部だけで考えると、どうしても既存の改善思考にとらわれてしまう。その壁を突破するには、外部の専門知見が必要だと判断しました。
今回のワークショップでご一緒したチェンジ様、ディジタルグロースアカデミア様の存在は非常に大きかったです。単なる知識の提供にとどまらず、学びをいかに行動につなげるかという構造を丁寧に設計されたことで、実践的な成果に結びついたと感じています。
実践重視のワークショップ設計
──学びを現場に還元する仕組み
― 今回のワークショップは、単なる座学ではなく、実践重視が特徴でした。検討時にどのような工夫をされたのですか?
 一色智行様
一色智行様- 一色様:
-
受講者が研修後に現場で「実際にやってみる」ことを重視しました。私たちがチェンジ様、ディジタルグロースアカデミア様にご支援頂く前の企画では、学びの現場での実践・定着に課題がありました。。そこで今回は、学んだ内容をその場でアウトプットできる双方向型の構成にしました。
さらに、上司からの推薦書を事前に取得したり、受講後のシェア会を必須としたりと、職場とのつながりを強く意識した仕組みも取り入れています。
今回のプログラムは、「どのような課題に対して、どのようにツールを活用できるか」を一緒に考える時間を作れたことが非常に有効でした。ただツールの使い方を教えるだけではなく、「そのツールにどうやってたどり着くか」「どう調べるか」というスキルを重視してくださった点も大変ありがたかったです。
- 南里様:
-
企画を進める中で我々が目指す景色は、受講生が学びを得て行動変容に至り職場で実践し成果を産出す状態です。しかしながらその景色を見るために苦労を重ねて来ました。
今回のプログラムでは、学んで終わりではなく、その場で実践できる構成だったことが非常に重要だったと思います。チェンジ様やディジタルグロースアカデミア様は、ワークショップを現場と地続きに設計してくださり、組織の空気を変えるところまで寄り添ってくださいました
「やってみる」で変わった現場
──ワークショップ受講期間中の実践とその成果
― 実際に現場で改善を行った石井様、今回の取り組みについて詳しく教えてください。
 石井綾子様
石井綾子様- 石井様:
-
はい。私は九州センコーロジで、工場内倉庫の在庫管理業務を担当しています。これまで、お客様から紙で受け取る機械の稼働予定チャートを、Excelに手入力して管理していました。チャートも変更が多いため作業量も多く、属人化しており、非効率な作業が続いていたのが悩みでした。
今回の研修で「まずは自分の課題を選び、そこから着手する」ことを学び、自動化ツールの作成に挑戦しました。実は、きっかけは同僚からの「一番自分が困っていることを変えれば?」という一言でした。確かにそうだなと納得し、今回のテーマを決めました。
― 自動化によって、どのような変化が生まれたのでしょうか?
- 石井様:
-
作業時間としては、毎日60分ほどの削減です。1年で換算すると、30営業日分にも相当します。ただ、これは単なる時間の削減だけでなく、作業の標準化や属人化解消にもつながり、誰でも対応可能な体制が整いました。
さらに、今回作ったツールは、同様の業務を抱える他拠点にも展開が可能で、すでに2拠点での導入が進んでいます。工場内の限られたスペースをより効率的に使うためにも、在庫の流動が見える化されたことは大きなメリットです。
 (九州センコーロジ 鳥栖倉庫営業所 ※イメージ写真)
(九州センコーロジ 鳥栖倉庫営業所 ※イメージ写真)- 田原様:
-
私の立場から見ても、今回の取り組みは単なる業務改善にとどまらず、現場全体の意識変革のきっかけになったと実感しています。特に印象的だったのは、石井さんが自ら考えて行動に移した事に対し、周囲が自然とサポートし始めたことです。
 田原清治様
田原清治様- 田原様:
-
私は普段から、現場のメンバーに対して「改善できることがあったら一緒に考えよう」「やりたいことがあるなら遠慮なく言って」と伝えています。石井さんがツール作成に挑戦していると知ったときも、「周りの協力は私が話を通すから大丈夫」と伝え、サポートするようにしました。
結果として、ツールが完成した後は、周囲も自分ごととして捉えるようになり、「こういうのができるなら、うちの業務にも使えるかも」という声が自然に出てくるようになりました。特に、担当者が休んでも他のメンバーで業務を回せるようになったことは大きいです。以前は「休まれたらどうしよう」という空気がありましたが、今は「このツールがあるから大丈夫」と思える安心感がある。これは職場の雰囲気にも良い影響を与えています。
「学びの連鎖」が現場を動かす
──自然と広がった協働の空気
― ワークショップ中、職場での共有はどのように行われていたのですか?
- 石井様:
-
正直に言うと、最初は「DXって難しそう」という空気がありました。受講時には、「静かな環境でイヤホンなどを付けて受講するように」との連絡もありましたが、実はスピーカーで音声を流しながら事務所内で受講していたのです。すると、自然と周りの人たちも耳を傾けるようになって、「こんなことができるの?」「この職場でも使えるのでは?」と声が上がるようになりました。
― まるでラジオ番組ですね。あえてスピーカーで音声を流しながら受講されていたとは、驚きました。
- 一色様:
-
私も驚きでしたが、石井さんが自然と「学びのハブ」になってくださったことがとても嬉しかったです。研修設計の中でも「どうすれば学びを職場へ還元できるか」という点を特に重視していました。
今回の研修では、受講者にとって“実践”がゴールではなく“周囲の変化を生み出す”ことが重要でした。チェンジ様やディジタルグロースアカデミア様は、そうした我々の意図を深く理解し、受講生一人ひとりが動き出しやすいようサポートしてくださいました。
組織を変える“背中の押し方”
──トップの旗振りがつくる安心感
― トップとして、藤井様が今回の取り組みにどのような期待や方針を持っておられたのか、お聞かせください。
 藤井信茂様
藤井信茂様- 藤井様:
-
物流業界全体が今、大きな転換点に差しかかっています。人手不足や働き方改革、設備投資の抑制、そしてお客様からの高い品質要求──そのすべてに応えるには、従来のやり方ではもう限界があると痛感しています。
その中で、DXは避けて通れない重要なテーマです。ただし、これを現場任せにしてしまうと、どこかで「他人事」になってしまい、なかなか進みません。だからこそ、私は「DXは経営課題であり、現場と経営が一体となって進めるべきもの」という意識を強く持っています。
そのために、私は社内で繰り返し「やっていいんだ」「失敗してもいいから挑戦してみよう」と発信してきました。加えて、現場からチャレンジの芽が出た時には、できるだけ早く視察に行き、担当者の話を直接聞いて「ちゃんと見ているよ」「応援しているよ」というメッセージを伝えるようにもしています。
今回の石井さんの取り組みに対しても、早い段階からどんな工夫をしているのか、どういった成果が出始めているのかという情報を報告ベースだけでなく、実際に現地に足を運んで確認しました。「現場がやってくれていることに、経営が反応する」という姿勢を示すことが、現場のモチベーションを高める一番の近道だと考えているからです。
―「現場が動きやすくなる環境づくり」に、経営側としてもかなり意識を払っておられるのですね。
- 藤井様:
-
はい。「制度があるから使いなさい」ではなく、「やりたいことをサポートするよ」という姿勢をとるようにしています。今回のような研修を受講して終わりではなく、「何かやってみようかな」と行動に移すためには、本人の意欲だけでなく、職場の空気や上司の姿勢、そして経営陣の後押しが不可欠だと考えています。
実際、今回の取り組みの裏側では、私だけでなく管理職層にも「受講者を孤立させないように」「何か動きがあったら支えてあげよう」と伝えていました。研修の成果が“現場に根づくかどうか”は、トップだけでなく、各レイヤーの反応スピードにかかっていると思います。
「できた」から「伝えたい」へ
──石井様のこれから
― 石井様、今回の経験を通じて、ご自身の意識にどのような変化がありましたか?

- 石井様:
-
正直、初めは「自分にできるだろうか」と不安でした。でも今回の成功体験を通じて、「やればできる」「自分にも現場を変える力がある」と実感できました。
今は、学んだことをもっと周りの人に伝えていきたいという思いがあります。私自身が受講前に不安を感じていたからこそ、今後は誰かの背中を押せる存在になりたいです。
もし機会があれば、社内でミニ講座のような形でツール活用や業務改善の方法を紹介していけたらと考えています。
- 一色様:
-
石井さんのような「伝える人材」が現場に生まれることこそ、私たちが一番目指していた姿です。DXはツール導入では終わりません。自らの言葉で語り、周囲を動かす人が増えてこそ、本当の意味での変革が始まるのだと思います。
最後に
──「共に走る」パートナーとして
― 今回、チェンジ様・ディジタルグロースアカデミア様をパートナーに選ばれた理由と、今後の期待についてお聞かせください。
- 南里様:
-
なんといっても、成果が上がったことです。今回の成果を見て、「お願いして本当に良かった」と心から感じています。単なるスキル研修にとどまらず、「どう学びをマインドの変化、行動に変えるか」「現場に変化・成果を生むにはどうすればよいか」といったコーススタート前の企画段階の打合せでの我々の想いを具現化する深い設計に支えられたプログラムでした。
大平さんの講師の進行もとても丁寧で、受講者一人ひとりの反応や理解度に目を配りながら、決して置き去りにすることなく進めてくださった点が印象に残っています。専門的な内容でありながらも、親しみやすく、実際の業務と結び付けながら話を展開してくださったことで、受講者の集中力も高く保たれていたと思います。
ツールの使い方だけでなく、調べ方、考え方、そして“やってみる勇気”を引き出してくださった点が非常に素晴らしかったです。
- 一色様:
-
伴走型のフォローも印象的でした。受講生のペースに合わせて、柔軟に対応していただけたことが、最終的な定着や成果に大きく貢献していたと感じています。
また、大平さんが講師として時折交えるユーモアや問いかけによって、受講者同士の間でも自然と対話が生まれ、学びの場としての熱量が高まっていたことも、現場で聞いていて感じました。単なる説明に終始せず、「実践につながる納得感」を引き出していただいたと思っています。
- 藤井様:
-
今回の取り組みをきっかけに、我々としてもDXへの関心が一層高まりました。今後もこうした実践型の研修を継続しながら、現場に小さな成功体験を積み重ねていきたいと考えています。チェンジ様、ディジタルグロースアカデミア様、センコーユニバーシティ事務局の皆様の熱意あるご支援が、受講者の行動変容を確実に後押ししてくださったと実感しています。
 (九州センコーロジ 鳥栖倉庫営業所 トラック画像 ※イメージ写真)
(九州センコーロジ 鳥栖倉庫営業所 トラック画像 ※イメージ写真)DX人材育成・研修・
コンサルティング
デジタル人材育成にお悩みの方は、
ぜひ一度ご相談ください。