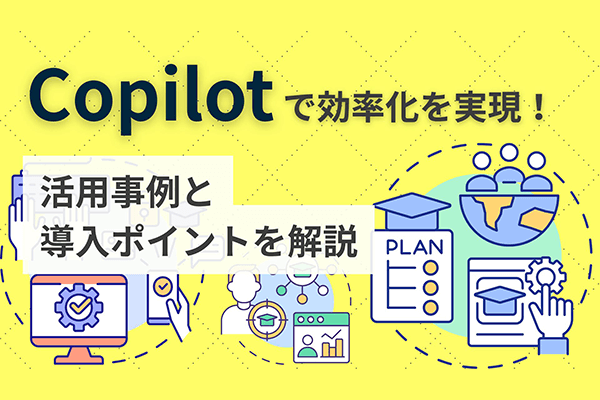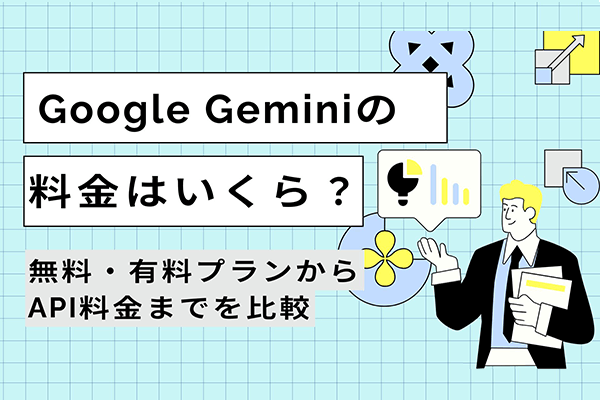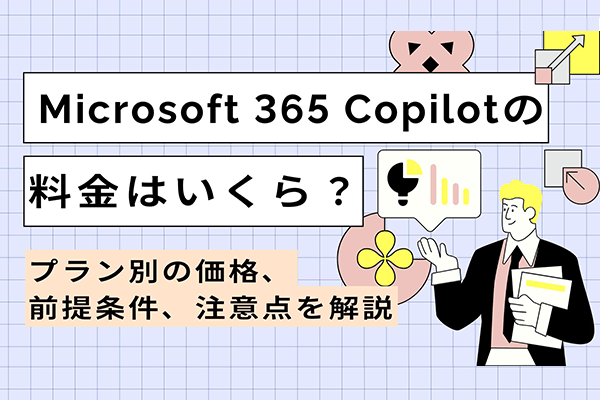【AI迷子脱出コラム】
第2回 AIエージェントとは何か?
─誰が使ってくれるのか分からない、
“ユーザー迷子”にならないための組織を俯瞰する目
更新日:2025年10月23日
株式会社ディジタルグロースアカデミア
カスタマーサクセス スーパーバイザー 柴田 佳幸

AIエージェントを導入したはずなのに、思ったほど使われない。
そんな現場の声を、私たちはこれまでにたくさん耳にしてきました。
「やり方が悪いのか」「もっと教育が必要なのか」──そう思って取り組んでも、なぜか現場ウケが悪いまま。
実はこの“停滞”こそが、AI導入における第二の迷子なのかもしれません。
第1回のコラムでは、こうお伝えしました。
「AI導入が進まない最大の理由は、“誰が使うのか”“誰にとっての価値なのか”が見えていないことだ。」
この第2回では、さらにその一歩先へ。
“誰が、どんな得をする”のかをハッキリさせれば、AIは組織で使われ、活き始める。
─このテーマを中心に考えていきます。
AI導入を「技術の導入」や「テクニックの習得」としてではなく、経営層、推進部門、人事、現場──それぞれの立場が抱く想いと“得(メリット)”のかたちに焦点を当ててみましょう。
登場人物すべてを見える化したAll Star Cast(オールスターキャスト)の視点から、組織の中でAIが“動き出す”ための構造を、一緒に紐解いていきます。
目次
DXブームからAIブームへ──変化の波は“同じ課題”を繰り返している
DXブームとAIブームのデジャビュー構造
結論:DXとAIは“テーマ”こそ違えど、構造と停滞の仕組みは驚くほど同じ
「DX」「リスキリング」「生成AI」「AIエージェント」──。
この数年、企業を取り巻く言葉は次々と入れ替わってきました。
しかし、ブームのたびに現場で起きている“構造的な現象”は、驚くほど似ていると感じませんか?
技術の名前は変わっても、現場の混乱の構造は変わっていない。
「DX」という看板が「AI」や「エージェント」という言葉に置き換わっただけで、結局は「何を変えたいのか」「誰のための変化なのか」が見えないまま、導入が先行してしまう。
それが「DXブームとAIブームをデジャビューと感じてしまう」要因かもしれません。
この構造を抜け出すために、“実際に現場でAIを使う人と組織の視点”から考察を行きましょう。
比較表:DXブームとAIブームの構造比較
結論:DXもAIも「導入が目的化する」構造に陥りやすいが、本質的な変革には“組織内の関係設計”が必要
| 観点 | DXブーム(2019〜2022頃) | AIブーム(2023〜) | 共通する構造 |
|---|---|---|---|
| 旗印 | 「変革」「デジタル化」「リスキリング」 | 「AI活用」「生成AI」「エージェント化」 | 大義はあるが、現場が実感できない |
| 推進役 | DX推進部門・IT企画部 | AI推進室・データ戦略室 | 部門主導で始まり、“自分ごと化”されにくい |
| 現場の反応 | 「忙しくてDXどころでは…」 | 「AIは自分の仕事に関係ある?」 | 主体ではなく“対象”にされている |
| 成功企業の特徴 | 小さく始めて、成功体験を共有 | 部署単位で“得”を定義し共有 | 共通:現場の“得”を起点に設計している |
| 失敗企業の特徴 | 部門任せ・ツール導入で満足 | PoC止まり・試しただけで終わる | 共通:目的が「導入」で終わっている |
両者に共通しているのは、「導入が目的化する」構造です。
“何のために変えるのか”が定義されないまま動き出し、現場が置き去りになる。
これが、DXとAIの両方に見られる“変革の停滞構造”です。
DX推進が声高に言われた時期、多くの企業は「デジタル化=効率化」と理解していました。
一方で、AIの時代には「AI=業務自動化」「AI=時短」といった視点が多いようです。
しかし、AIエージェントがもたらす価値には、人の判断や創造を支援し、人と組織をつなぐこともあります。
ここで大切なのは、「技術の導入」ではなく「組織内で関係の設計」にも視線を持つこと。
同じ課題構造を繰り返さないようにしたいものです。
次の章では、この構造的デジャビューを生み出している出発点──
「誰が旗を振っているのか」という導入パターンから課題を明らかにしていきます。
AI導入の出発点の違いが生む課題マトリクス──誰が旗を振るのか
導入の4パターン|出発点の違いで何が起きるのか?
結論:AI導入は「誰が旗を振るか」で目的の見え方と現場の温度が大きく変わる。
AIエージェント導入の“はじまり方”には、いくつかの典型パターンがあります。
それは、単に「どの部署が主導するか」という違いにとどまりません。
旗を振る人が変わると、導入の目的の定義も、現場の受け止め方もまったく異なるのです。
私たちディジタルグロースアカデミア(DGA)が多くの企業を支援してきた経験から見えてきたのは、導入の出発点と課題はおおむね次の4つに分類できるということでした。
AI導入の出発点 4パターンと特徴
| 導入パターン | 主導主体 | 導入の動機・背景 | 現場に起きやすい課題 |
|---|---|---|---|
| ①経営層・事業部長主導型 | 社長・役員・事業部長 | 「競合に遅れたくない」「変革を進めたい」 | 方針はあるが現場との温度差が大きく、“やらされ感”が生まれやすい。 |
| ②DX/AI推進部門主導型 | DX推進室・AI戦略室 | 「技術的な実現可能性を探りたい」「モデルケースをつくりたい」 | 構造設計は進むが、実装で止まりやすい。現場理解の浅さがネック。 |
| ③人事・教育部門主導型 | 人事部・研修部門 | 「社員のリスキリング」「AIリテラシー向上」 | 学習機会は増えるが、業務適用との橋渡しが弱く、“学び止まり”になる。 |
| ④情報システム部門主導型 | 情シス・IT運用部門 | 「社内システムをAIで最適化」「効率化を進めたい」 | 技術中心になりがちで、“業務の文脈”と噛み合わない。 |
現場との距離が生む“推進のズレ”
結論:AI導入は出発点がどこであっても、現場との接続設計を欠くと“使われないAI”に陥る。
この4つの導入パターンは、それぞれ得意なフェーズと苦手なフェーズがあります。
- 経営層主導は、意思決定が早い反面、現場の共感を得にくい。
- 推進部門主導は、上層部との整合性をとりやすいが、実装段階で孤立しやすい。
- 人事主導は、教育の土台を築けるが、現場活用につなげるための“実装”が弱い。
- 情シス主導は、システム整備が早いが、現場の“使いたい理由”が浮かばない。
つまり──どのようにAIエージェント導入を始めても、必ずどこかにズレが生じてしまう。
それは失敗ではなく、構造上“自然に起きること”だと考えれば、多少気が楽になります。
重要なのは、そのズレを放置せず、どうお互いに橋をかけるかを設計すること。
ここにこそ、AIエージェント導入を“使われる仕組み”へと変えるための第一歩があります。
現場の多層構造──職場と役職によって違うAIへの課題と期待値
現場の4領域|それぞれの現場で行動価値感が異なる
結論:AI導入の本質は「仕事の仕方を変えること」であり、その前提となる価値観は職場ごとに異なる。
現場という言葉は一つでも、実際にはそれぞれの部署・現場には違った行動価値感があります。
AIエージェント導入を考えるとき、この『何を大切にして働いているのか』という価値感を無視すると、どれだけ優れた仕組みを導入しても動き出しません。
私たちが企業支援の現場で見てきた代表的な“4つの現場領域”を見ていきましょう。
4つの現場領域と、それぞれの行動価値感
| 現場領域 | 行動価値感の特徴 | AI導入への典型的な反応 |
|---|---|---|
| ①営業・販売部門 | 「数字で成果を出す」「顧客との関係を守る」 | AIを“効率化ツール”として期待する一方、顧客対応の“人の勘”を軽視されることに警戒心。 |
| ②管理・バックオフィス部門 | 「正確に」「ミスなく」「ルールを守る」 | AIの自動化に好意的だが、システムトラブルや責任所在の不明確さに不安。 |
| ③開発・技術・企画部門 | 「新しいものを創る」「仕組みを改善する」 | AIを“共創のパートナー”として捉えやすいが、自由度が制約されると抵抗感。 |
| ④情報システム・運用部門 | 「安定稼働」「トラブル防止」「守りの品質」 | 技術視点では理解が早いが、“業務改善の主体”と誤解されやすく、負担増につながることも。 |
「現場」といっても、動機づけの軸や“得たいメリット”がまったく違うことが分かります。
そのため、「AIを入れれば皆が助かるはずだ」という一律の発想では、必ずどこかで“価値観の摩擦”が生まれてしまいます。
重要なのは、この違いを“導入の障害”ではなく“設計要件の1つ”として捉えること。
つまり、AI導入とは単なるシステム実装ではなく、現場の価値観を尊重しながら再設計していくプロセスなのです。
経営層・中間管理職層・現場層の三層構造に見える課題
結論:三層の温度差が、AI導入の“心理的な距離感”を生む。
DGAが実施した1万人以上の「デジタル活用アセスメント※」データ分析の結果から見えてきたのは、組織内の“縦の構造”における明確な温度差でした。
どの業種・業界でも、経営層・中間管理職層・現場層の三層間で、「方針への納得度合い」「課題解決への行動意欲」「仕事の報われ感」に差が見られました。
このコラムをお読みの方々にも、心当たりがあるのではないでしょうか?
この三層の温度差こそが、AI導入における“心理的な距離感”を生む構造的要因です。
※デジタル活用アセスメント

- 【AI活用とDXに向かう企業の経営層と推進担当は必見!】AI導入の成否を決めるのは”テクノロジー”ではなく『組織の土台』初公開!8,000名アセスメント分析が明かす構造的課題(2025年08月21日掲載)
- ニュースリリース:~「デジタル活用アセスメント」統計分析から得られた示唆~(2025年08月21日掲載)
三層の特徴とAI導入における意識傾向(DGA分析より)
| 層区分 | 意識・行動の特徴 | AI導入における傾向 |
|---|---|---|
| 経営層 | 危機感と推進意欲が高い。変化を「企業の生存条件」と捉える。 | 早期導入を決断しやすいが、現場理解が追いつかないケースも多い。 |
| 中間層(管理職) | 変化には慎重。日々の業務維持責任が重く、リスク回避志向が強い。 | 方針を理解しつつも、現場への展開でブレーキ役になりやすい。 |
| 現場層(一般社員) | 実務に直結しない変化には関心が薄く、“静観”傾向。 | 「自分に関係あるのか」が見えず、導入後も活用が定着しにくい。 |
この三層の意識ギャップは、個人のモチベーションの問題ではなく、構造的な現象です。
DGAのアセスメントでは、特に「中間層」で
- 方針理解の乖離
- 課題解決行動の低下
- 成果の報われ感の欠如
が顕著であることが分かっています。
つまり、AI導入の停滞は「反対する人がいるから」ではなく、“誰も悪くないのに、心理的な距離感が起きている”という状態なのかもしれません。
あなたの組織にも“温度差”はありますか?
ディジタルグロースアカデミアが実施した 「デジタル活用アセスメント」 の1万人超データから、組織の構造に潜む課題をデータ分析したレポート。

組織の縦糸と横糸を編み上げる──AI導入を全体構造でとらえる
結論:縦(役職別の温度差)と横(職場ごとの価値観の差)の両面への考慮が、AIエージェント導入を成功に導く
ここまで見てきたように、AI導入が進まない背景には二つの構造的な違いがあります。
一つは横方向(職場・部門の違い)──それぞれの現場が大切にしている行動価値観の違い。
もう一つは縦方向(役職・立場の違い)──経営層・中間層・現場層の温度差。
この二つの軸が交わる場所こそが、AI導入の“本当の現場”です。
つまり、AIを“使われる仕組み”に変えるには、縦と横の両方の視点を重ねて考えることが大切になります。
| 観点 | 水平方向(職場・機能) | 垂直方向(役職・立場) |
|---|---|---|
| 理解すべき違い | 部門ごとの行動価値感・目的意識 | 層ごとの温度差・納得の度合い |
| 起きやすい課題 | 「AIの使い方」が職場で異なり、連携しづらい | 「なぜ導入するのか」が伝わり方で歪む |
| 必要なアプローチ | 部門を横断した共通課題を起点にする | 立場を越えた納得形成の場をつくる |
成功する企業は、この“縦×横の掛け算”を意識しています。
経営は方向を示し、現場は具体を語り、そのあいだをつなぐ中間層が翻訳者として機能する構造をデザインしています。
AIエージェント導入とは、単なる技術の実装ではなく、組織構造と現場への再接続が必要になります。
それを現実に動かすために、はめ込むべき“ピース”を次章で「AIエージェントの活用メリット」として整理します。
AIエージェントが提供できる価値を「役職×職場」から整理する
ここまで見てきたように、AIエージェントは、単なるAIツールではなく“組織の文脈に適応する存在”にしたいところです。
成功させる鍵は「誰にとって、どんな得があるのか」を具体的に棚卸ししてみることです。
前章で明らかにした縦(役職の温度差)と横(職場の価値観の違い)の構造を踏まえ、本章ではそれらを掛け合わせた“役職×職場”の視点から、AIエージェントが提供できる具体的な価値をマッピングします。
代表例:AIエージェントの「価値×役職×職場」マッピング
結論:AIエージェントの価値は、職種や部門によって“得られるメリット”の形が異なる。
同じAIエージェントでも、活躍の場は部門によってまったく異なってきます。
- 情報システム部では自動化のエンジンとして、
- 営業部では商談支援として、
- 人事部では教育やOJTのパートナーとして──
ここでは、代表的なマッピングを例として紹介します。
| AIエージェントの価値カテゴリ | 主に恩恵を受ける部署・職種 | 代表的な活用シーン |
|---|---|---|
| 業務効率化 | 情報システム部、総務、経理 | 定型処理やレポート作成の自動化 |
| 意思決定支援 | 経営企画部、事業部長、マネージャー層 | 売上・顧客データのAI要約/戦略検討支援 |
| コミュニケーション支援 | 営業、広報、人事 | メール・提案資料・面談要約生成 |
| 学習・教育支援 | 人事、教育研修部門 | 社員教育・OJT支援・リスキリング教材生成 |
| 創造性支援 | 企画、マーケティング、商品開発 | アイデア出し、キャッチコピー案出力 |
| 顧客体験価値 | 営業、カスタマーサクセス | 問い合わせ対応、顧客履歴要約 |
| 心理的負担軽減 | 管理職、現場リーダー | 会議準備・報告業務の効率化 |
| ナレッジ共有 | DX推進部、情報システム部 | 社内Q&Aやドキュメント検索AI |
| 品質向上 | 技術職、製造業務 | 設計書チェック、バグ検出支援 |
| 文化形成 | 経営層、人事 | 「AIを使う文化」の定着・ロールモデルづくり |
| イノベーション促進 | 新規事業開発、経営企画 | 新サービス構想、仮説検証の加速 |
このように、AIエージェントの価値は「どの技術を入れるか」ではなく、「誰がどうメリットを具体的に得そうなのか?」という現場の視点から整理することで、“使われるAI”のイメージが湧いてきます。
提案とまとめ──AI導入を“パズルのように”進める
ここまで、AI導入を阻む構造を「縦(役職)」と「横(職場)」の両面から見てきました。
そして、AIエージェントが提供できる価値を“役職×職場”のマトリクスで整理することで、組織の中で「誰が、どんなメリットを感じるのか」というパズルの全体像が見えて来そうです。
次に必要なのは、そのパズルへ実際にピースをはめていく計画と取り組みになります。
部署ごとのピースと価値を見つける
結論:すべてを一気に変えようとせず、“1ピースずつ整える”ことでAI導入は確実に動き出す。
どの部署から、どの課題から着手するか。
それは企業ごとに違って構いません。
重要なのは、「どのピースを先にはめると全体が動きやすくなるか」を考えてみることです。
例えば──
- 情報システム部は、セキュリティーのピースから。
- 営業部は、業務効率化のピースから。
- 人事部は、学習支援や文化形成のピースから。
すべてを一度に完成させようとするのではなく、ひとつのピースを丁寧に整え、隣のピースへ広げていく。
その積み重ねが、組織にとって自然で持続的なAI導入の流れをつくります。
ここまでお読みいただき、どうでしょうか?
これまでは、「AIエージェントの導入や活用」を大きな塊のように感じ、どこから着手すればいいのか分からない方も多いかと思います。
今日の第2回コラムでは、一気に進む改革プロジェクトのような大きな塊ではなく、各現場にいらっしゃる社員を想像して、小さな“はめ込み作業”のピースにまで考えてみる試みをしました。
最初から全体を完璧に設計する必要はありません。
たとえば、「誰のどんな困りごとを少しでも軽くしようか?」──その問いを出発点にすればいい。
1ピース、また1ピースと現場に合った形で整えていくうちに、組織全体のAI導入の流れが自然と見えてきます。
ぜひ、職場ごとにはめ込むAIのピース(=各位にとってのメリット)を見つけてみてください。
次の一歩を“自社仕様”で始めてみませんか?
DGAオリジナルのプロンプトテンプレート 「AIエージェント導入支援ファシリテータ」 を公開中。
自社の現場課題に沿って、導入ステップや議論設計をAIがナビゲートします。

次回予告:第3回「AIエージェント導入の“流れ”を描く──実践の段取りで見る組織の動かし方」
ここまでの第2回では、AIエージェント導入を“平面構造”としてとらえ、縦(役職)と横(職場)の違いを整理し、そこにどんなピース(価値)をはめるべきかを考えてきました。
しかし、AI導入が組織の中で本当に“動き出す”ためには、そのピースをどの順番で、どのように動かしていくのか──時間軸と場所の段取りが大切になってきます。
次回の第3回では、AI導入を時間軸も意識した「立体構造」としてとらえ、“動かし方”の段取り=実践フェーズを具体的に描いていきます。
立ち止まっていたパズルが、いよいよ組織の中で動き出すよう、一緒に進めて参りましょう。
読者特典:AIエージェント導入の壁打ちを、AI自身と始めてみませんか?
本コラムの内容を踏まえ、自社のAI導入計画を整理できる「AIエージェント導入支援ファシリテーター」のプロンプトを特別公開。チームで使える壁打ちAIと、今日から導入の道筋を描いてみましょう。

「AIエージェント導入支援ファシリテーター」の使い方
- プロンプト(Wordファイル)をダウンロードしたら、そのWordファイルのままAIにUPロードしてください。
ファイル名=「AIエージェント導入支援ファシリテータS(JSON).docx」 - 次にAIへ、「このファイルに記載の内容を実行してください」と指示してください。
第1回はこちら
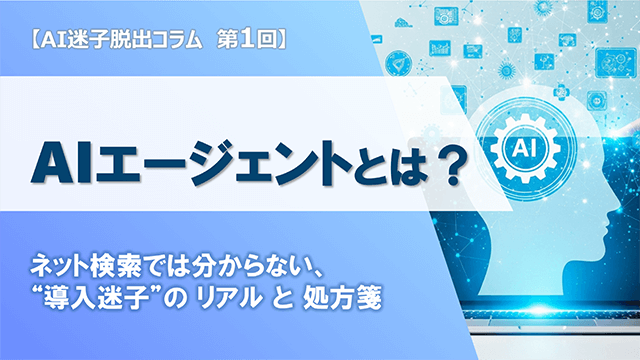
第1回 AIエージェントとは何か?
─ネット検索では分からない“導入迷子”のリアルと処方箋 AI導入の初期混乱は“失敗”ではなく必然。本記事では、AI導入担当者が直面する“導入迷子”のリアルを整理し、AIエージェント活用の3つの視点から、正しい第一歩の見つけ方を解説します。
AI導入を“使われる仕組み”に変えたい方へ