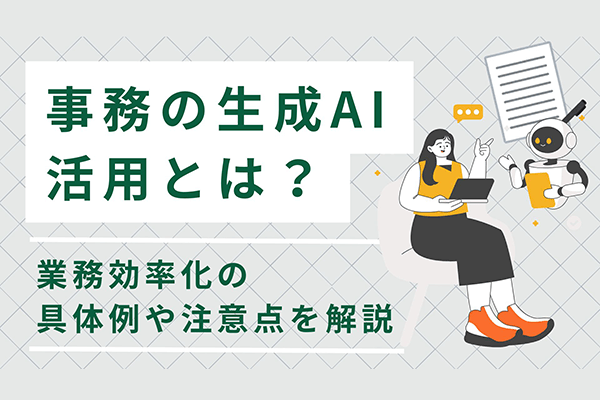DX人材育成の進め方とは?育成のポイントを詳細解説!
更新日:2025年11月13日

多くの企業がデジタルトランスフォーメーション(DX)の重要性を認識し、その推進に取り組んでいます。しかし、最新のITツールを導入し、立派な戦略を描いただけでは、DXは決して成功しません。その成否を分ける最大の鍵は、変革を担う「人材」の存在です。
独立行政法人情報処理推進機構(IPA)の調査によれば、DXに取り組む企業の実に8割以上が「人材の不足」を課題として挙げており、これがDX推進の最大の障壁となっています。
外部からの採用が困難な今、企業が競争力を維持し、成長を続けるためには、社内でDX人材を育成(リスキリング)していくことが不可欠です。この記事では、DX人材とは何かという定義から、育成を成功に導くための具体的なステップ、そして先進企業の事例までを分かりやすく解説します。
参考:IPA 独立行政法人 情報処理推進機構 ─ プレス発表「日本・米国・ドイツ企業のDX推進状況を調査した「DX動向2025」を公開」
目次
なぜ今、DX人材の育成が急務なのか?
DXは、単にデジタルツールを導入する「IT化」ではありません。デジタル技術を前提として、ビジネスモデルや業務プロセス、さらには企業文化そのものを変革し、新たな価値を創造する取り組みです。この変革をリードし、実行できる人材がいなければ、DXは「掛け声」だけで終わってしまいます。
DX推進の最大の壁は「人材不足」
前述の通り、多くの企業がDX人材の量と質の両面で課題を抱えています。特に、ビジネスの課題を理解し、それをデジタル技術でどう解決するかを構想できる人材は、市場全体で不足しており、採用による確保は極めて困難です。そのため、自社のビジネスを深く理解している既存社員を、DX人材へと育成・再教育(リスキリング)するアプローチが、最も現実的かつ効果的な解決策として注目されています。
関連記事

DX人材とは?必要とされるスキルと役割
企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進する上で、DX人材の育成は避けて通れない重要な課題です。経済産業省と情報処理推進機構(IPA)は、DXを推進する人材に求められる能力を「デジタルスキル標準」として定義しています。この指標は、DX人材の役割や必要なスキルを明確化し、育成の指針とすることを目的としています。自社にとってどのような人材が必要かを見極め、計画的な育成を進めるための羅針盤となるでしょう。
DXを推進する人材の5つの役割
「DX推進スキル標準」では、DXの中核を担う人材を5つの類型に分類しています。これらは、DXに関する企画・立案を主導する「ビジネスアーキテクト」、顧客視点で製品やサービスを設計する「デザイナー」、データ解析を担う「データサイエンティスト」、システムの実装を行う「ソフトウェアエンジニア」、そしてセキュリティを確保する「サイバーセキュリティ」です。これらの専門性を持つ人材が連携し、協働することでDXは強力に推進されます。
| 役割(人材類型) | 主なミッション |
|---|---|
| ビジネスアーキテクト | DXの目的を設定し、ビジネス変革のプロセスを主導する |
| デザイナー | 顧客・ユーザー視点で体験価値をデザインし、製品・サービスを設計する |
| データサイエンティスト | データを解析し、ビジネスに活用するための洞察を導き出す |
| ソフトウェアエンジニア | デジタル技術を活用したシステムの設計や実装、インフラ構築を担う |
| サイバーセキュリティ | ビジネスの持続性を確保するため、サイバーセキュリティリスク対策を担う |
全てのビジネスパーソンが身につけるべき能力
DXは、一部の専門人材だけで実現できるものではありません。経済産業省が定める「DXリテラシー標準」では、役職や職種に関わらず、全てのビジネスパーソンが身につけるべきマインドや知識、スキルが示されています。具体的には、DXの必要性を理解し、データやデジタル技術を業務で活用するための基礎的な能力がこれにあたります。全ての従業員のリテラシーを底上げすることが、組織全体のDX推進力を高めるための第一歩となります。
DX推進の役割を担う人材に必要なスキル
DXを推進する5つの役割を担う人材には、それぞれの専門性に加えて、共通して求められるスキル領域が存在します。これらは「共通スキルリスト」として、「ビジネス」「データ」「テクノロジー」といったカテゴリーで整理されています。例えば、ビジネス課題を的確に捉え解決策を考える能力や、データを適切に扱う知識、最新のデジタル技術に関する知見などが挙げられます。これらのスキルをバランス良く身につけることが、DX人材育成の鍵となります。
関連記事

参考:METI/経済産業省 ─ デジタルスキル標準
人材育成を成功させる5つのステップ
DX人材の育成は、闇雲に研修を受けさせるだけでは成功しません。経営戦略と連動した、計画的なアプローチが不可欠です。
手順1:経営戦略と連動した人材像を定義する
まず最も重要なのは、「自社がDXによって何を目指すのか」という経営戦略を明確にし、その実現のために「いつまでに、どのようなスキルを持つ人材が、何人必要なのか」という具体的な人材像と目標を定義することです。この最初のボタンを掛け違えると、育成そのものが目的化してしまいます。
手順2:現状のスキルレベルを可視化する
次に、全社員を対象としたスキルアセスメントなどを実施し、現状の人材レベルを客観的に把握します。誰がどのようなデジタルスキルや潜在能力を持っているのかを可視化することで、育成対象者の選抜や、目標と現状のギャップを埋めるための育成計画を具体的に立てることができます。
手順3:育成体系と具体的なプログラムを設計する
定義した人材像と、現状のスキルギャップに基づき、育成の全体像(育成体系)を設計します。全社員向けの「DXリテラシー研修」、選抜メンバー向けの「専門スキル研修」、管理職向けの「DXマネジメント研修」など、階層や役割に応じたプログラムを組み合わせることが重要です。
手順4:Off-JTとOJTを組み合わせ実践の場を提供する
研修(Off-JT)で知識をインプットするだけでなく、実際のDXプロジェクトに参加させるOJT(On-the-Job Training)の機会を提供することが、スキルを定着させる上で最も効果的です。学んだ知識を実践で使い、試行錯誤する経験こそが、本当の意味でのDX人材を育てます。
手順5:挑戦を評価しキャリアパスを示す
DXへの貢献や新しいスキルの習得を、人事評価制度に明確に位置づけることが重要です。また、DX人材としての専門性を高めていくキャリアパスや、相応の処遇を用意することで、学習へのモチベーションを高め、育成した人材の社外流出を防ぎます。
関連記事

なぜDXがうまくいかないか?
多くの企業がデジタルトランスフォーメーション(DX)の重要性を認識し、取り組みを進めていますが、その道のりは決して平坦ではありません。実際には、思うような成果を出せずにいるケースが多く見られます。その背景には、人材不足やビジョンの欠如、既存システムの複雑化といった、企業が共通して直面する根深い課題が存在します。これらの課題を一つずつ理解することが、DX成功への第一歩となります。
DXに取り組まない理由
DXが進まない以前に、一部の企業ではDXへの取り組み自体が始まっていません。その主な理由として、「DXの必要性を感じていない」「知見やノウハウがない」「対応できる人材が社内にいない」といった点が挙げられます。特に、日々の業務に追われ、新たな変革に着手する余裕がないと感じている企業も少なくありません。また、多額のIT投資が必要になるというイメージから、予算確保の面で二の足を踏むケースも見受けられます。
DXの定義が曖昧
DXがうまくいかない一因として、DXの定義が曖昧なまま進められていることが挙げられます。経済産業省はDXを「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」と定義しています。つまり、単にITツールを導入する「デジタル化」とは異なり、デジタル技術を手段としてビジネスモデルそのものを変革することがDXの本質です。
参考:METI/経済産業省 ─ 産業界のデジタルトランスフォーメーション(DX)
DX推進に向けて取り組むべき課題
DXを推進する上では、様々な課題が障壁となります。最も深刻な課題の一つが、DXを牽引する専門的なスキルを持った人材の不足です。さらに、経営層のDXに対する理解が不十分であったり、全社で共有されるべきビジョンや戦略が明確でなかったりすることも、推進の妨げとなります。加えて、老朽化した既存システム(レガシーシステム)が足かせとなり、新しい技術の導入を困難にしているケースも少なくありません。
| 課題の分類 | 具体的な課題内容 |
|---|---|
| 人材 | DXを推進できる専門人材が社内にいない、育成のノウハウがない |
| 経営・ビジョン | 経営層のコミットメントが不足している、明確なビジョンや戦略がない |
| 組織・文化 | 部署間の連携が取れていない、変化に対する現場の抵抗がある |
| 技術・システム | 既存システムが老朽化・複雑化しており、データ連携が困難 |
| 予算 | DX推進のための十分なIT投資予算が確保されていない |
DXをうまく進めるには
DXを成功に導くためには、まず経営層が強いリーダーシップを発揮し、明確なビジョンを策定して社内全体で共有することが不可欠です。その上で、全社的な大きな変革を目指すのではなく、特定の部門から小さく始めて成功体験を積み重ねる「スモールスタート」が有効とされています。そして何よりも重要なのが、DX推進の中核を担う人材の確保と育成です。外部からの採用と並行して、社内での計画的な人材育成に取り組むことが、持続的なDX推進の鍵となります。
DX人材の具体的な育成方法
育成プログラムを設計する際の、具体的な手法をご紹介します。
| 育成方法 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 研修・eラーニング |
|
|
| OJT |
|
|
| 資格取得支援 |
|
|
研修・eラーニング
外部の専門機関が提供する研修や、オンラインでいつでも学べるeラーニングは、DXに関する基礎知識や最新の技術動向を、効率的に全社へ展開するのに適しています。自社の課題に合わせたカスタマイズ研修を依頼するのも有効です。
OJT(On-the-JobTraining)
前述の通り、最も重要な育成方法です。実際のDXプロジェクトにアサインし、経験豊富なリーダーのもとで課題解決に取り組む中で、知識は初めて生きたスキルへと昇華します。
資格取得支援
ITパスポートやデータサイエンティスト検定、各種クラウドサービスの認定資格など、DX関連の資格取得を奨励し、受験費用や学習費用を会社が支援する制度です。従業員の自律的な学習を促す効果が期待できます。
DX人材育成の成功事例
ここまで、DX人材育成の進め方や手法について解説しましたが、理論だけでは自社での具体的なイメージが湧きにくいかもしれません。国内の先進企業は、すでに独自の工夫を凝らした育成プログラムを実践し、大きな成果を上げています。
ここでは、特に参考となる企業の成功事例を取り上げ、その具体的な取り組みから成功のヒントを探ります。
センコーグループホールディングス:実践的DX研修で、現場の自動化を達成
センコーグループホールディングスは、『センコーユニバーシティ』の一環として実践重視のDX人材育成ワークショップを実施し、顕著な成果を上げています。このプログラムでは座学ではなく、「学びを現場に還元する」ことを重視した設計を採用しました。参加者である九州センコーロジ株式会社の石井綾子様は、ワークショップで学んだ知識を活用して現場での自動化導入による改善を実現。その結果、作業効率の向上だけでなく、受講内容をスピーカーで共有する取り組みによって組織全体に「学びの連鎖」が生まれ、従業員の自発的な改善意識が高まるという成果につながっています。
関連記事

─センコーユニバーシティの実践型DXワークショップ センコーグループホールディングス様に、「センコーユニバーシティ」の一環として、DXワークショップを実施された背景についてお話を伺いました。
LIFULL:全社横断AI活用プロジェクト
LIFULLは「全従業員が生成AIを使って業務効率化を自らできること」をビジョンに掲げ、組織横断型のプロジェクトチームを結成しました。社内用生成AIツール「keelai」の開発・導入を軸に、利用状況のトラッキングやChrome拡張機能との連携により、日常業務への統合を実現しています。その結果、2024年10月から2025年3月の半年間で従業員の90.9%が生成AIを活用し、合計31,596時間の業務効率化を達成。エンジニア・デザイナー職ではほぼ100%の活用率を記録し、目標達成に繋がるコア業務の比率も2年間で7%向上するなど、全社的な生産性向上を実現しています。
- 株式会社LIFULL(ライフル) ─ LIFULL、生成AIの社内活用を推進し、過去最高ペースとなる半年間で約31,600時間の業務時間を創出
まとめ:DX人材育成は企業の未来への投資
DX人材の育成は、一朝一夕に成し遂げられるものではなく、時間もコストもかかる息の長い取り組みです。しかし、これは単なる研修ではなく、変化の激しい時代を生き抜くための、企業の未来そのものへの投資と言えます。
DX人材育成の重要性は理解しているものの、自社に最適な育成計画の策定や、効果的な研修プログラムの設計にお悩みではありませんか。成功の鍵は、体系的なノウハウと、他社の成功事例から学ぶことにあります。
ディジタルグロースアカデミアでは、DX人材育成を成功に導くための具体的な進め方や研修事例をまとめた資料を、無料でご提供しております。下記リンクよりダウンロードいただき、貴社の人材育成計画の策定にお役立てください。

DX推進でお悩みの方へ