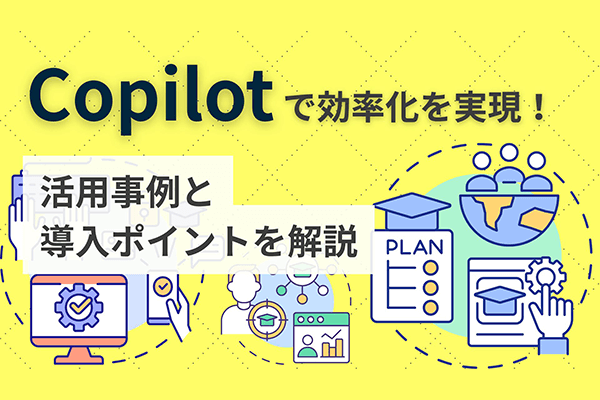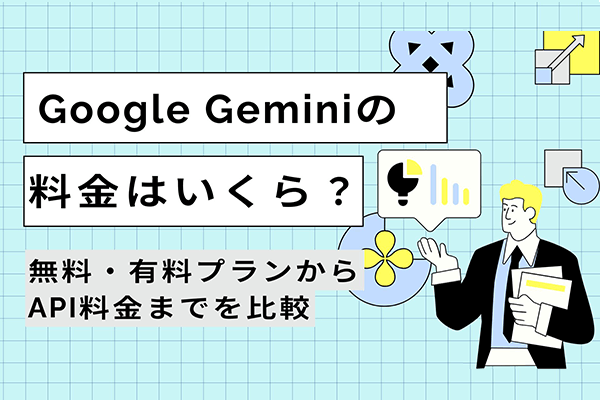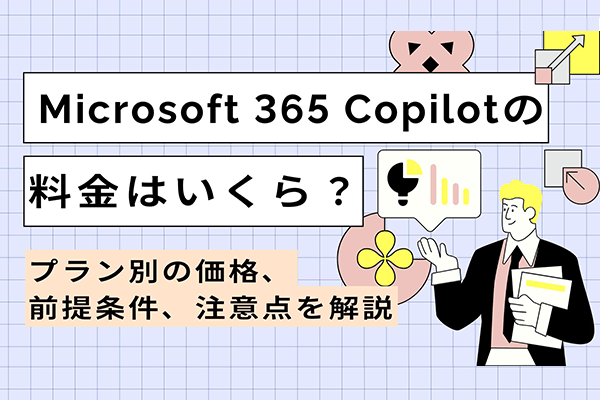自治体DXとは?現状や課題、事例などをわかりやすく紹介
- 公開日:2022年10月05日

「自治体DXって一体何?」「どうして自治体DXが重要なの?」と疑問をお持ちの方もいるのではないでしょうか?
近年は企業の間でデジタル化の取り組みが行われていますが、自治体においてもデジタル化の動きが加速しています。
しかし、何から始めべきかわからないという自治体も少なくありません。そこで今回の記事では、自治体DXの基礎知識や自治体DXが求められる理由、自治体DXの現状と事例、自治体DXの課題などを解説します。
おすすめのサービスやサイトも紹介するので、ぜひ参考にしてください。
目次
自治体DXとは

近年は企業の間で「DX」が叫ばれていますが、自治体の間でもDXへの注目度が高まっています。
自治体DXとは、都道府県や市区町村などの自治体が最新のデジタルテクノロジーやツールを利用して、既存システムや業務フローの効率化を目指す取り組みです。
一般企業の場合はデジタル技術を駆使することで、古いビジネスモデルの刷新や、新しいビジネス機会を創出するといった意味合いでも使われる言葉ですが、自治体の場合は業務フローの改善、効率化といった文脈で使用されることが多いでしょう。
例えば、行政手続きをオンラインで行えるようになれば住民にとって便利なサービスを目指すことができます。
自治体にとっても業務が効率化されるので、双方にとってメリットのある取り組みなのです。
なぜ自治体DXが必要なのか
それでは、なぜ自治体DXが必要とされるのでしょうか?
新型コロナウイルスによる影響
新型コロナウイルスの流行によって、DXの必要性が叫ばれるようになりました。
感染リスクを抑えるためにステイホームが推奨されていましたが、そのような状況の中でも、住民は行政手続きをするために区役所等に出向かなくてはいけなかったのです。
あらゆる行政手続きがオンライン上で完結すれば、感染の心配をせずに手続きを完了させることができます。
このような事態に対応するためにも、自治体におけるDX推進が求められています。
少子高齢化の影響
少子高齢化もDXの必要性を浮き彫りにした要因のひとつです。
現在は、少子高齢化が加速するにつれて労働に従事できる人口が減少しています。自治体においても人材を確保するのが難しくなっており、人材不足が懸念されているのです。
しかし、デジタルツール等を活用し業務フローを簡潔にすれば、限られた人数でも業務をこなすことができます。
DXレポートの影響
自治体DXのニーズが高まったのは、経済産業省が公開した「DXレポート」も関係しているでしょう。
DXレポートでは、既存システムがアナログだったり、システムが複雑化・ブラックボックス化したりしている状態だと、2025年には年間で最大12兆円の経済損失があると報告しています。
このような事態を踏まえて、DXを促進する企業は急増しました。自治体もその影響を受けており、業務効率化を目指すために取り組みが強化されているのです。
自治体DXの現状と事例

具体的に自治体はどのような取り組みを実施しているのでしょうか?
AIチャットボット
AIチャットボットとは、文字情報や音声によってユーザーとコミュニケーションを取るシステムのことです。ホームページや、受付などに設置されることが多いです。
AIチャットボットは質問者の行動や言葉、会話の内容に基づいて疑問の解消を目指します。
住民、子育て、引越し・住所変更など、行政関係のあらゆるデータに対応しており、問い合わせの件数を減らすことが可能です。
結果的に問合せ対応のリソース負荷を軽減することができるので、他業務にリソースを配分したり、少ない人材でも効率的な業務処理を実現します。
電子申請
電子申請とは、これまで郵便や直接提出していた書類をオンラインで提出できるようになるシステムです。
パソコンやスマートフォン、タブレットなどの電子機器があれば、インターネット上で提出できるので住民にとって便利なシステムといえます。
新型コロナウイルスが流行している状況でも活用できますし、住民は営業時間等を気にせずに好きなタイミングで手続きできるようになります。
地域通貨
地域通貨(コミュニティ・マネー)とは、特定のエリアのみで使用できる通貨のことです。地域の経済を活性化させようと、さまざまな地方公共団体が導入しています。
この地域通貨においてもデジタル化が促進されており、アプリやQRコードなどで決済できるようになっています。
決済手段を増やすことができますし、ユーザーにとっても便利なシステムを目指せるのです。
RPA
RPA(Robotic Process Automation)とは、ロボットを導入して業務を自動化することです。
従来は人間が行っていた業務をロボットが代行することで、人材不足をカバーできますし、人為的なミスを防止することができます。
業務の効率化を実現できていない自治体では、職員が1人で多くの業務を抱えることになり、残業なども発生しやすくなります。
防災ダッシュボード
防災ダッシュボードとは、災害リスクを予測、可視化するオンラインサービスです。
リアルタイムで状況を確認できるので安全性を確認できますし、避難指示などの判断をすることができます。
他にも、過去に起きた災害を振り返ったり、水害リスクを予測したりすることが可能です。
データをスピーディーかつ効率的に収集できる仕組みを構築することで、住民の安全を守ることができます。
オンライン市民サービス
オンライン市民サービスとは、市民がインターネットを通じて行政サービスを受けられる仕組みです。例えば、住民票の取得や税金の納付、各種証明書の発行などがオンラインで可能になります。
オンライン化によって、市民は窓口に出向く必要がなくなり、時間や交通費の節約が可能です。また、行政側も窓口業務の負担が軽減され、効率化やコスト削減にもつながります。
スマートシティの推進
スマートシティとは、ICT(情報通信技術)を活用して、都市のさまざまな課題を解決し、持続可能な発展を目指す取り組みです。
| 分野の例 | 具体例 |
|---|---|
| 環境・エネルギー | スマートメーターや太陽光発電 |
| 観光・地域活性化 | ビッグデータやAIを用いた動向分析や魅力的なコンテンツ提供 |
| 健康・医療 | ウェアラブルデバイスやテレヘルスを活用した健康管理や診療支援 |
もっと身近な例を挙げると、IoTやAIなどを用いて、交通渋滞や駐車場の空き状況、災害情報や観光情報などをリアルタイムに提供するなどです。
スマートシティは、快適で便利な暮らしを実現できるとともに、環境や経済の持続可能性も向上する自治体の取り組みと言えます。
サイバーセキュリティとプライバシー
自治体DXでは、ICTを活用して多くのデータを収集・分析・活用しますが、その際にはデータの漏洩や改ざんなどのサイバー攻撃に対する防御や対策が必要です。
また、多くのステークホルダー(行政、民間企業、研究機関、市民等)によって共有・連携されることが想定され、データの管理・運用に関するルールや規格を明確にする必要があります。
そのため、市民の個人情報やプライバシーを保護するためには、データの利用目的や範囲を明確にし、市民の同意や理解を得ることが求められます。
例えば、パスワードや暗号化などを用いて、市民の個人情報や行政機関の重要情報を保護したり、ウイルス対策やファイアウォールなどを用いて、不正アクセスや改ざんなどを防止したりするなどです。
このように、自治体DXでは、安心してオンラインサービスを利用できるとともに、行政機関も信頼性や信用性を高める取り組みが続けられています。
自治体DXの課題
では、自治体DXを促進する上での課題はどのようなものなのでしょうか。
人材不足
現在は、自治体DXの取り組みを実行するデジタル人材が不足しています。
DXのプロジェクトを進めるためには、デジタルに関する専門的な知識をが必要ですし、プロジェクトをリードしていくスキルが求められます。
このような人材を採用するのは難しく、人材育成をするにしても教育のための環境が整っていないのです。
どのようにデジタル人材を育成していくのかが全国レベルでの課題となっています。
既存業務の業務負荷
既存業務の業務負荷により、DXの取り組みを行う時間が確保できていない自治体も少なくありません。
DXを進めるには、通常の業務と並行して新たな業務フローの考案やデジタルツールの選定などを行う必要があります。
自治体の対応業務が遅延してしまうと、住民は不満を抱きやすくなり、人口不足が加速してしまいます。従って、既存業務の対応が優先である以上、自治体としてチームを組むなど、リソースを確保したうえで取り組む必要があります。
住民への周知、ITリテラシーの不足
行政と住民が上手く連携できていないことも課題に挙げられます。
自治体が積極的にDXを進めても住民や国民が対応できないと、DXの意味が薄れてしまうのです。
DXを推進するためには、住民や国民に情報を提供し、理解促進をサポートする必要があります。特にデジタルツールなどに慣れていない高齢の方への対応をどうするかについても、課題として捉えられています。
自治体がDX推進で成功するためのポイント

自治体DXを成功させるためには、以下の5つのポイントが重要です。
- DXに関する理解を深める
- DXに関する専門知識・スキルを持つ人材を獲得する
- DX推進する目標・全体方針を定める
- DX推進するための組織体制を作る
- データの整理・管理をしっかりと行う
それぞれのポイントは、前述した自治体DXの課題とも関連しています。
DXに関する理解を深める
まずは、自治体の幹部や職員がDXに関する理解を深めることが必要です。
- DXとは何か
- なぜ必要なのか
- どのようなメリットやデメリットがあるのか
などを明確に把握することで、DXに対するモチベーションや意識を高めることができます。また、住民や国民にもDXの目的や内容をわかりやすく伝えることで、協力や支持を得ることもできます。
例えば、自治体のホームページやSNSなどでDXに関する情報を発信したり、住民向けの説明会やワークショップなどを開催したりすることが有効です。
DXに関する専門知識・スキルを持つ人材を獲得する
次に、DXに関する専門知識・スキルを持つ人材を獲得することも大切です。DXのプロジェクトを進めるためには、デジタル技術やデータ分析などの専門的な知識やスキルが求められます。
しかし、現在はDX人材が不足している状況です。そこで自治体は、外部から専門家やコンサルタントなどを招いたり、内部からデジタル人材を育成したりするなどし、人材不足の解消へ動き出す必要があります。
そのため、自治体の職員に対してデジタル教育や研修などを実施したり、デジタル人材の採用や異動などを促進したりすることを検討しましょう。
DX推進する目標・全体方針を定める
さらに、DX推進する目標・全体方針を定めることも必要です。DXは目的ではなく手段であり、何を達成したいのかを明確にすることが重要だからです。
また、全体方針を定めることで、各部署やプロジェクトの役割分担や連携方法などを決めることもできます。自治体のビジョンやミッションに基づいてDXの目標やKPIなどを設定し、組織全体で共有しましょう。
DX推進するための組織体制を作る
また、DX推進するための組織体制を作る意識で進めることも大切です。DXは組織全体で取り組むべき課題であり、そのためには組織の変革や改革が求められます。
特に、DXのリーダーシップを発揮する人材や組織は不可欠です。そのため、自治体のトップや幹部がDXの推進者となって牽引することや、DXに関する専門部署やプロジェクトチームなどを設置することが有効でしょう。
データの整理・管理をしっかりと行う
最後に、データの整理・管理をしっかりと行うことも忘れてはなりません。DXはデータに基づいて行政サービスの改善や最適化を行うことであり、そのためにはデータの品質や活用が重要です。
しかし、データが散在していたり、形式が統一されていなかったり、セキュリティが不十分だったりすることは意外にも多い問題です。
そこで、自治体はサイバーセキュリティとプライバシーに注目し、データの収集、整理、分析、共有、活用などを効率的かつ安全に行う方法を策定する必要があるでしょう。
総務省の自治体DX推進計画

総務省は自治体DXの推進に関して、以下の項目を重点取組事項に挙げられています。
- 自治体の情報システムの標準化、共通化
- マイナンバーカードの普及促進
- 行政手続のオンライン化
- AI・RPAの利用推進
- テレワークの推進
- セキュリティ対策の徹底
自治体の情報システムを統一する、テレワークを推進するなど、推進すべき取り組みはさまざまです。
自治体DXについて理解を深めたい場合は
①ネットで情報収集を行う
自治体DXについて理解を深めたい人は、たとえば、「自治体DX白書」などのサイトも参考にするとよいでしょう。
自治体DX白書とは、自治体のデジタル化を推進するために情報を発信しているサイトです。DXの基本や推進ノウハウ、事例・コラム、都道府県別レーダーチャートなど、さまざまな情報を収集することができます。
現在の状況を明らかにするために、自治体DX診断を利用することも可能です。
参考:自治体DX白書
②DX推進企業に相談する
DXの取り組みには様々なアプローチ方法があります。コンサル・実行支援を行う企業に全業務を依頼してしまう場合、DX人材を派遣する会社に依頼しその人材に業務を依頼する場合、既存のスタッフを育成し、DXを推進する場合など様々です。
多くの企業が無料でヒアリングを行うことも多く、課題の洗い出しや、金額感、期間といった情報を知ることができるでしょう。
当サイトを運営するディジタルグロースアカデミアも研修プログラムを提供しており、自治体DXのサポートも行っています。無料で提示できる項目や、DXの進め方など、情報収集の一環で問題ありませんので、興味がある方はぜひお問い合わせください。
自治体DXの将来性

自治体DXの将来性は、非常に高いと言えます。なぜなら、持続可能な未来を築くために不可欠な要素だからです。例えば、デジタル技術を活用することで、以下のメリットが得られます。
- 市民の生活の質を向上させる
- 地域の課題を解決する
- 財政の効率化と透明化を図る
そして、デジタル技術やデータは、交通・モビリティ、防災、行政、観光・地域活性化、健康・医療、農林水産業、環境・エネルギー、セキュリティ・見守り、都市計画、物流、教育・文化など、さまざまな分野でイノベーションを起こす可能性を秘めています。
このように、自治体DXは、地域のニーズに応じて柔軟に対応し、最適なソリューションを提供することで、市民や地域にとって多くの恩恵をもたらします。また、国や企業とも連携し、地方から日本全体を変えることも視野に入れられるでしょう。
まとめ

今回の記事では、自治体DXに興味がある方に向けて、基本的な知識や自治体DXが求められる理由、自治体DXの現状と事例、自治体DXの課題などを説明しました。
都道府県や市町村は自治体DXを取り入れることで、業務を効率化できますし、住民に対してスピーディーに対応することができます。
しかし、デジタル人材を育成する環境が整備されておらず、何から始めるべきかわからないという自治体も少なくありません。
まずは様々な手法を比較検討するために、情報収集と、企業やサービスへの問い合わせを積極的に行うことがおすすめです。
【監修】
日下 規男
ディジタルグロースアカデミア マーケティング担当 マネージャ
2011年よりKDDIにてIoTサービスを担当。2018年IoTごみ箱の実証実験でMCPCアワードを受賞。
2019年MCPC IoT委員会にて副委員長を拝命したのち、2021年4月ディジタルグロースアカデミア設立とともに出向。
資料・研修動画ダウンロード申し込みページ
DXに関する様々な資料や動画がダウンロード可能です。