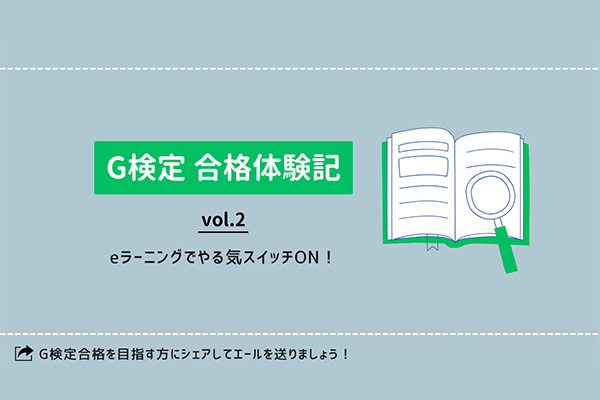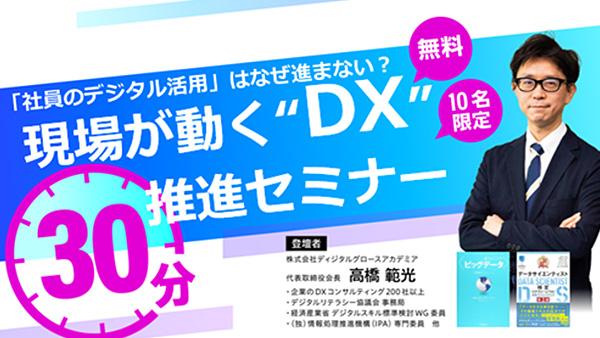社内DXの進め方は?おすすめのツールや浸透させるためのポイント
- 公開日:2022年12月7日

新型コロナウイルスの流行によりDX推進が急速に進んでいます。
DXを実現するためには、まず企業のなかでも部門ごとに、または一部の業務プロセスの改善から進めていくことが求められています。
社内でDXの取り組みを実行し、部門ごとの変革を重ねることで、会社全体の組織やビジネスモデルの変革にもつながるでしょう。
本記事で社内DXの概要や必要性、社内DXを進めるポイントなどについてチェックし、小さなところからでもDX推進の取り組みを始めていきましょう。
目次
社内DXとは

DXとは、デジタル技術を活用し業務プロセスやビジネスのモデルの変革を行うことです。
そのために、まずは企業単位ではなく、部門単位で行える変革を検討し実現することが優先事項となります。部門のなかでもさらに一部の業務プロセスの見直しやデジタル化を進めることで、業務スピードの改善や生産性向上が見込めるでしょう。
こうした小さなところから変革を進めることを、社内DXといいます。
企業単位での新たな価値創出には長期的な視点が必要ですが、社内DXなら短期的にプロジェクトを進められるため、取り組むハードルも下がります。
社内DXの目的

社内DXが必要とされている背景には、以下の理由が挙げられます。
- 業務の効率化・生産性の向上
- BCP(事業継続計画)対策
社内のみで行われる小さな取り組みが、大幅な業務効率の向上や大きな価値創出に直結することはありません。しかし、部門単位の業務効率化や顧客に対して一部のサービスをシステム化するだけでも、ささやかな利便性向上によって満足度が高まることもあるでしょう。
こうした取り組みを1つ1つ行うことで、全社的なDXにつながる見込みです。
業務の効率化・生産性の向上
社内DXに取り組むのは、業務の効率化や生産性の向上のためにも必要です。
業務のデジタル化・システム化を進めることで、多くの企業が悩まされている人材不足の課題を解決しやすくなります。
たとえば、経理課で請求書や発注書などの書類をデジタル化できれば、手書きにかける時間や紙の書類管理の手間を減らせます。
こうした一部の業務プロセスをデジタル化するだけで、一人一人の負担を削減でき、部門全体の生産性向上にもつながるでしょう。
BCP(事業継続計画)対策
社内DXを進めることは、BCP対策にも有効です。
災害が起きて業務が停滞することになれば、会社の事業自体がストップします。
そうなると、商品やサービスを必要とする顧客ニーズに答えられなかったり、経営状況が悪化したりするなど多くのリスクを抱えるため、BCP対策は急務とされています。
非常事態に優先すべき業務をピックアップし、優先度の高い順に対策を行っていくことが大切です。
関連記事

社内DXの進め方!ポイント

本章では、社内DXを進めるためのポイントを確認しましょう。
- 企業の改善点を把握し、目的を明確にする
- DX推進が可能な社内環境を作る
- デジタル人材を育成する
- システムを導入し、業務の効率化を図る
- 新しいビジネスモデルの構築を行う
- 文化の変革と持続的な改善
企業の改善点を把握し、目的を明確にする
社内DXを進めるときのポイントの1つは、企業の改善点を把握しDXの目的を明確にすることです。
DXによってどのようなビジネスモデルを創出したいのか、市場にどのような価値提供をするのか、を明確にできれば、社内のどの部分からDXを進めていけば良いのかが見えてきます。
全社的なDXの目的や戦略が見えないままデジタル化を進めるだけでは、変革を目指すのは困難です。
ただし、これまで慣れ親しんだ業務を新しいシステムに変革させようとする場合、反対意見が出てくることもあるでしょう。
変化に対する恐れや、自分の仕事がなくなるのではという不安から生まれる意見でもあるため、こうした不安を払拭した上で、経営層や社員全体で、目指すビジョンを具体的・明確にすることからはじめます。
DX推進が可能な社内環境を作る
社内DXを進めるためには、DX推進が可能な社内環境を作ることが大切です。
経営層が社内DXに関する発信や研修を行うことで、社内全体でDXを進めるための意識が高まったり、必要な人材確保が進んだりすることが考えられます。
自社でDXを進める理由について社員の理解が深まるほど、よりDXに取り組みやすい環境を整えやすくなるためです。
デジタルデータやIT技術を導入し、こうした技術の活用をサポートする部門の設置からはじまり、IT人材の確保と育成を行う過程で、トラブルが発生することもあるでしょう。
プロセスを進めたりトラブルをできるだけ防いだりするためにも、経営層や社員全体で社内DXに関する知識やスキルをつけておく必要があります。
デジタル人材を育成する
デジタル化が進む現代において、社内DXを推進する上ではデジタル人材の育成が必要です。
2030年には最大で79万人のDX人材が不足すると言われていることから、採用に加えて社内での人材育成まで求められているためです。
したがって、企業は組織内でデジタル人材を育成するための戦略立案と投資を行う必要があります。
このように、長期的なビジョンの実現に向けてデジタル人材の確保とスキルの向上を図っていくことが求められるでしょう。
システムを導入し、業務の効率化を図る
社内DXでは、まずシステムを導入して業務の効率化を図ることが大切です。
例えば、人の手で行われている定性的な業務がある場合、自動化できるものはシステムに行わせてヒューマンエラーを減らし、社員のリソースを本来注力すべき事柄へ向けます。
具体的には、マーケティングにはCRMやSGAといったツールを導入したり、他部門と連携できるようなツールを利用し業務の効率化を図ったりするなどです。
このように業務を効率化し、社員のリソースを確保するためにも、現在の業務を洗い出して導入すべきシステムの検討を進めてみてください。
新しいビジネスモデルの構築を行う
業務の効率化を行った後は、新しいビジネスモデルの構築を進めましょう。
一部門や部分的な業務効率化だけではなく、年単位で社内全体に広く浸透させて、その先を見据えた動きがデジタル化する社会を生き抜く競争力を得るために必要だからです。
将来を見据えて動き出す場合、社外へシステムを外注するだけに限らず、IT人材の育成や教育を充実させることも必要です。
社内DXを進めていくためには、既存の業務効率を見直し、新しいビジネスモデルの構築を目指していきましょう。
文化の変革と持続的な改善
最後に、文化の変革と持続的な改善も社内DXに必要です。
社内DXを成功させるには企業の文化を変革し、デジタル化を自然な流れとして組織内に浸透させることが不可欠です。
また、企業文化の変革には、経営層から現場の従業員までが一丸となって取り組む姿勢も求められます。
そのため、経営層はデジタル変革の重要性を理解し、全社的なビジョンの共有と、その実現に向けた強いリーダーシップを発揮する必要があるでしょう。
関連記事

社内DXによく活用されるツール

社内DXによく活用されるツールには、以下が挙げられます。
- オンライン会議システム
- ビジネスチャットツール
- クラウドストレージサービス
- プロジェクト管理ツール
- データ分析ツール
- RPAツール
- 会計ソフト
- BIツール
- 人事管理システム
オンライン会議システム
まず、社内DXにおいてはオンライン会議システムがよく活用されます。
例えば、従業員がオフィスに集まらずとも会議を行えるため、移動時間やコストを削減できます。
また、テレワークやフレキシブルな働き方をサポートすることで、働き方の多様化に対応し、従業員のワークライフバランスの改善にも寄与するでしょう。
このように、在宅勤務やリモートワークが一般化する中で、企業の業務改善や生産性の向上に資する重要なツールです。
ビジネスチャットツール
ビジネスチャットツールも、社内DXにおいて社員間のコミュニケーションを活性化させ、より効率的かつ迅速な情報共有を可能にすることから活用されています。
メッセージの即時送受信、チーム内でのアイデア共有、業務知識の呼びかけなど、多様な機能を有しています。
さらに、多様なデバイスに対応しており、場所を問わず効果的にコミュニケーションを図ることも可能です。
そのため、「報告・連絡・相談(報連相)」のプロセスを強化し、一体感の向上やビジネス活性化にも大きく貢献するでしょう。
クラウドストレージサービス
クラウドストレージサービスは、社内のどの場所にいても、様々なデバイスからアクセスが可能であり、DXに大きく貢献するツールです。
文書やプレゼンテーション資料、プロジェクトファイルなど、多様なデータを一か所で一元管理できるため、社内での情報共有や協働作業をスムーズに行うことができます。
また、リモートワークやフレキシブルな労働スタイルをサポートする上でも非常に有効であり、DXを通じた柔軟な働き方の普及にも寄与するでしょう。
プロジェクト管理ツール
ほかにも、社内DXではプロジェクト管理ツールもよく活用されます。
- タスクの割り当て
- 期限の設定
- 進捗状況の追跡
- 各種リソースの管理
- チームメンバー間のコミュニケーション
など、多岐にわたる管理を可能にし、社内のDXにおける業務効率化に役立ちます。
例えば、必要なときに迅速にアクションを起こしたり、関係者間のコミュニケーションを円滑にしたりするなどが可能です。
データ分析ツール
社内DXにおいて、データ分析ツールは業務の質を向上させ、意思決定を円滑にするために用いられます。
データ分析ツールは、膨大なデータを集め、整理し、解析して、有益な情報に変換する役割を担っています。
そのため、企業内の異なるデータソースから集められた情報を統合し、パターンやトレンドを見つけ出すために活用できるでしょう。
また、データを基にした戦略立案や判断が可能となり、最終的に競争力のあるビジネスへの転換にも繋がります。
RPAツール
社内DXでRPAは多くのルーティン業務を自動化し、従業員がより創造的で価値の高い作業に集中できる環境構築に活用されます。
具体的には、RPAツールはデータ入力、フォームの記入、ファイルの移動、簡単な分析等を効率化できるでしょう。
結果、労働時間を大幅に削減したり、人的ミスのリスクも抑えたりできます。
会計ソフト
社内DXにおいて、会計ソフトは日々の取引の記録、経費の追跡、請求書の作成、財務報告書の生成などの経理をデジタル化する際に活用されます。
また、税務申告に必要な帳簿やスケジュール、財務状況のリアルタイムモニタリングなどに対応したツールもあるでしょう。
選ぶ際には、改正電子帳簿保存法やインボイス制度への対応を念頭においた機能が搭載されているかを見ておくと安心です。
BIツール
BIツールも、社内DXで企業や組織が持つ大量かつ多様なデータを統合し、分析・解析を行い、業務の効率化や意思決定を支援するために活用できます。
例えば、定形レポートの自動出力や、ダッシュボード機能のほか、棒グラフ、円グラフ、レーダーチャートなどを用いてデータも可視化できます。
BIツールは膨大なデータから有益な情報を見つけ出し、素早い意思決定や業務改善に役立つでしょう。
ただし、BIツールは安価なものではなく、導入にはそれなりのコストがかかることから、企業の規模や要件に合ったツール選びが大切です。
人事管理システム
最後に、人事管理システムも社内DXで活用されるツールの1つです。
主に、従業員の基本情報、評価情報、異動情報、教育履歴など、広範なデータを一元的に集約し、「見える化」することで管理・用途を高める役割を果たします。
そのため、曖昧だった従業員情報が明確となり、人事部門だけでなく経営層も含めた迅速な意思決定に役立ちます。
社内DX導入に伴う課題

社内DX導入に伴う課題には、以下が挙げられるでしょう。
- スキルや知識の不足
- DX人材の不足
- 組織文化の変化への抵抗
- 適切なツールの選定
スキルや知識の不足
まず、社内DXの課題として挙げられるのがスキルや知識の不足です。
DXを推進するためには、以下のような複合的なスキルが求められます。
- デジタル技術やデータ活用に関する深い知識
- 事業プロセスをデジタルに適正化できる能力
- UI・UX設計に関する知識
- データサイエンスの知識と、機械学習やビッグデータを活用する能力
- 大規模プロジェクトを統括するプロジェクトマネジメント(PM)能力
そのため、スキルや知識の不足を補う解決方法として、人材の雇用や育成が必要となります。
DX人材の不足
社内DXにおいて、日本では2025年に向かってIT人材の不足が深刻化しており、DX人材の不足も課題として挙げられます。
実際、経済産業省の「DXレポート」で2030年には約45万人に達すると警鐘が鳴らされている状況です。
解決策としては、既存の従業員のデジタルスキル向上への投資、DX人材の育成プログラムの利用、社外からの人材獲得、さらにはAIアプリケーションなどの外部リソースを活用して不足分を補完することが挙げられます。
組織文化の変化への抵抗
さらに、社内DXでは組織文化の変化への抵抗も課題です。
既存の企業文化や業務プロセスに習慣化された従業員が、新しいデジタル技術や変革に抵抗感を示すためです。
社内DXに関する抵抗を軽減する解決策としては、経営者と従業員の対話を促進し、共通のビジョンを構築することが有効です。
また、リスキリングや継続的な教育を通じて、従業員のDX素養を高めることで段階的に進めることもできるでしょう。
適切なツールの選定
最後に、社内DXの実施には、組織に適したデジタルツールの選定も課題として残ります。
RPAやワークフローシステム、CRMやSFAなどツールは多岐にわたります。
そして、課題を解決するためには、目的に応じたツールが必要です。
解決策としては、まず自社のビジネスプロセスを詳細に分析し、どのツールが課題解決に役立つかを特定しましょう。
ツールの機能性やコストだけでなく、操作性や社内システムとの相性、サポート体制などを総合的に比較検討します。
また、従業員からのフィードバックを取り入れ、実際のユーザーが直面する問題や改善点を明らかにすることも大切です。
社内でDXを浸透させるためには?

社内でDXを浸透させるためにできる取り組みは、まずDX研修を行うことです。
社員全員の理解を得るためには、経営トップがDXを知る必要があります。
経営層向けのセミナーに参加して、最新のデジタル技術やDX成功事例について学べると、社内での取り組みに活かせるでしょう。
社内全体で従来のやり方が変わっていくことを受け止めたり、社員の自立性・自発性を育てるために権限を渡したりする決断力も大切です。
経営層から現場の社員が目線を揃えてDXを進めるために、社員一人ひとりに経営層と同じように顧客、市場、競合などの動向や自社の置かれる状況を把握してもらうことで、自分ごととして捉えて変革に向かうことができます。
部門を飛び越えた連携を行うことにより、全社的にDX推進の取り組みが浸透するでしょう。
社内DXを推進している企業はどれくらいある?

社内DXは、アメリカを始めとした先進国では積極的に進められていますが、日本ではまだ取り組み始められていない企業が多いのが現状です。
全社的に、または部署ごとにDXを進めている企業の割合は、日本では5〜6割に対し、アメリカでは8割にものぼります。
なお、DXへの取り組みすら始めていない、という企業は、日本企業が3割強に対し、アメリカは1割強です。
日本においては、DX推進を担う人材の人数と質の不足が課題としてあげられています。
また、情報が少ないために取り組み方がわからず進められていない企業があるのも実情です。
ただし、アメリカに後れをとっているとはいっても、半数以上の国内企業がDXを進めている事実はあります。
早めに取り組み始めることで、国内で優位性を強化することができるでしょう。
社内DXの成功事例

社内DXの成功事例を、以下に分けて紹介します。
- デジタルワークフローの導入
- オンライントレーニングの提供
- リモートワークの促進
- データ分析とデータドリブンな意思決定の推進
デジタルワークフローの導入
社内DXにおけるデジタルワークフローの導入は、業務の自動化や電子署名の導入などによって、スピードアップやコスト削減を狙うものです。
主に、紙ベースの文書を電子化し、プロセスを自動化することで、オペレーションの迅速化やエラーの減少を図る取り組みが該当します。
例えば、株式会社エイトレッドが提供する「X-point Cloud」や「AgileWorks」のシステムの導入によって、社内の文書申請プロセスが簡素化するなどが挙げられるでしょう。
他にも、一般社団法人KEC関西電子工業振興センターは約40%の申請書処理業務削減を実現しています。
オンライントレーニングの提供
社内DXにおけるオンライントレーニングの提供も、DX事例の1つです。
主に、DXに必要なスキルやリテラシーを身につけるための研修プログラムをオンライン形式で提供する方法が一般的です。
例えば、富士通ラーニングメディアやSIGNATE Cloudの研修サービスを用いることで、社員は最新のDX関連スキルを効率良く習得でき、社内のDX推進に対する理解と意識を高めることができます。
受講方法も多岐にわたり、マンガ動画やチャット形式のレッスン、直接対面型研修など、学習スタイルに合わせた教材を選択できます。
リモートワークの促進
リモートワークの促進とは、社内での労働形態をデジタルテクノロジーの力を借りて、物理的なオフィスに依存しないワークスタイルへと変革する取り組みを指します。
社内のDXを推進する上で、リモートワークの促進も成功事例の1つです。
従業員が自宅やカフェなど、オフィス以外の場所で働ける環境を整えることを目的としています。
具体的には、クラウドツール(例:Microsoft TeamsやSlack)、VPN(仮想プライベートネットワーク)を活用した安全なアクセス、そして、オンラインでのプロジェクトマネジメントツール(例:TrelloやAsana)の導入などです。
データ分析とデータドリブンな意思決定の推進
最後に、データ分析とデータドリブンな意思決定の推進も社内DXの成功事例です。
例えば、データドリブン経営を実施している企業では、目的設定から始まり、必要なデータの収集、データの可視化、分析を行い、その結果を基に施策立案と実行を繰り返すPDCAサイクルを実行しています。
さらに、データドリブンマーケティングでは、マーケティング施策の展開に際してデータを活用し、より精度の高いターゲティングや施策の効果検証を効率良く行います。
このように、収集したビッグデータを分析し、企画立案や未来予測を行って意思決定する、というプロセスを通じて社内のDXを成功に導くものです。
補助金を利用してDX推進を行う

DX推進にコストがかかるために取り組みを始められない場合であれば、補助金の利用を検討しましょう。
DXに役立つ補助金には以下のようなものがあり、いずれも国や自治体から出されます。
- IT導入補助金2022(経済産業省・中小企業基盤整備機構)※2022年現在(2023年以降の最新情報はチェック!)
- ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(中小企業庁・中小企業基盤整備機構)
- 中小企業デジタル化応援隊事業(中小企業庁・中小機構)
- 戦略的基盤技術高度化支援事業
このような補助金制度によって、国をあげてDXを推し進めていることがわかります。
銀行の融資とは異なり、補助金は返済する必要がありません。そのため、システム導入のコストをできる限り抑えることが可能です。
自社のニーズや事業形態に合った補助金を選び、DX推進の取り組みを進めていきましょう。
まとめ

社内DXを進めることで、大きなビジネス変革を生み出せる可能性があります。
まずは、DX推進に必要な人材の確保や育成が大きな課題といえるでしょう。
DX人材育成会社のデジタルグロースアカデミアでは、DXに関する研修や、いつ・どこにいても受講できるe-ラーニングの整備から企業別コンサルティングまで、幅広いサポートを提供しています。
デジタル化やDXによって事業を成功させるための人材育成をご希望であれば、ぜひデジタルグロースアカデミアにご相談ください。
【監修】
日下 規男
ディジタルグロースアカデミア マーケティング担当 マネージャ
2011年よりKDDIにてIoTサービスを担当。2018年IoTごみ箱の実証実験でMCPCアワードを受賞。
2019年MCPC IoT委員会にて副委員長を拝命したのち、2021年4月ディジタルグロースアカデミア設立とともに出向。
資料・研修動画ダウンロード申し込みページ
DXに関する様々な資料や動画がダウンロード可能です。