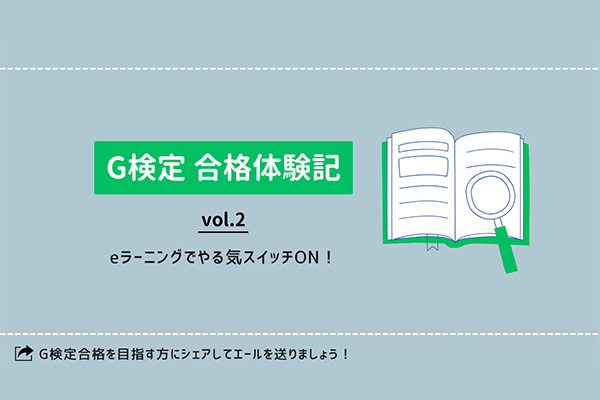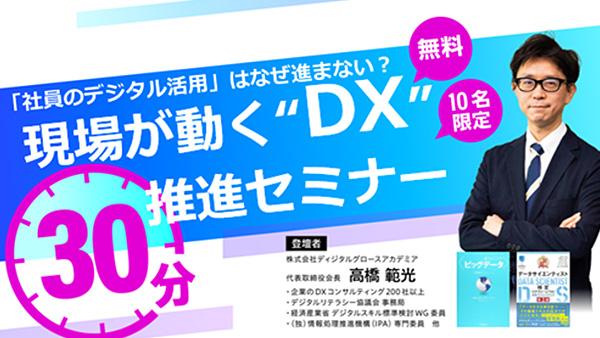DX推進のメリットとは?注目される背景や課題、推進方法を紹介
- 公開日:2022年10月25日

DXとは「デジタルトランスフォーメーション(Digital Transformation)の略で、「デジタル改革」を意味します。本来はビジネス領域に限らず、デジタル技術を社会に浸透させ生活をより良いものに変革することを指し、広義な意味があります。
DXは、2004年にスウェーデンにあるウメオ大学のエリック・ストルターマン教授によりその概念が提唱され、広まりました。DXは単にデジタル技術を取り入れるだけではなく、既存の価値観や枠組みを覆す革新的なイノベーションも含まれます。
ビジネス領域においては、業務フローの改善や新規ビジネスモデルの創出が挙げられます。
また、既存システムからの変化や企業風土の変革まで行う場合もあるでしょう。市場変化の激しい現代において、DXは企業にとって競争優位性を維持するために欠かせない要素となっています。
目次
そもそもDXとは?

DXとは、企業や組織がデジタル技術を活用して、ビジネスプロセスや顧客体験、企業文化を根本的に改革する戦略のことです。
DXは「Digital Transformation」の略で、訳は「デジタル変革・改革」です。
昨今では企業文化や風土の変革を通じて、競争優位性を変えることが求められています。
また、デジタル技術の進化により、企業はグローバル市場において競争力を維持するためにも、DXを推進することが不可欠です。
そのため、DXは企業がこれからの社会で生き残り、持続可能な成長を遂げるために欠かせないものとなりつつあります。
DX(デジタルトランスフォーメーション)推進とはどういう意味?

DX推進とは、企業内でDXを推し進めるという意味です。ビジネス市場におけるDX推進は、業務をデジタル化するだけに留まらず、組織のあり方や枠組みの変革も含まれます。DX推進と似た言葉でよく知られるのが、IT化です。
IT化は、業務の効率化や生産性の向上などを目的にデジタル技術を導入します。一方、DXは業務の改善だけでなく、ビジネスモデルや組織、新事業まで及ぶ変革が目的です。
多くの企業でDX推進が行われているのには、時代的背景も関係しています。その1つは、「2025年の崖」です。「2025年の崖」とは、経済産業省が発表した2018年のDXレポートの中で、日本企業がデジタル化に取り組まなければ多大な経済損失が生じる可能性を提起したものです。
この問題を受け、経済産業省では同年に「DX推進ガイドライン」も公表しています。このような政府の動きもあり、大企業に限らず国内の多くの企業がDX推進に取り組むようになりました。
関連記事
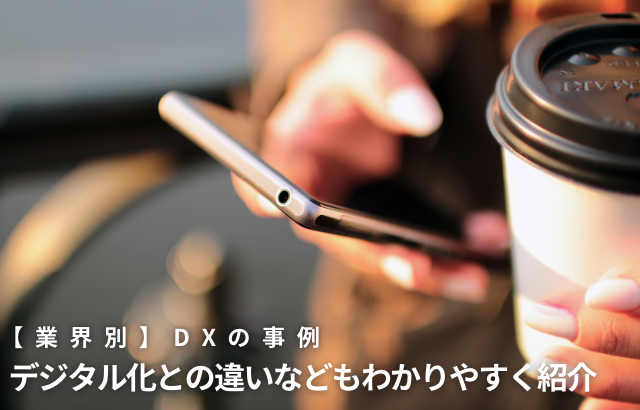
経済産業省のDX推進ガイドラインとは?

経済産業省が策定した「DX推進ガイドライン」とは、DXを企業が効果的に進めるための指針のことです。
現在は「デジタルガバナンス・コード2.0」と呼ばれているものです。
2025年のITシステムの崖の問題をきっかけとし、企業のITシステムの抜本的な刷新およびデジタルを活用した新たなビジネスモデルへの転換が必要であるとされています。
主に、以下の11のチェック項目を提供しており、企業が自身のDX推進の現状を評価し、今後の体制を整備するための基準として機能します。
- 経営層のコミットメント:経営者の強いリーダーシップと明確な意思表示
- ビジョンの策定:長期的な企業のデジタル化に向けたビジョン
- 組織文化の変革:従業員のDXマインドセットの育成と組織文化の変革
- 人材の育成:デジタル人材の内部育成および外部導入
- 技術戦略:長期的に持続可能な技術戦略の策定
- データの利活用:事業価値を生むためのデータの集約と活用
- 顧客体験の強化:デジタル技術を用いた顧客体験の向上
- パートナーシップの構築:他企業との協業による新サービス・ビジネスモデルの創出
- 業務プロセスの改革:ITとデジタル技術を活用した業務プロセスの最適化
- 組織・ガバナンス:DXを推進する組織構造と意思決定プロセス
- セキュリティ:セキュリティリスクへの対応強化と情報セキュリティの確保
ガイドラインを使えば、現状の評価からはじめ、DX推進に向けた体制や戦略を検討して着実に遂行するためのロードマップを立てることができます。
DX推進が推奨されている背景

DX推進が推奨されている背景は、前項ですでに触れたように、新たなビジネスモデルへの転換が求められているためです。
では、なぜここまでDXの推進が重要視されるのかを以下に分けて紹介します。
- 「2025年の崖」問題
- 市場の変化と競争の激化
- 効率化と生産性向上の必要性
「2025年の崖」問題
DX推進が推奨されている背景の1つに「2025年の崖」問題があります。
多くの企業の情報システムが老朽化しており、2025年までに多くのシステムのサポートが終了すると予想されています。
そのため、それまでにシステムの更新や新しいシステムへの移行が求められるでしょう。
この状況でDX推進を行うことで、老朽化したシステムの問題を克服し、効率的な新しいデジタル基盤へと移行可能です。
市場の変化と競争の激化
次に、DX推進が推奨されているのは、市場の変化と競争の激化も関係しています。
昨今では、変動する顧客のニーズや多様化する社会の環境への迅速かつ効率的な対応が求められるものです。
そのため、リアルタイムで変化するデータを活用して意思決定を行い、顧客エクスペリエンスを向上させるなどの施策が求められます。
また、競争力のある新製品やサービスの開発、内部プロセスの効率化、そして新たな収益源の創造といった具体的成果を追求することも、DX推進を通じて実現されると考えられます。
このことから、DX推進は企業が競争力を維持し、地位を確立するために不可欠な戦略的アプローチであると言えるでしょう。
効率化と生産性向上の必要性
最後に、DX推進は効率化と生産性向上の必要性においても重要視されています。
ここでいう効率化とは、企業が従来の業務プロセスを見直し、デジタル技術を駆使して作業の自動化や最適化を図り、不必要な時間やコストを削減することを指します。
また、生産性向上は、より効率的なリソース管理を通じて、1人あたりの出力や企業全体の業績を向上させることを目指します。
それぞれの効果を得ることで競争力を確保したり、新たなビジネスモデルへ転換したりするなどを実現できるでしょう。
企業がDX推進するメリット・デメリット

企業がDX推進する場合、社内の経営方針や業務に影響するいくつかのメリット・デメリットがあり、これらは導入する前に検討しておきたい項目です。
ここではまず、以下の4つのメリットを解説します。
- 業務の生産性向上
- コスト削減
- リスクの回避
- 新規ビジネスの開発
企業がDX推進するメリット
企業がDX推進するメリットについて紹介します。
メリット①:業務の生産性向上
DX推進により社内業務がデジタル化されると、生産性や正確性が向上します。具体的には、業務の最適化により以下の事柄が達成されるでしょう。
- 作業時間の短縮
- 作業人数の縮小
- ヒューマンエラーの減少
- 作業優先度の可視化
人の手で行っていた単純作業や管理業務をデジタル化すると、社員はより重要度の高い業務に集中でき、クオリティの高い仕事ができるようになります。
メリット②:コスト削減
業務の生産性向上はコスト削減にもつながり、単純作業を自動化するなら、人手による作業にかかっていた人件費を削減できます。
また、業務プロセスを可視化・分析し、プロジェクトを全体的な視点で見られるようになります。結果、プロジェクトのフローや経費の見直しにつながり、コスト削減が達成できるでしょう。
メリット③:リスクの回避
DX推進の一環としてBCP(事業継続計画)も実施するなら、リスクの回避につながります。BCPとは、災害やシステム障害などの危機的状況の際に被害を最小限に抑え、業務を持続するための対策のことです。
DX推進により業務が効率化していれば、BCPを最適な形で準備できます。また、他にも多くの日本企業が抱えるリスクとして、レガシーシステムのブラックボックス化があります。
レガシーシステムのブラックボックス化とは、古い社内システムが使いづらくなったまま放置されている状態のことです。レガシーシステムは生産性を低下させ、余分な維持コストも発生させます。
また、運用の引き継ぎが行われておらず、扱える人材が社内にいなくなるという問題もあります。DX推進により、このようなレガシーシステムのブラックボックス化を避けられる点もメリットといえるでしょう。
メリット④:新規ビジネスの開発
DX推進は現状の業務を最適化するだけでなく、新規ビジネスの開発の機会も広げます。最先端のデジタルテクノロジーを駆使し、最新のビジネスモデルを検討できます。
たとえば、日本は消費人口が減少傾向にあり、内需向けのビジネスだけでは伸び悩む企業も少なくありません。デジタルテクノロジーにより、国外の時差や言語の問題をクリアするシステム構築を行えば、世界経済と市場を相手にしたビジネスが可能になります。
DX推進により、急激な社会の変化にも適応できるビジネスモデルを開発できる点は大きなメリットです。
企業がDX推進するデメリット
DX推進には多くのメリットがある一方で、企業の状況によってはデメリットとなる点もあります。ここでは、以下の3つのデメリットを解説します。
- コストがかかる
- 既存システムからの移行に手間がかかる
- すぐには結果が出ない場合もある
デメリット①:コストがかかる
DX推進のデメリットの1つは、初期費用やランニングコストがかかる点です。新たにシステムを構築したり、既存システムの再構築をしたりする場合、エンジニアに対する人件費が必要となります。
また、システムを運用するためのランニングコストも必要です。DX推進が利益を生み出すまでには、数年かかるとされています。
一方で、DX推進は長期的に見てコスト削減にもつながります。導入にかかる費用とコスト削減が可能な割合を比較し、自社に最適な形を検討すると良いでしょう。
デメリット②:既存システムからの移行に手間がかかる
DX推進は、場合によっては既存システムを大きく変革することを意味します。そのため、導入に手間がかかる点はデメリットです。
移行作業そのものの手間に加え、社員が慣れるまでの移行期間も想定に入れる必要があります。たとえば、紙の書類や押印を使用するなどアナログ方式な業務方法に慣れている社員が多い場合、業務をデジタル化するのが困難なケースもあります。
移行期間にはある程度のリスクが伴う点を踏まえつつ、「このDX推進がなぜ必要か」を社内全体で共有する必要があるでしょう。
デメリット③:すぐには結果が出ない場合もある
DX推進には異なる手法やツールがあり、自社にとって最適な戦略を選択した時にメリットをもたらします。結果が出るまでには、試行錯誤しなければいけない場合も少なくありません。
すぐに結果が出ないからといって焦ると、社内で混乱や食い違いが生じてしまいます。DX推進を成功させるためには、ある程度の時間とトライアンドエラーのプロセスが必要である点は認識しておくべきでしょう。
経済産業省がDX認定制度を推進する目的

経済産業省では、国内企業のDX認定制度を推進しています。
DX認定制度は、コロナ禍など時代の変化が激しい現代において生き残れる強い企業を作ることを目的としており、企業の経営者であればみな一考に値する制度といえるでしょう。
DX認定制度とは
DX認定制度とは、2020年5月施行の「情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律」に基づく認定制度です。認定企業は「DX認定事業者」として公表され、税の優遇などのメリットも受けられます。認定基準は、「デジタルガバナンス・コードの基本的事項」に対応することです。
「デジタルガバナンス・コード」には、デジタル技術による社会の変革を踏まえた経営ビジョンの策定・公表などの経営者に求められる対応がまとめられています。
DX認定企業に申請する際は、DX推進ポータルにアクセスして必要書類を提出するとWeb申請が可能です。同サイトを運営する情報処理推進機構(IPA)が「DX認定制度事務局」として、各種問合せや認定審査事務などを担当しています。
DX認定事業者になると以下のメリットが得られます。
- 社内のDX推進状況が確認しやすい
- 企業価値やイメージを向上できる
- DX投資促進税制の税額控除が受けられる
- DX銘柄の応募資格が得られる
- IT活用促進資金の特別利率が利用できる
DX認定事業者の認定を受けるための「デジタルガバナンス・コード」に沿って社内変革を行っていくと、DX推進の進捗がわかりやすく、課題がクリアしやすい点はメリットです。
また、認定を取得すると認定事業者一覧への掲載やDX認定ロゴマークの使用が可能になり、企業イメージの向上につながります。そのほか、税額控除や銘柄選定、融資においても有利となるメリットがあります。
関連記事

DX推進における課題

DX推進における課題には、以下が挙げられます。
- 文化の変革
- 適切な人材とスキルの不足
- 適切なテクノロジーの選択と統合
- データの品質とセキュリティ
- レガシーシステムの問題
文化の変革
DX推進には、レガシーシステムの更新にとどまらず、組織全体の企業文化や風土を変える文化の変革が求められます。
具体的には、社内のコミュニケーションスタイル、意思決定プロセス、リスク管理、イノベーションへの姿勢などです。
また、単に技術を導入するだけでなく、従業員のマインドセットを変え、新たなビジネスモデルや顧客に価値を届ける方法を採用する必要もあります。
適切な人材とスキルの不足
DX推進における課題の1つとして、適切な人材とスキルの不足も挙げられます。
DX人材が不足する原因として、日本の少子高齢化による労働人口の減少や、人材育成の遅れが挙げられるでしょう。
結果として、人材の獲得競争が激化しており、適切な人材を確保することが難しくなっています。
適切なテクノロジーの選択と統合
さらに、DX推進では適切なテクノロジーの選択と統合も課題となります。
企業においては、モバイル技術、ソーシャルメディア、クラウドコンピューティング、ビッグデータ分析といった押さえるべきテクノロジーは多岐にわたります。
そして、各テクノロジーを企業の持つビジネスモデルやプロセスにどう統合し、新しい価値を生み出すかを見極めなくてはなりません。
データの品質とセキュリティ
DX推進では、データの品質とセキュリティも課題の1つとして挙げられます。
デジタル化されたビジネス環境においては、データそのものの正確性、信頼性、一貫性がサービスの質に直結します。
また、データを適切に保護し、不正アクセスやデータ漏えいから守ることも必要です。
レガシーシステムの問題
最後に、DXではレガシーシステムの問題もしばしば取り上げられます。
この場合、維持や運用にかけるコストが増大したり、最新のセキュリティ基準を満たしていないことでサイバー攻撃のリスクが高まったりします。
そのため、DXの推進においてはガバナンスの観点から現行システムを評価し、戦略的な刷新を行うことが求められます。
DX推進をしていくためには?

DX推進をしていくために、以下を押さえましょう。
- ビジョンの確立
- 戦略的な計画とロードマップの策定
- データの活用と分析
- 持続的な改善とイテレーション
ビジョンの確立
まず、DX推進において企業が目指すべき最終的な姿やビジョンを確立します。
ビジョンがあることで、目指す方向が明確になり、企画・戦略立案から実行計画、ロードマップ作成まで一貫して推進できます。
また、ビジョンに基づいた組織運営は、変革の動力として機能し、コアコンピタンス(企業の独自の競争力)を基盤にした競争優位の獲得にも繋がるでしょう。
戦略的な計画とロードマップの策定
DXの推進を成功させるためには、綿密な戦略的計画とその実行の道筋を示すロードマップの策定も必要です。
先ほど触れたビジョンの確立を核とし、実現のための具体的なタスク、優先順位、効率的なアプローチをロードマップとして策定します。
戦略的な計画とロードマップの策定においては、デジタル人材を育成し、外部パートナーとのアライアンスを積極的に形成すること、そして可視化されたデジタル投資と採算計画により、投資回収と採算性のバランスを計画的に進めることが求められます。
データの活用と分析
DXを推進するにあたり、データの活用と分析も企業の事業戦略強化、業務の効率化、生産性向上、未来の事業変革などで求められます。
データを通じて客観的な意思決定や競争力の源泉となる洞察の提供が可能となり、品質向上、顧客満足度の向上、売上増加なども期待できます。
また、蓄積したデータは競合する他企業との差別化や、新たなビジネスチャンスの発見に対しても有効な資源となり得ます。
持続的な改善とイテレーション
DX推進では、持続的な改善とイテレーションも大切です。
主に、計画された変革の目標に向かって継続的に見直しや改善を行うことで、企業は変化する市場や顧客の要求に迅速に対応します。
このイテレーションを繰り返すことで、変化に対応し顧客満足度を向上させることができるだけでなく、市場における競合優位性も確保できます。
関連記事

DX推進のためにはDX人材の確保・育成が必要

DX推進において多くの企業が持つ課題の1つが、DX人材の不足です。DXを進めるためには、新システムの導入だけでなく、使用できる人材の確保・育成が欠かせません。
ディジタルグロースアカデミアでは、DX推進に必要な人材の育成体系や研修プログラムをパッケージとして提供しています。当社では、以下の課題解決をサポートします。
- 社員のデジタルリテラシーを上げたい
- 経営者層がデジタル推進するための力を上げたい
- デジタル改革をしてビジネス拡大につなげたい
目的に応じた各種プログラムをご用意しており、貴社の環境に合わせてオンライン開催・リアル開催のどちらも可能です。
デジタル人材育成体系の策定からコンサルティングまで、一貫したサポートを提供し、迅速な効果創出を実現します。社内のDX推進でお困りでしたら、お気軽にお問い合わせください。
【監修】
日下 規男
ディジタルグロースアカデミア マーケティング担当 マネージャ
2011年よりKDDIにてIoTサービスを担当。2018年IoTごみ箱の実証実験でMCPCアワードを受賞。
2019年MCPC IoT委員会にて副委員長を拝命したのち、2021年4月ディジタルグロースアカデミア設立とともに出向。
資料・研修動画ダウンロード申し込みページ
DXに関する様々な資料や動画がダウンロード可能です。