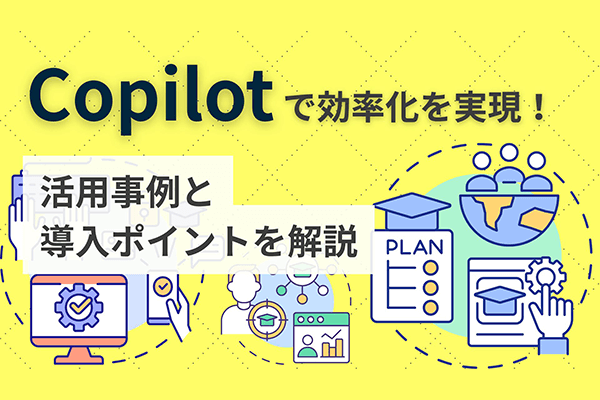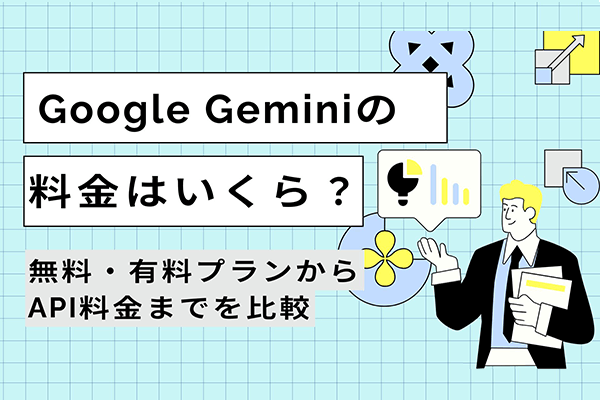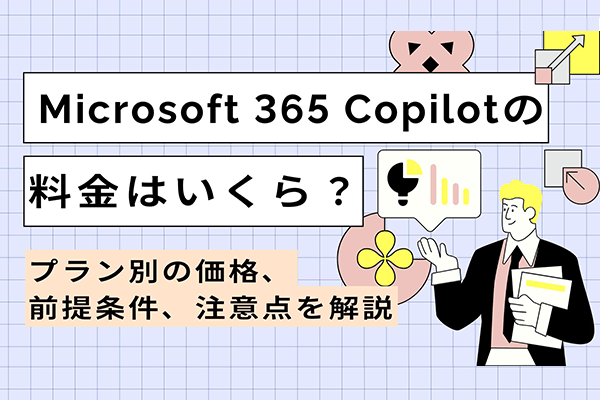経済産業省が定めるデジタル人材とは?スキル標準についても紹介
更新日:2023年6月6日

デジタル技術が急速に発展する中、企業はデジタル人材の確保が急務となっています。しかし、どのような技術が求められ、どういった人材を確保すべきなのかが明確にならなければ、具体的に動き出せません。
そこで本記事では、デジタル人材とは何か、不足がなぜ問題となるのかなどを詳しく解説します。また、デジタル人材の育成・確保のために企業や社会ができることにも触れるため、ぜひ読んでみてください。
目次
デジタル人材について

デジタル人材とはどのような人を指すのか、以下の2つに分けて解説します。
- デジタル人材とは
- IT人材との違いとは
デジタル人材とは
デジタル人材とは、デジタル技術を活用して、企業や社会に新しい価値を創造する人材です。具体的には、AIやビッグデータ、IoTなどのデジタル技術を理解して活用できる人を指します。
デジタル人材には、以下のスキルが求められます。
- デジタル技術に関する知識・スキル
- データ分析・活用能力
- ビジネス理解力
- コミュニケーション能力
- チームワーク能力
DXが推進される昨今において、デジタル人材は企業に必要不可欠な存在となるでしょう。
IT人材との違いとは
デジタル人材とIT人材との違いは、その対象の幅にあります。
IT人材とは、経済産業省 の定義を基本とする場合、「情報技術(IT)分野で活躍する人材」を指します。これには、情報サービス業やITソフトウェア・サービスの提供事業に従事する人、また企業の情報システム部門の従業員も含まれます。
一方でデジタル人材とは、デジタル技術を活用して、企業や社会に新しい価値を創造する人材であり、IT人材よりも広義の概念です。IT人材を含むだけに限らず、マーケティングや営業など、幅広い職種の人材も含まれるでしょう。
デジタル人材が不足している

デジタル人材の不足は、日本だけでなく世界的な課題です。経済産業省の調査によると、2030年には最大79万人のデジタル人材が不足すると推計されています。これには、以下の理由が挙げられています。
- デジタル技術の進化が速い
- デジタル技術を活用した新ビジネスが生まれやすい
- デジタル人材の育成が難しい
こうした背景があるものの、デジタル技術を活用して企業の競争力を高め、社会に貢献するためにはデジタル人材の育成や確保が非常に重要です。
経済産業省が定めるデジタルスキル標準

経済産業省が定めるデジタルスキル標準について、以下に分けて解説します。
- デジタルスキル標準
- DX推進スキル標準
デジタルスキル標準
経済産業省は、2022年12月に「デジタルスキル標準」を策定 しました。デジタルスキル標準は、DX時代のデジタル人材の育成・確保を目的とした指針で、以下の2つの指針から構成されています。
| デジタルスキル標準 | 対象者 | 内容 |
|---|---|---|
| DXリテラシー標準(DSS-L) | 全てのビジネスパーソン | DXの基礎知識や心構えを学習するための項目、そしてDXに必要な人材とスキルを取りまとめた指針 |
| DX推進スキル標準(DSS-P) | DXを推進する人材 | DXを推進する人材の役割や習得すべきスキルの標準 |
参考・出典:「デジタルスキル標準」をとりまとめました!(METI/経済産業省)
デジタルスキル標準は、デジタル人材の育成・確保を支援するツールとして、企業や教育機関等で活用されることが期待されます。
DXの背景
DXの背景には、以下が挙げられます。
- デジタル技術の進化
- 顧客ニーズの多様化
- 競争の激化
- 働き方の変化
インターネットやクラウドコンピューティング、人工知能(AI)などの技術が普及し、ビジネスや社会に大きな影響を与えています。また、少子高齢化や人口減少、グローバル化が進み、企業を取り巻く環境は複雑化していることも踏まえて、デジタル技術を活用した変革が求められるでしょう。
DXで活用されるデータ・技術
DXで活用されるデータ・技術には、以下が挙げられます。
- 人工知能(AI)
- ビッグデータ
- クラウドコンピューティング
- ロボット技術
- ブロックチェーン技術
ただし、活用されるデータ・技術は日々進化するものであり、最新の技術を常に把握し、自社のビジネスへ取り入れる意識を持つ必要があるでしょう。
データ・技術の活用
DXで活用されるデータ・技術の具体的な活用方法は、以下のような例があります。
| データ・技術 | 活用例 |
|---|---|
| データ | 顧客のニーズやトレンドを把握する、新商品・サービスの開発やマーケティング戦略に活用する |
| 人工知能(AI) | 単純作業やルーチン作業を自動化する、商品の価格設定や在庫管理などの意思決定を最適化する、新しいビジネスモデルやサービスを創出する |
| 機械学習 | 商品の価格設定や在庫管理などの意思決定を最適化する |
| ブロックチェーン | データの改ざんや不正を防ぎ、安全な取引を実現する |
| IoT | モノのインターネットを活用し、あらゆるモノからデータを収集・分析する |
企業は、自社の課題やニーズに合わせて、データ・技術を活用し、ビジネスの変革を図りましょう。
DX推進スキル標準
DX推進スキル標準(DSS-P)とは、経済産業省と独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が策定した、DXを推進する人材の役割や習得すべきスキルを定義した指針です。
具体的には以下の5つの人材類型に分けて、それぞれの役割や習得すべきスキルを定義しています。
- 経営層
- 事業部門のリーダー
- DX推進人材
- データサイエンティスト・AIエンジニア
- ビジネスアナリスト・UXデザイナー
DX推進スキル標準は、企業がDX推進人材を育成する際の参考として活用できるでしょう。
ビジネスアーキテクト
ビジネスアーキテクトは、DXの戦略立案や全体設計を行う人材です。主な内容としては、企業の経営戦略や事業戦略を踏まえ、DXを推進するための戦略を策定するなどが挙げられます。
データサイエンティスト
データサイエンティストは、データを分析し、ビジネスに活用する仕組みを構築する人材です。主に、大量のデータを収集・分析し、データから新たな価値を創造します。
必要に応じて、データ分析の結果を基にビジネスの意思決定の支援も行います。
サイバーセキュリティ
サイバーセキュリティは、サイバー攻撃から企業のシステムやデータを守る人材です。企業のシステムやネットワークの脆弱性を分析し、脆弱性を突いたサイバー攻撃から企業を守るための対策が求められます。
また、サイバー攻撃が発生した場合に備え、対応計画を策定・実行する能力も必要です。
ソフトウェアエンジニア
ソフトウェアエンジニアは、DX推進に必要なシステム・アプリケーションを開発する技術者です。ソフトウェアの設計・開発・保守を行うことで、企業のDXを支援します。
加えて、必要に応じた周辺業務に対応したり、ハードウェアにまで携わったりすることもあります。
デザイナー
デザイナーは、ユーザーにとって使いやすく、魅力的なシステム・アプリケーションをデザインする人材です。ユーザーのニーズを理解し、ユーザーが使いやすいシステム・アプリケーションの設計が求められます。
また、システム・アプリケーションのデザインを通じて、ユーザーに新たな価値を提供する必要もあるでしょう。
デジタル人材育成プラットフォーム

デジタル人材育成プラットフォームには、以下の2つが挙げられます。
- マナビDX
- マナビDX Quest
それぞれがどのようなものかを紹介します。
マナビDX
マナビDXは、デジタル人材育成プラットフォームです。DXを推進する人材に必要なスキルが学べる以下の講座を提供しています。
| コース | 内容 |
|---|---|
| デジタルスキル標準講座 | DXを推進する人材に必要な基礎的なスキルを学ぶ |
| 実践講座 | DXを推進するために必要な実践的なスキルを学ぶ |
| 資格取得講座 | DXに関連する資格を取得するための講座 |
また、「マナビDX Quest」というデジタル推進人材育成プログラムがあります。このプログラムは、企業データを使った実践的なケーススタディ教育プログラムと、地域企業と協力したオンライン研修プログラムで構成されています。
マナビDX Quest
マナビDX Questは、マナビDXが提供するデジタル人材育成プログラムの1つです。このプログラムでは、実践的なケーススタディ教育プログラムと地域企業との協働によるオンライン研修プログラムが提供されます。
このプログラムを通じて、以下のことを学ぶことができます。
- DXの基礎知識
- データ分析
- プログラミング
- システム設計
- プロジェクトマネジメント
- コミュニケーション
デジタルに詳しい人でなくても、企業がDXを推進するための変革の考え方やプロセスを学び、同じ志を持つデジタル人材とのつながりを作ることができます。
まとめ

デジタル人材とは、デジタル技術を活用して、企業や社会に新しい価値を創造する人材です。具体的には、AIやビッグデータ、IoTなどのデジタル技術を理解して活用できる人を指します。DXが推進される昨今において、デジタル人材は企業に必要不可欠な存在となるでしょう。
デジタルグロースアカデミアでは、DX推進に必要なデジタル人材の育成体系や研修プログラムを提供しています。エンジニアだけでなく、全ての企業人・自治体職員などにも対応しているため、ぜひお気軽にお問い合わせください。
資料・研修動画ダウンロード申し込みページ
DXに関する様々な資料や動画がダウンロード可能です。