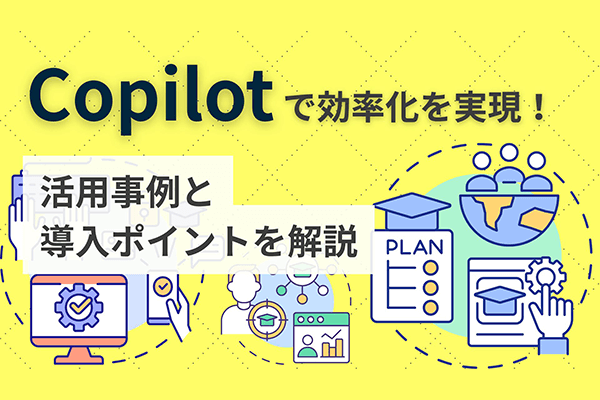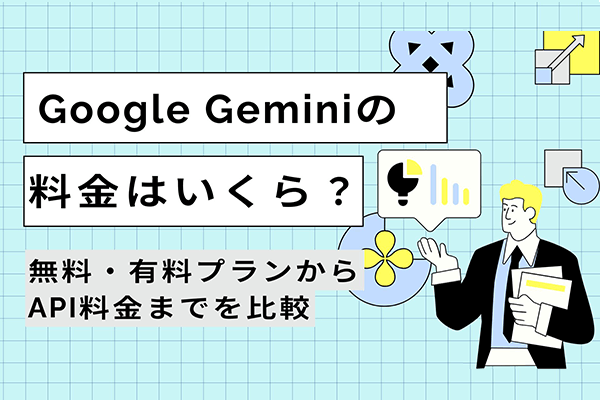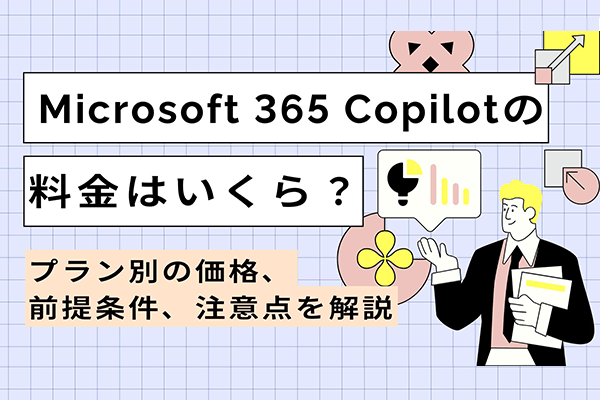DXレポートとは?2025年の崖が提起された理由なども一緒にわかりやすく紹介
更新日:2022年11月21日

DXとは、デジタルトランスフォーメーションの略語で、デジタル技術を用いることで生活やビジネスを変革させていく取り組みのことを指します。
2018年には、日本においても経済産業省が『DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」克服とDXの本格的な展開~』を発表したことから、企業での取り組みが少しずつ始まっていました。
さらに2020年の新型コロナウイルスの大流行により急速な変革が見られているものの、まだ多くの課題が残っている現状もあるのです。
目次
総務省が発表したDXレポートとは

DXレポートとは、経産省が設置する「デジタルトランスフォーメーションに向けた研究会」で行われた議論がまとめられたレポートです。
2018年の9月に最初のレポートが発表され、2022年現在では計3つのレポートが公開されています。
DXレポート~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~
本レポートでは、まず現在の問題について触れられています。
IT化やDX促進を進められない理由には、以下のようなものがあるという指摘です。
- 既存のシステムが事業部門ごとに構築されており、全社で横断的なデータを活用できない
- システムは過剰なカスタマイズによって、複雑化・ブラックボックス化している
- 経営者がDXの推進を望んでいても、既存システムの問題を解決するための人材がいない
- 既存システムの維持管理費が、IT予算の9割以上を占めている
- 市場の変化に対応したビジネスモデルが実現できていない
- 保守運用の担い手がおらずシステムトラブルやデータ滅失等のリスクを抱えている
こうした問題によって、DXを進められないどころか日本はデジタル競争の敗者となり、2025年以降には最大12兆円/年(2018年の約3倍)の経済損失が生じる可能性があるとされています。
そこでDX実現に向けて、複雑化・ブラックボックス化している既存のシステムを刷新させるシナリオを提示しています。
具体的には、クラウド、AI等のデジタル技術をできるだけ早くに取り入れ、ニーズに応じたサービスやビジネスモデルを国際市場に展開させることを展望としているのです。
DXレポート2(中間取りまとめ)
DXレポート2(中間取りまとめ)では、コロナ禍によって浮き彫りとなったDXの本質について触れられています。
最初のDXレポート発行から2年が経過した2020年のレポートとなりますが、DX推進指標の自己診断の結果を提出した企業であっても、95%の企業はDXにまったく取り組めていない現状がある、または取り組みはじめたばかりの段階にありました。
しかしコロナ禍に入り7都府県の緊急事態宣言をうけて、たとえばテレワーク導入率は1ヵ月で2.6倍にも増加しました。
テレワークをはじめとした社内のITインフラや就業規則等の迅速な変更が進み、コロナ禍の大きな環境変化に対応できた企業が散見されたという結果となっています。
事業環境の変化に迅速に適応し、ITシステムのみならず固定概念の変革すらも叶っています。
もとよりDXとは、たんにITシステムを取り入れてデジタル化を目指すだけのものではなく、デジタル化に伴って企業文化や社会の変革を目指すものでした。
コロナ禍においてもビジネス変革に取り組めない企業は、デジタル競争の敗者となるでしょう。
なお、顧客や社会の課題、環境は常に変化するため、変革を目指して終わりではなく、「変革し続ける」という考えが大切であるということにも触れています。
DXレポート2.1(DXレポート2追補版)
2022年に発表された「DXレポート2.1」は、DXを進めている企業は増加傾向ではあるものの、まだ多くの課題が残る、というものです。
「2025年の崖」問題の解決は順調ではないとされている一方、DX推進指標による自己診断結果の提出状況は着実に増加傾向にあり、DXを全社戦略のもと部門横断で推進している企業の割合も増加し続けています。
ただし、デジタル投資の内訳には2018年のDXレポート発出後からの大きな変化がなく、既存システムの維持・管理に約8割が占められているという現状が続いているのです。
また、自己診断結果を提出していない企業が水面下に多数存在することからも、DX推進にはまだ課題が多く残ることがわかります。
「2025年の崖」とは?提起された理由

「2025年の崖」問題が提起された理由には、以下のような課題が広く見受けられるためです。
- IT人材の不足
- レガシーシステムのブラックボックス化
- DXに関する知識不足
IT人材の不足
DXを進めるためには、最新のIT事情や既存システムの仕様に詳しい人材が必要とされています。
多くの企業では、ITシステムの開発や運用を外部企業に委託しているケースがあり、こうした場合には社内にITシステムのノウハウが蓄積されていないため、社内のIT最新化を目指すことの大きな壁になっているのです。
少子高齢化によって、そもそも労働人口が減少しており、ITやDXに詳しい人材の採用が難しい現状もあります。
レガシーシステムのブラックボックス化
レガシーシステムは、以下のような多くの問題を生み出しています。
- ドキュメントが整理されず誰も内部構造を理解できない
- 他のシステムとのデータ連携が不可能
- 性能に限界がある
また、事業部単位での最適化を優先したことにより、全社でいくつものレガシーシステムが乱立していることも課題となっています。
こうした問題が解決しなければ、全社でのデータ利活用は困難を極めるでしょう。
つまり老朽化したITシステムの複雑化・ブラックボックス化が、DX推進の足かせとなっているのです。
DXに関する知識不足
DX推進のためには、全社で共通認識を持つ必要がありますが、そもそも経営層の知識不足が課題となっています。
多くの経営者は、企業の将来的な成長や社会貢献のためにもDXを進める必要性は認識している一方で、具体的にどのように変革したら良いのか、イメージできていないケースがあります。
たとえば経営者から「AIを使ってなにか新しいサービスを立ち上げてみて」と曖昧な指示を出されても、根本的な変革につなげるのは困難です。
経営層が具体的なビジョンを持つことが、DX成功への近道となるでしょう。
「2025年の崖」の対策としてDX推進が必要な理由

先にも述べたように、もし日本企業がDXを推進できずに2025年に突入すると、最大で年間12兆円もの経済損失が発生するといわれています。
DXを進められない場合、既存のシステム(レガシーシステム)が2025年以降も残り続けます。
なおDXレポートでは、2014年の段階でシステム障害による損失が国内全体で4.96兆円にのぼるという試算結果がすでに出ていることに触れられているのです。
「2025年以降は最大で年間12兆円もの経済損失」と警笛を鳴らしているのは、過去の統計データをもとにし、かつレガシーシステムにIT予算の大半がつぎ込まれているという事実があるためです。
すでに日本は2025年の崖に転落しつつある状況だといえるでしょう。
このまま行政や企業が変革を求めて動き出さなければ大きな経済損失の発生が予測されていることから、迅速なDX推進が求められているのです。
「2025年の崖」に向けてDX人材を育成しよう

2025年の崖に転落しないためには、全社をあげたDX推進の取り組みが必要です。
DX人材育成会社のデジタルグロースアカデミアでは、デジタル化・DXに関する研修が充実しています。
いつ・どこにいても受講できるe-ラーニングの整備から企業に合ったコンサルティングまで、幅広いサポートを提供しています。
まずは社内のITの最新化を進めたり、より迅速にDXへの取り組みを強化するために、ぜひデジタルグロースアカデミアにて相談してみてください。
【監修】
日下 規男
ディジタルグロースアカデミア マーケティング担当 マネージャ
2011年よりKDDIにてIoTサービスを担当。2018年IoTごみ箱の実証実験でMCPCアワードを受賞。
2019年MCPC IoT委員会にて副委員長を拝命したのち、2021年4月ディジタルグロースアカデミア設立とともに出向。
資料・研修動画ダウンロード申し込みページ
DXに関する様々な資料や動画がダウンロード可能です。