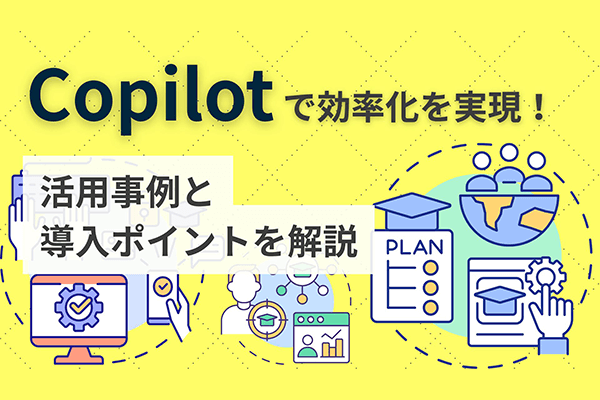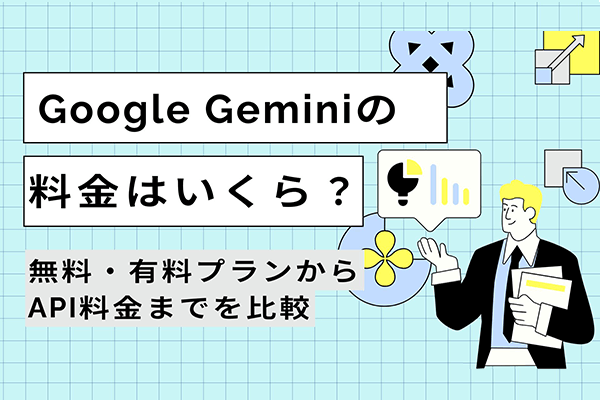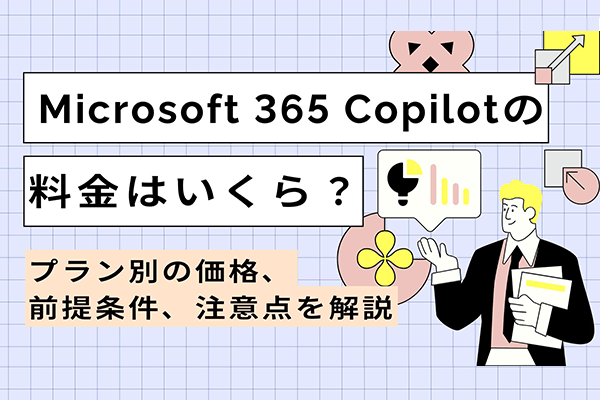DXとは?DXの定義やIT化・デジタル化との違いについて解説
- 公開日:2022年10月11日

現在多くの企業がDXを推進しています。しかし、「DX」という言葉を聞いたことはあっても「DXが何であるのかわからない」という方も多いのではないでしょうか?DXとはデジタル技術を使ったビジネス変革のことです。この記事ではDXの読み方や定義、IT化やデジタル化との違い、DXが注目されている理由などについてわかりやすく解説します。
目次
DXとは

そもそもDXとはどのようなことを指すのでしょうか?ここから詳しく見ていきましょう。
DXはデジタルトランスフォメーションの略
「DX」とは「Digital Transformation:デジタルトランスフォメーション」を略した言葉を指します。DTと略さない理由は、英語圏では「Trans」は「T」と略さずXと略すのが一般的だからです。スウェーデンのエリック・ストルターマン教授により提唱されました。
DXの定義
デジタル技術で生活が変革され、さまざまな活動においてIT(情報技術)をベースに変革させることです。企業においては、顧客や社会のニーズをベースにITを使い事業活動・内容・仕組を全体的に再構築することを指します。
DXとデジタル化の違い
DXとデジタル化は似ているようで異なります。2つの違いについて具体的に解説しましょう。
DXの目的:企業の競争力向上
DXの目的は、データや技術を活用し顧客起点で価値を創出し、ビジネスモデルを「変える」ことです。その結果、競争優位性を確立し、競争力を向上できます。単なるデータ化だけではDXとは言いません。
デジタル化の目的:業務の効率化
デジタル化の目的は紙やパンチカードなどのアナログデータをデジタル化し、業務の効率化につなげることです。DXの前提としてデジタル化の推進が挙げられます。デジタル化の事例は、ワークフローシステム・電子契約の導入やテレワークへの移行などです。
その他の記事はコチラから



DXとIT化の違い

DXとIT化は似ているようで大きく異なります。IT化とはこれまでアナログでやっていた作業をIT化し、生産性を高めることです。具体的には給与計算システムを使って作業時間を短縮、残業時間を減らすことなどです。一方DXは、企業が顧客のニーズによりデジタル化へと変革し、事業内容を再構築します。IT化が企業の一部門だけであるのに対し、DXは全社でビジネスモデルを変革する仕組みです。
なぜDXが注目されているのか
なぜDXが注目されているのでしょうか?背景には2025年の崖問題、新型コロナウイルスによる影響、海外企業による産業構造の変化があります。一つずつ詳しく見ていきましょう。
2025年の崖問題
経済産業省は「DXレポート」で「競争力強化のためデジタル技術を活用し、新たなビジネスモデルに変革するDXを実現できないと2025年以降最大12兆円もの経済損失が生じる可能性がある」と発表しました。DXを実現できないとデジタル競争の敗者となり、システムの維持管理費が高額化したり、セキュリティリスクが高まったりすると警鐘を鳴らしています。
新型コロナウイルスによる影響
新型コロナウイルスによる影響により、企業はテレワークの実現などを余儀なくされ、デジタル化が急速に進みました。「感染拡大を防ぎながら、いかに事業を展開していくか」といった課題を解決するには、DXが必要であると考えた企業が増加しています。

海外企業による産業構造の変化
実際にAIやデータを活用したビジネスの在り方が増えていますが、米国と日本を比較すると日本はDXの取り組みが遅れています。IPAの「DX白書2021」のDXへの取り組み状況を見ると、日本は約56%ですが米国は79%です。日本は米国と比較してもデジタル化も遅れており、DX推進のためには、まずペーパーレス化などデジタル化を進めることが急務でしょう。

DX推進における日本企業の抱える課題と解決策

DX推進における日本企業の抱える代表的な課題は、以下が挙げられます。
- DX人材が不足している
- DXを行う目的・目標・経営戦略が明確になっていない
- DX推進のための社内環境が整っていない
- DX推進のためにコストを割いていない
それぞれの課題における解決策も同時に解説するため、ぜひ参考にしてください。
DX人材が不足している
DX推進における日本企業が抱える最も深刻な課題として挙げられるのが、DX人材の不足です。
2022年の「日本企業の経営課題」調査によると、DX推進における課題として回答した企業のうち84.5%が「DXに関わる人材不足」を挙げています。
DX人材の育成を行う
DX人材の不足に対しては、社内研修や外部研修の充実によるDX人材育成が有効です。
社内研修では、既存の社員に対してDXに必要なスキルや知識を教育できます。また、外部研修では、専門的な知識を持つ講師から学ぶことでより高度なスキルを身につけられるでしょう。
しかし、これらの研修にはコストや時間がかかるため、効率的なDX人材育成のために研修内容の最適化やオンライン研修の導入なども一緒に模索しておくことが大切です。
DXを行う目的・目標・経営戦略が明確になっていない
日本企業がDX推進において抱える課題の一つに、目的・目標・経営戦略が明確になっていないことも挙げられます。
多くの企業がDXを導入することで業務効率化や顧客満足度の向上を目指していますが、それらの目的を達成するための具体的な目標や戦略が定まっていない状況があるためです。
経営層がDXについて学ぶ
この課題を解決するためには、経営層がDXについて学ぶことが必要です。DX推進において目的・目標・戦略が明確になっていないと、各部署での取り組みがバラバラになるためです。
積極的に経営層がDXの重要性やメリットを理解し、具体的な目標や戦略を策定することで、社内の全員が共通の目的に向かって取り組めます。
DX推進のための社内環境が整っていない
社内環境が整っていないことが、DX推進において大きな障害となることもあります。原因は多岐に渡りますが、その中でも関係部署との連携が十分でないことが大きな要因となっています。
例えば、ある企業が新しいシステムを導入する場合、IT部門だけで進めてしまうと他の部署がそのシステムを使いこなせず、本来の効果を発揮できません。また、新しい技術を導入する場合にも関連部署との連携が不十分だと、その技術を十分に活用できなくなります。
社内全体の意識改革を行う
社内環境を整えるためには、社内全体の意識改革を行いましょう。
例えば、業務プロセスをスムーズにしつつ意思決定を迅速に行うために、社内における情報共有やコミュニケーションの改善などによって関連部署との連携を強化します。
また、社員に向けたセミナーや研修を開催し、社内全体でDXについて学ぶことも大切です。DXについての理解が深まれば、社員が自ら改善点を見つけ、積極的に取り組める状態を作り上げられるでしょう。
DX推進のためにコストを割いていない
DX推進において、見えざる課題とも言えるのが投資不足です。
多くの企業が、既存のビジネスモデルを守るために新しい技術やシステムへの投資を控えています。しかし、守りの投資のままでは競争力を失い、生き残りが危ぶまれます。
デジタル化などを行いコストを削減する
解決策としては、デジタル化や自動化などの技術を活用し、コスト削減を図ることが挙げられます。例えば、業務プロセスの自動化により人件費や時間を削減したり、クラウドサービスを活用してITインフラにかかるコストを減らしたりするなどです。
スタート時点では一定の投資が必要なものの、長期的な視点から見ると全体のコストを削減できる場合や、効率化・生産性の向上による売上の増加などによるリターンが期待できます。
DXを推進するための戦略

DXを推進するための具体的な戦略の代表例は、下記が挙げられます。
- 明確なビジョンを策定する
- データを収集・分析し、可視化する
- イノベーションを推進する
- プロセスを見直し、自動化する
- カスタマーエクスペリエンスの向上を図る
- パートナーシップの構築をする
- ITシステムを導入する
これらはITシステムを活用したIT化だけではなく、何を主軸にDXを進めるべきか、ブレないためにはどうするべきかを考えるために必要な戦略も含まれるため、ぜひ参考にしてください。
明確なビジョンを策定する
DXの目的は、組織の価値を高めることです。そのためには、現状の課題や将来の展望を分析し、どのような変革が必要かを明確に定める必要があります。ビジョンがなければ、DXの方向性や優先順位がぼやけてしまい、効果的な施策が打てなくなります。
ビジョンを策定する際には、顧客視点や社会貢献といった外部要素にも目を向けることが大切です。たとえば、顧客ニーズに応える新しいサービスや商品を開発することや、社会課題を解決することで社会的価値を創出することなどが考えられます。
ビジョンを策定したら、それを組織内に共有し、全員が同じ目標に向かって動くことができる状態も必要でしょう。
データを収集・分析し、可視化する
そして、DXの実行には組織の活動や成果に関する情報・データが不可欠です。データを収集・分析することで、現状の把握や問題点の発見、改善策の検討などができ、データは客観的で信頼性が高く、意思決定の根拠として有効だからです。
データを収集・分析する際には、目的や仮説を明確にし、必要なデータを選別し、適切な方法で処理することが重要です。たとえば、売上や利益率などのKPI(重要業績評価指標)を設定し、それらの変化や傾向を分析することや、顧客満足度や離職率などの指標を用いて組織の課題や改善点を探ることなどが挙げられます。
データを収集・分析したらデータをグラフや表などに整理し、データの理解や共有が容易にできるよう可視化しましょう。
イノベーションを推進する
DXの成果は、新しい価値や解決策を創出するイノベーションによって生まれます。イノベーションの推進は、創造性や挑戦意欲、協働性などの人的要素に依存するため、組織の文化や制度を変える必要があります。
そのためにも、失敗を恐れないことや多様な視点を尊重するといった姿勢を持つことが重要なポイントです。たとえば、失敗から学びや改善点を見つけることや、異なるバックグラウンドや専門性を持つ人たちとアイデアを交換することなどです。
イノベーションを推進したら、それを評価や報酬に反映します。これにより、イノベーションへのモチベーションや継続性も高めていきましょう。
プロセスを見直し、自動化する
DXの推進においては、プロセスの見直しと自動化により、業務効率や品質の向上も必要です。プロセスを見直すことで課題を明確化でき、無駄な作業やミスを減らせるほか、自動化することで人手に頼らないスピーディーで正確な業務を実現できます。
たとえば、請求書の発行や入金確認などのルーチンワークは、人間が行うと時間やコストがかかり、ミスも起こりやすいものの代表例です。しかし、これらの作業をシステムに任せることで、短時間で正確に処理でき、人間はより付加価値の高い業務に集中できるでしょう。
このようなプロセスの見直しと自動化は、従業員の満足度やモチベーションを高めるためにも必要です。また、顧客に対しても迅速かつ正確なサービスを提供できるため、信頼性や満足度の向上が見込めます。
カスタマーエクスペリエンスの向上を図る
他にも、カスタマーエクスペリエンスの向上により、顧客のロイヤルティや売上を高めることもできます。顧客が商品やサービスを購入したり利用したりする際に感じる感情や印象が良ければ良いほど、顧客はリピートしたり口コミしたりする可能性が高まるためです。
たとえば、オンラインショッピングでは、商品の検索や注文が簡単であったり、配送が早かったり、返品や交換が柔軟であったりすることがカスタマーエクスペリエンスに影響します。また、商品に関する質問や不満に対しても、迅速かつ丁寧に対応することも求められるでしょう。
このように、カスタマーエクスペリエンスの向上により、顧客は商品やサービスに対して高い満足度や感謝を持ちます。また、顧客は自分の体験を他人に伝えたり、SNSなどでシェアしたりすることで、商品やサービスの認知度や評判を高め、結果として売上や利益につながるという好循環も期待できます。
パートナーシップの構築をする
DXを推進するためには、自社だけでなく、他社やスタートアップ企業、自治体などと連携し、パートナーシップの構築も必要となります。それぞれの組織が持つ強みや特徴を生かしながら、デジタル技術やデータを共有し、新しいサービスや事業の創出を狙えるためです。
また、市場競争力を高めるだけでなく、イノベーションの創出や社会課題の解決にも貢献します。異業種や異分野の知見やアイデアが交流されることで、新たな価値や可能性が生まれることもあるでしょう。
パートナーシップの構築は、DXのスピードやスケールを拡大できる方法のひとつとなるため、積極的に戦略として取り入れてみてください。
ITシステムを導入する
DXの推進においては、デジタル技術やデータを効果的に活用するために、ITシステムの導入も欠かせません。導入によって、業務効率化やコスト削減だけでなく、顧客体験の向上や新しいビジネスモデルの創出にもつながります。これは、従来のアナログなプロセスをデジタル化し、自動化や最適化を図ることができるからです。
たとえば、ネット通販でおなじみの「おすすめ機能」は、AIがユーザーの好みを推測し、関連する商品を自動的に表示するITシステムです。AIが急速に発展する昨今においては、こうしたシステムの活用は大きくビジネスモデルの変革に変革に貢献すると考えられます。
また、多くの業務を効率よくこなせるようにITシステムを導入できれば、これまで以上に顧客ニーズへ応えられる企業体制も整えられるでしょう。
DXで活用される技術

DXで活用される技術には、AI・IoT・クラウド・RPA・BIなど様々なものがあります。ここから詳しく見ていきましょう。
AI
AIとは「人工知能(Artificial Intelligence)」と呼ばれ、コンピュータに人間のような推論や問題解決などを行わせる技術のことです。現在はAIの第三次ブームといわれており、本格的な定着が期待されています。「機械学習」は、AIに大量のデータを読み込ませAIが自分で学習する仕組みです。部屋の状態に合わせて温度調節してくれるエアコンや掃除ロボットのような家電、画像認識システムなど、機械学習は様々な分野で活用されています。さらに現在は、機械学習を発展させ、ニューラルネットワークの仕組みを取り入れた「ディープラーニング」により高度な分類や判断が可能です。
IoT
「IoT」とは「モノのインターネット」です。コンピュータなどのIT機器だけではなく、産業用機械・家電・自動車・洋服・靴など、あらゆるモノをインターネットに接続する技術を指します。IoTの仕組みは、センサーを搭載した機器や制御装置がインターネットを通じて様々なやり取りができることです。IoTの環境が整備された結果、ビッグデータを収集や蓄積、分析できるようになり、高い付加価値を生むことができるようになりました。IoTは金融・農業・医療・物流など、あらゆる産業で活用されています。
クラウド
「クラウド」とはインターネットを通じて、必要最低限の機器構成でサービスを利用する形態です。インターネット上にあるソフトウェアやハードウェアなどを物理的な存在場所を意識せずにオンデマンドでスケーラブルに利用できます。クラウドの代表的なサービスは、SaaS・PaaS・IaaSなどです。身近なSaaSの事例としてはGmail、PaaSやIaaSの事例としてAWSがあります。
RPA
「RPA」とは「Robotic Process Automation」を略した言葉で、従来人間が行っていた定型的な業務をソフトウェアで自動化・効率化する仕組みです。具体的にはWebブラウザを使った情報の閲覧・取得、表計算ソフトへの書き込み、社内情報システムへの入力を指します。単独の業務だけではなく、それぞれを組み合わせた一連の業務フローとして自動化・効率化します。
BI
「BI」とは「Business Intelligence」を略した言葉で、経営戦略に役立てるために、蓄積されたデータを視覚化したり分析したりするシステムのことです。経営者などがデータに基づき、意思決定を行うことを支援します。
DXの導入事例
DXは家庭分野・タクシー分野・金融分野など、様々な分野で活用されています。ここからDXの導入事例について見ていきましょう。
参考:なぜ多くの企業はDX推進に失敗するのか?その理由や成功の秘訣とは
家庭分野
IoTやスマート家電は炊飯器・洗濯機・エアコン・携帯電話・携帯情報端末などで利用されています。IoTやスマート家電は「組み込みOS」と呼ばれる専用のソフトウェアと必要最低限のメモリ・CPU・ROMを搭載したハードウェアで構成されているのが特徴です。利用者の操作に合わせて細やかな制御ができます。
タクシー分野
タクシー分野には、アプリを活用した配車サービスがあります。配車サービスを利用するとタクシーを指定の場所に呼ぶことが可能です。配車地・降車地の指定でタクシーを呼べるため、タクシー乗り場で待つ必要がありません。海外でも利用できるアプリもあるため、旅行や出張の時でも使えます。
金融分野
キャッシュレス決済は現金を使わずに清算できる決済方法、Suicaやnanacoなどが代表的な例です。キャッシュレス決済は、現金の持ち合わせがなくても利用できたり、支払い履歴が残ったりします。支払い方法はプリペイドカード・デビットカード・クレジットカードの3種類です。支払いの手軽さ、ポイント還元、管理のしやすさなどから急速に広まっています。
DX人材になるには?

DX人材になるには、以下に挙げた例を含めたさまざまなスキルや知識が求められます。
| 必要なスキル・知識 | 詳細 |
|---|---|
| デジタル戦略の経験 | 企業がデジタルテクノロジーを活用して自社のビジネスを進めるための戦略 |
| 製品開発・サービス設計の経験 | ユーザーのニーズを把握し、それに応じた製品やサービスを開発すること |
| デジタルテクノロジーに関する業務経験 | デジタルで情報を処理する技術を活用してビジネスを進めること |
これらのスキルや知識を身につけるには、研修やセミナーに参加することがおすすめです。
そこで学ぶことで、実践で活用できる知識やスキルを身につけることができます。また、実際に業務へ活用して実践を経験することで、自分のスキルや知識の量を確認できます。
他にも、必要に応じてテクノロジー関連スキルを習得したり、デジタルテクノロジーを活用した副業の経験を積んだりすることも検討しましょう。
まとめ

DXとは、様々な活動においてIT(情報技術)をベースに変革させることです。DXが注目されている理由は、2025年の崖問題や新型コロナウイルスによる影響などがあります。DXで活用される技術は、AI ・IoT ・クラウド・RPA ・BIなど、代表的な導入事例はスマート家電・配車サービス・キャッシュレス決済などです。
DX人材の育成の課題を解決したい方にはDX人材育成サービス「ディジタルグロースアカデミア」がおすすめです。当サービスは、社員のやる気と行動を引き出し、事業のDXを加速させます。
「社員のデジタルリテラシーを上げたい」「デジタル変革してビジネス拡大につなげたい」とお考えの方は、ぜひ問い合わせてみてください。
【監修】
日下 規男
ディジタルグロースアカデミア マーケティング担当 マネージャ
2011年よりKDDIにてIoTサービスを担当。2018年IoTごみ箱の実証実験でMCPCアワードを受賞。
2019年MCPC IoT委員会にて副委員長を拝命したのち、2021年4月ディジタルグロースアカデミア設立とともに出向。
資料・研修動画ダウンロード申し込みページ
DXに関する様々な資料や動画がダウンロード可能です。