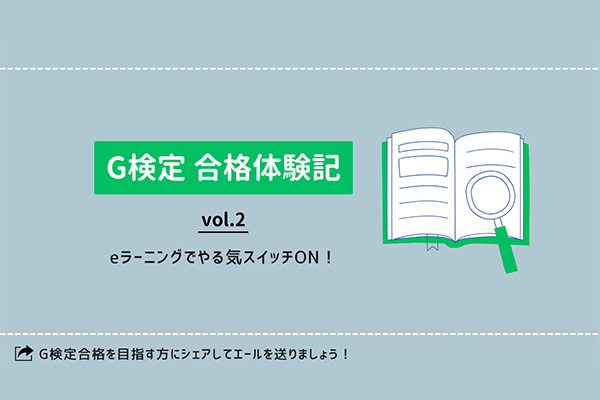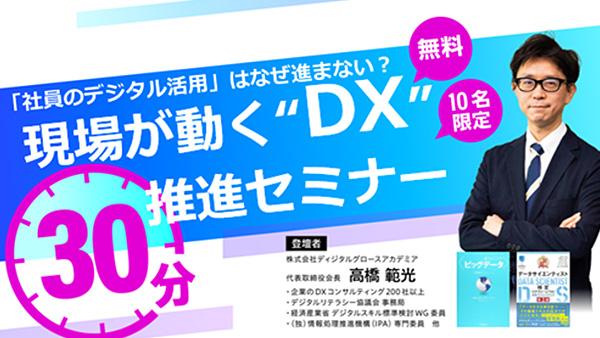【業界別】DXの事例│デジタル化との違いなどもわかりやすく紹介
- 公開日:2023年3月3日
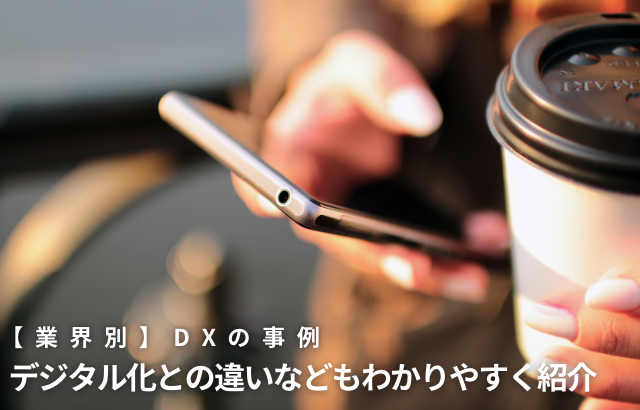
世界的に注目されるDXは、日本でも推進している企業の数が増えています。近年では日常生活に溢れる身近な製品やサービスがDX推進によって生まれ変わっており、仕事でデジタル技術に触れる機会のない人でも、知らずしらずのうちにDX推進によるメリットを享受しているのです。
本記事ではDXの身近な事例を参考に、デジタル化やDX推進のヒントとなるIT技術について紹介します。
DX推進を考えている、DX推進に必要なノウハウを学びたい、DX人材としてスキルを伸ばしたいという人はぜひ読んでみてください。
目次
そもそもDXとは?

そもそもDXとは、デジタルトランスフォーメーション(Digital Transformation)の略称で、企業や組織がデジタル技術を活用してビジネスモデルやプロセス、サービスなどを変革することを指します。
DXの目的は、競争力の強化や生産性の向上、イノベーションの促進などにあります。DXを実現するためには、経営者の意思決定や組織文化の変革、人材育成やパートナーシップなど、多方面にわたる取り組みが必要です。
そして、DXは単にITシステムを導入するだけではなく、デジタル化によって顧客や社会のニーズに応える価値を創出することが大切です。
では、ここで取り上げた「デジタル化」とはどのようなものか確認しておきましょう。
DX化とは?
DX化という用語は、企業や組織がデジタル技術を駆使して、市場における競争力を強化し、その結果として明確な優位性を築き上げた状態を表す造語です。
主に、ビジネスモデルの変革や業務の効率化、顧客体験の向上などを通じて実現され、結果的に組織の価値を大きく高めた状態と言えます。
そのため、DX化はただ単にデジタルツールを導入することではなく、それらを活用して業務を根本から見直し、革新的な変化を遂げることを意味しています。
IT化とは?
IT化とは、従来アナログ手法で行われていた作業をデジタル技術を使って行うように変えることです。
一方で、DX化は、企業や組織がデジタル技術を駆使して変革を遂げる目標を指します。
そのため、DX化とIT化には、目標と手法という違いがあります。
つまり、DX化を実現するための具体的な手法がIT化です。
関連記事

デジタル化とは?
デジタル化とは、アナログな業務をデジタルに変換するプロセスのことを指します。具体的には、紙を使った事務処理をペーパーレス化したり、電子契約を導入したりするなどです。
また、社内のマニュアルや資料などを電子化、およびクラウド化してアクセスしやすくするなどもデジタル化の例として挙げられます。
DXとデジタル化の違いとは?

DXとデジタル化の違いは、活用と変革にあります。デジタル化で単に技術やツールを導入するだけではなく、ビジネスモデルやプロセス、組織文化などを変革してDXを達成します。
業務効率やコスト削減などの目的で、既存のプロセスやサービスにデジタル技術を適用するという手段は、『デジタル化』です。このデジタル化を活用して、新しい価値を創造したり、競争力を高めたりすることが『DX』となります。
そのため、デジタル化は現状の改善に重点を置くのに対し、DXは、未来の創造に焦点を当てると言えます。DXは、デジタル化の先にある戦略的な取り組みとして考えましょう。
デジタル化の身近な例

紙書類のデジタル化
紙書類は次々とデジタル化が進んでいます。
FAXやメールといったツールでやり取りされていた取り引きが、すべてオンライン上で完結するようになりました。
具体的な事例は受発注や電子契約などです。
デジタル化されたこれらの書類はすべてクラウドやサーバーによって管理されます。
クラウドによる情報共有
情報共有もデジタル化が進んだ事例の一つです。
既存の情報共有は、書面やメールといったツールを用いて行われていました。
しかし、こうした方法では個々人の手を介して情報が伝播されるため、伝わる速度は遅く、人為的な伝達ミスによる伝え漏れがどうしても発生してしまいます。
クラウドによる情報共有は、情報の伝搬速度を低下させず、伝え漏れが出ることもありません。
DXによって情報共有は速度と確実性が担保できるようになったのです。
業務の進捗管理もより簡単にできるようになるため、業務効率も上がります。
ビジネスチャット
ビジネスチャットもDXによってより使いやすく便利になった事例の一つです。
既存のメールや対面といった方法でのコミュニケーションは、素早い情報を発信しづらく手間がかかることが問題でした。
しかし、ビジネスチャットならより速く正確に情報を伝えられます。
オンライン会議
オンライン会議はデジタル化によって生み出された新しいコミュニケーション方法です。
自宅やコワーキングスペースなど、会社に身を置かずとも会議に参加できます。
オンライン会議に使われる多くのサービスは無料で始められ、特別なツールを使わずとも利用できます。
DXの身近な例

DXの身近な例を見ていきましょう。
- 在宅ワーク
- スマート家電
- フードデリバリー
- オンラインスクール
- 配車サービス・相乗りタクシー
- 保険料のキャッシュバック
在宅ワーク
在宅ワークは、近年でもっとも広く認知されたDXの事例です。
ネットワーク環境にアクセスすることでどこでも仕事ができる仕組みで、新型コロナウイルス感染症の流行によって多くの企業が導入するようになりました。
また、オンライン上で社内システムに安全にアクセスできるよう、セキュリティ関連の技術も飛躍的に向上した点もDX事例として評価されています。
スマート家電
エアコンや冷蔵庫でお馴染みのスマート家電も、生活家電の使い勝手向上に貢献したDX事例です。
自分の手で操作して使うことが当たり前だった生活家電は、DXにより離れた場所からの遠隔操作が可能になりました。
機能によっては、節水や節電というような節約につながるものもあるため、家電製品市場でも人気を博しています。
フードデリバリー
DXが出前を大きく変革させたフードデリバリーも導入事例と言えるでしょう。
既存の出前は、飲食店が自社でデリバリー人員を用意しておく必要がありました。
出前が入らなければ人件費は無駄になり、注文が殺到すると人手不足により売り上げ機会の損失を出してしまうといった状態がDXにより解消されました。
また、好きな時間帯だけ働けるというフードデリバリー特有の働き方も、DXのデジタル技術が支えています。
出前をしたい企業と働き手、サービスの利用者の三方にとって便利な仕組みを、フードデリバリーは提供しています。
オンラインスクール
オンラインスクールは、DXが習い事の自由度を向上させた事例です。
従来の習い事といえば、特定の時間・特定の場所で生徒と先生が顔を合わせる必要がありました。
しかし、オンラインスクールは先生と生徒の双方が一ヶ所に集まる必要はなく、講義内容を記録しておけば生徒はいつでも好きな時間に勉強できます。
一度にたくさんの生徒に講義ができるようになるため、スクール運営側の収益も最大化するというメリットがあります。
配車サービス・相乗りタクシー
配車サービスや相乗りタクシーも、従来のサービスがDXによって刷新された事例です。
従来のタクシーと言えば、車を捕まえるために人が道端でタクシーを待ち、タクシー側も乗客を探して待つ時間がありました。
しかし、配車サービスや相乗りタクシーは、乗客がタクシーの所在をネットやアプリで確認できるため、車の到着を待つという手間が省けます。
運転手も、車を必要とするカスタマーを探す必要がなくなるので効率良く乗客を見つけられます。
保険料のキャッシュバック
生命保険や医療保険の保険料キャッシュバックも、DXによって導入された新たなサービス事例です。
この仕組みは、医療保険の加入者が健康に過ごして保険金を請求しなかった場合、保険料の一部をキャッシュバックするという制度です。
キャッシュバックには、被保険者の健康状態を分かりやすく可視化できる一定の指標が用いられています。
被保険者も保険を使わずに済むよう自身の健康状態を気にかけられる一つのきっかけになっています。
【業界別】DX の事例

ここからは、DX の事例を以下に分けて紹介します。
- 製造業
- 小売・流通業界
- 交通業界
- 金融業界
- 建設・不動産業界
- 介護・医療業界
- メディア・エンターテインメント業界
- 観光業界
- 農業・食品業界
- 教育業界
製造業
製造業のDXの事例は、以下の3つです。
- スマートファクトリーの導入
- デジタルツインの活用
- サプライチェーンのデジタル化
スマートファクトリーの導入
スマートファクトリーとは、製造業の心臓部とも言える生産管理や原価管理をデジタル化し、効率的な工場運営を実現する最先端のシステムのことです。
製造現場はリアルタイムでのデータ分析や迅速な意思決定が可能となり、品質向上、コスト削減、納期短縮といった複数のメリットを得ることができます。
その結果、生産性の向上はもちろん、柔軟で迅速な対応も可能となります。
デジタルツインの活用
デジタルツインとは、リアルな世界のデータを基に、バーチャル空間にその複製を作り出す革新的な技術のことです。
製造業界では、IoTやAIの進化によって関心が高まっており、製品開発や生産工程を効率化できます。
業務のスピードアップやコスト削減、新たなイノベーションを生み出す基盤を整えられるでしょう。
サプライチェーンのデジタル化
サプライチェーンのデジタル化は、運営をデジタル技術で一新し、より効率的にするものです。
非財務情報(財務データ以外の経営戦略や課題、サステナビリティへの取り組みなど)をデジタル化し、サプライチェーン全体の効率を格段に向上します。
結果として、リードタイムの短縮やコスト削減だけでなく、より透明性の高いビジネス運営が実現可能です。
関連記事

小売・流通業界
小売・流通業界の事例は、以下の4つが挙げられます。
- オムニチャネル戦略
- データ分析とデジタルマーケティングの活用
- モバイル決済サービスの導入
- 自動化された在庫管理システムの導入
オムニチャネル戦略
オムニチャネル戦略とは、オンラインとオフラインの両方の販売チャネルを融合させ、顧客がどこでもスムーズに買い物を楽しめるようにする手法のことです。
例として、コンビニ大手のローソンは、AIを駆使した先進的な発注システムを取り入れ、店舗間での商品の連携を実現しています。
データ分析とデジタルマーケティングの活用
データ分析とデジタルマーケティングを活用することで、ユーザー・販売データから顧客の行動パターンや好みを深く理解し、それに合わせたマーケティング戦略を展開することも可能です。
無印良品は、顧客が自社アプリ「MUJI passport」を使って店舗を訪れたり商品を購入するたびにポイントがたまる仕組みを提供しており、顧客エンゲージメントの強化に努めています。
モバイル決済サービスの導入
さらに、モバイル決済サービスの導入も、顧客にとっての買い物の手軽さとスピードを向上させるDXの事例です。
実際に、百貨店の三越伊勢丹は、リモートショッピングアプリを通じて、顧客がビデオチャットでスタッフに直接質問でき、商品をリアルタイムで見ることができるサービスを開始しています。
自動化された在庫管理システムの導入
最後に、自動化された在庫管理システムを導入することにより、在庫管理の効率化を図って、常に適切な在庫レベルを保つこともできます。
この点でローソンは、AIを活用して半自動の発注システムで他店舗との連携を図りながら、最適な商品の取り揃えを実現しています。
交通業界
交通業界の事例は、以下の2つです。
- モビリティサイネージクラウドの導入
- 交通インフラのデジタル化
モビリティサイネージクラウドの導入
デジタルサイネージとは、インターネットを使って、さまざまな場所にある複数のサイネージ端末をまとめて管理するシステムのことです。
モビリティの業界では、広告やお知らせを流す基本的な機能に加え、時刻表や運行情報といった重要な交通情報も発信できます。
同様のシステムとして、西日本鉄道は「MMvision」を春日原駅の新ホームに導入し、2022年8月28日から利用を開始しています。
交通インフラのデジタル化
鉄道業界では、交通インフラのデジタル化でDXが実施されています。
主に、労働力不足やコスト高騰といった問題に対処しつつ、運行の効率化やサービス向上を図る動きが挙げられます。
例えば、センサーやカメラを道路に設置し、交通の流れをリアルタイムで監視するなどです。
金融業界
金融業界の事例は、以下が挙げられます。
- デジタルモーゲージの活用
- オンラインバンキングの強化
- ブロックチェーン技術の活用
デジタルモーゲージの活用
金融業界で、デジタルモーゲージを使えば、スマートフォンやPCを通じて住宅ローンの状況や審査の進捗を手軽にチェックできます。
いつでも、どこにいても自分のローン情報にアクセスできるという利点があり、金融機関はより良い顧客サービスを提供することが可能です。
オンラインバンキングの強化
オンラインバンキングも、金融業界のDX事例に挙げられます。
日夜問わずアクセス可能で、利便性を高められます。
ただし、この利便性の裏で不正送金のリスクが増加していることも事実です。
それに対応するため、金融機関はセキュリティを一層厳格にしています。
例えば、三井住友銀行は2023年3月からインターネットバンキングのログインセキュリティをさらに強化しています。
ブロックチェーン技術の活用
ブロックチェーン技術は、金融業界において業務の効率化、新しいビジネスモデルの開発、コスト削減など、多くの利点をもたらしています。
例えば、貿易金融における文書の管理や不動産取引時の契約書の管理など、具体的な使用例があります。
建設・不動産業界
建設・不動産業界のDX事例は、以下の2つです。
- BIM
- バーチャル展示場の導入
BIM(建築情報モデリング)の活用
BIM(Building Information Modeling:建築情報モデリング)は、建設業界で革新的なITツールの一つです。この技術を活用すると、建物の設計や施工におけるミスを減らし、作業時間を短縮できます。
また、BIMでは、建材や設備などがデジタル上で組み合わされ、それぞれのサイズや材質、組み立てに必要な手順や時間などまで統合できます。
そのため、プロジェクトに関与する人々は、従来の図面だけでなく、詳細データをもとに効率的に作業を進めることも可能です。
バーチャル展示場の導入
一方、バーチャル展示場は、現代の非接触が求められる状況において、商品やサービスを宣伝する新しい手法です。
この仮想空間を利用することで、場所や時間に縛られることなく、まるで実際の展示場にいるかのように商品を紹介できます。
例えば新潟では、住宅事業者が集まって作ったハウこま島にVR住宅展示場が設けられています。
こうした取り組みにより、顧客は自宅にいながらにしてVRを通じて住宅見学を行うことができ、時間や労力も節約できるでしょう。
介護・医療業界
介護・医療業界のDX事例としては、以下が挙げられます。
- オンライン予約システムの導入
- 電子カルテの導入
オンライン予約システムの導入
医療業界のDXでは、オンライン予約システムが注目されています。
以前は電話や対面で行われていた予約が、オンライン化されることで、患者は自分の都合に合わせて手軽になりました。
また、医師のスケジュール管理も効率化され、時間やコストの削減にも繋がります。
そのほかにも、オンラインでのキャンセル処理が可能になることで、無断キャンセルが減少し、診療時間を最大限に活用できることも期待されています。
電子カルテの導入
医療業界におけるDXの代表例として、電子カルテの導入も挙げられます。
主に、患者の診療情報をデジタルで管理し、医療スタッフがリアルタイムで情報を共有できるため、診断の正確性が高まり、治療が向上します。
また、医療機関間の情報共有がスムーズになることで、患者の不要な重複検査を減らし、医療の効率化にも寄与するものです。
メディア・エンターテインメント業界
メディア・エンターテインメント業界のDX事例は、以下の2つです。
- ストリーミングサービスの導入
- 仮想現実(VR)や拡張現実(AR)の活用
ストリーミングサービスの導入
メディア業界におけるDX事例では、ストリーミングサービスを取り入れています。
サービスの普及により視聴者は、いつでもどこでもお気に入りの番組や映画を楽しめるようになりました。
さらに、AIが提供するおすすめ機能が視聴者の関心を引きつけ、満足度も高めています。
仮想現実(VR)や拡張現実(AR)の活用
一方、VR(仮想現実)やAR(拡張現実)は、エンターテイメントの世界で導入されています。
それぞれの技術を駆使することで、ユーザーはこれまでにないリアルな体験に浸ることができます。
例えば、映画の製作現場では、バーチャルプロダクションを通じてリアルタイムでCGIや視覚効果を取り入れ、より迅速に作品を仕上げるなどです。
観光業界
観光業界のDX事例としては、以下の2つが挙げられます。
- デジタル観光ガイドの提供
- オンライン観光体験の提供
デジタル観光ガイドの提供
観光業界のDX事例では、デジタル観光ガイドの提供が実施されています。
例えば「京都市観光マップ」というアプリは、京都市が提供している便利なデジタルガイドの代表例です。
同アプリは、GPSを使って現在地の周辺情報を教えてくれます。
この機能により、ただの観光地案内にとどまらず、地元の人しか知らないような絶品グルメや隠れた宿、季節ごとの特別なイベント情報も手に入ります。
オンライン観光体験の提供
また、オンラインでの観光体験もDXの事例といえます。
例として、「バーチャル沖縄」は、新型コロナウイルスの影響で観光客が減少したことを受け、沖縄の美しい景色を世界中の人々に届けるために作られました。
同サービスでは、先ほどエンターテインメント業界で触れたVR技術を使って、沖縄の絶景や自然の美しさを、まるでそこにいるかのように体験できます。
関連記事

農業・食品業界
農業・食品業界のDX事例は、以下の通りです。
- RPAの導入
- 農業IoTの活用
RPAの導入
農業・食品業界では、RPAの導入がDXの事例として挙げられます。
例えば、ドン・キホーテ(PPIH)は、RPA技術を駆使して170種類もの業務を自動化し、作業のスピードと正確性が大幅にアップしました。
さらに、三井住友海上火災保険では、特にバックオフィスの作業にRPAを取り入れて成功を収めています。
農業IoTの活用
一方、農業分野でもIoT(Internet of ThingsがDXの事例として挙げられます。
農場に設置されたIoTデバイスで、土壌の状態(土壌の湿度やpH)や気候をリアルタイムで監視できます。
そのため、農作物の量と質の両面での改善を実現できます。
また、水門の管理を自動化するシステムを導入することで、手間を減らしながら生産性を高めることも可能です。
教育業界
教育業界のDX事例としては、以下の2つが代表的です。
- 学習管理システムの導入
- デジタル教材やeラーニングコンテンツの提供
学習管理システムの導入
教育業界のDX事例では、オンライン授業への出席と課題の提出を、リアルタイムで確認できるなどが挙げられます。
例として神戸大学は、教育の質を高めるために、オープンソースソフトウェアのMoodleをカスタマイズして開発した学習管理システム(LMS)を採用しました。
同システムは、教育プログラムの管理を効率化し、eラーニング教材の作成をサポートする機能を備えています。
この導入により、学生のオンラインでの学習活動や課題の提出状況をリアルタイムで確認できるようになり、教師と学生のコミュニケーションもさらにスムーズになっています。
デジタル教材やeラーニングコンテンツの提供
また、デジタル教材やeラーニングコンテンツの提供もDXの事例です。
現代のビジネスシーンでは、「リスキリング」という学習の概念が注目されています。
そのため、従業員が既存の職から新しい成長分野への転職を目指し、必要なスキルや知識を身につける必要があります。
その際に、デジタル教材やeラーニングが役立つでしょう。
DX推進のために活用できるデジタル技術

ここからは、DX推進のために必須とも言える8つのデジタル技術についてご紹介します。
それぞれの技術はお互いを支え合っているので、その点もイメージしておくと覚えやすいでしょう。
- AI
- ビッグデータ
- クラウド
- IoT
- RPA
- MA
- SFA
- CRM
AI
AIは、人工知能(Artificial Intelligence)でありDX推進に欠かせないデジタル技術の一つです。
AIによって問題の定義や解決は自動で繰り返され、デジタル技術を適用するサービスはより最適化されます。
より少ない人員とコストでサービスが提供できるようになるため、効率良く利益が生み出せるようになるでしょう。
ビッグデータ
ビッグデータはそれぞれの要素が複雑に絡み合い、人の力では解析が困難な膨大な量のデータを意味します。
従来のデータとは違い、保存されるデータの形式は動画や音声以外にもさまざまです。
GPSによる位置情報や天気のようなリアルタイム情報も一緒に記録されるため、より精密なデータ分析が可能になります。
クラウド
クラウドとはインターネットを介して提供されるサービスの総称です。
オンライン上で手続きが完結するのであれば、どのようなサービスもクラウド上で実現可能です。
DXに用いられるデジタル技術の大半は、オンラインにアクセスしていることが前提となるため、クラウドの存在はDXにとって欠かせません。
IoT
IoTはインターネット上にないものをインターネットに接続することを意味し、しばしば「モノのインターネット」とも表現されます。
従来であれば、オンライン上にないものは人が自力で操作するしかありませんでした。
しかし、IoTの登場によりさまざまなモノがインターネットに接続できるようになったため、技術的な革新が見込まれる領域が一気に広がっています。
RPA
RPAはパソコンを使った業務を自動化させるためのデジタル技術です。
以前であれば人の手を介して行われていた作業を、RPAが代行して行います。
キーボードやマウスの操作以外に、簡単なデータの抽出やエラーの修正といった処理能力を有するものもあるため業務効率が上がるのが大きなポイントです。
MA
MAとはマーケティングオートメーションの略称で、顧客管理を担うデジタル技術です。
単純に蓄積された顧客情報を管理するだけではなく、顧客の趣味嗜好に合わせたカスタマイズが容易であるという点に魅力があります。
MAによってコンテンツやサービスの提供管理、購買意欲を掻き立てる施策を打つことができます。
SFA
Sales Force Automationは、営業の進捗管理をサポートするデジタル技術です。
通常、営業は見込み客を探索した上でどこに営業アプローチをかけるかを選定します。
タスク選定はすべてデータベースからの分析を参考にしているため、営業効率も上がります。
CRM
CRMとはCustomer Relationship Managementの略称であり、企業とユーザーの関係性をより良く保つためのデジタル技術です。
ユーザーの個人情報や購買履歴を一元管理し、嗜好に合った提案をサポートするため顧客満足度の向上に貢献します。
DXを推進するメリットとは?

ここからは、DXを推進するメリットを以下の6つに分けて解説します。
- 競争力の向上
- 効率性の向上
- 新たなビジネスモデルの創出
- 顧客満足度の向上
- データに基づく意思決定
- 市場のニーズに迅速に対応
競争力の向上
まず、DXを推進すると、企業の競争力を向上させることができます。なぜなら、自社の強みや差別化要素を明確にし、顧客に価値を提供できるようになるからです。
例えば、AIやクラウドを活用して、商品やサービスの品質やスピードを高めたり、オンラインでの販売やマーケティングを強化したりできます。
また、デジタル技術を使って、自社の業務プロセスや組織構造を最適化し、柔軟性やスケーラビリティを高めることも可能です。
効率性の向上
次に、DXを推進することによって、企業内における効率性を向上させることができます。デジタル技術を使えば、業務の自動化や省力化、コスト削減やエラー防止などを実現できるためです。
例えば、RPA(ロボティックプロセスオートメーション)やBPM(ビジネスプロセスマネジメント)などのツールを使えば、人間が行っていた煩雑な作業やルーチンワークを機械に任せることができます。
これにより、ヒューマンエラーを減らして正確性を高めたり、人件費を削減したりなどを実現可能です。
新たなビジネスモデルの創出
先ほど軽く触れたように、新たなビジネスモデルの創出もDX推進によるメリットの1つです。既存の商品やサービスに付加価値を与えたり、新しいニーズや市場に対応したりするなどを実現できるからです。
例を挙げると、VR(仮想現実)やAR(拡張現実)などの技術を使った場合、顧客に没入感や体験価値を提供できます。ブロックチェーンやトークンなどでは、信頼性や透明性の高い取引やサービスの提供や、新しい収益源やコミュニティを構築もできます。
顧客満足度の向上
DXの推進で得られるメリットには、顧客満足度の向上も含まれます。効率化による迅速な対応や、顧客のニーズや行動に基づいた商品やサービスを提供できるようになるためです。
具体例を挙げると、CRM(顧客関係管理)やビッグデータなどを活用した場合、顧客のプロフィールや購買履歴、フィードバックなどを収集・分析できます。
また、チャットボットやAIアシスタントを使えば、顧客に24時間365日の応対やサポートを提供したり、オムニチャネルでの接点やコミュニケーションを実現したりすることも実現できるでしょう。
データに基づく意思決定
先述したように、DXの推進はデータに基づく意思決定を実現できることもメリットです。これまでに累積した自社や市場の膨大なデータを収集・分析・可視化することによって活用できるためです。
例えば、BI(ビジネスインテリジェンス)やDWH(データウェアハウス)などのツールを活用して、自社の業績やKPI(重要業績評価指標)などをダッシュボードで一元管理できます。ダッシュボードでは、レポートや予測も作成できるでしょう。
また、AIや機械学習などの技術を活用して、データからパターンやインサイトを抽出し、最適なアクションや戦略を提案することもできます。
市場のニーズに迅速に対応
最後に、DXの推進によってデータドリブンな環境であれば、市場ニーズに迅速に対応することができます。市場の動向や変化を分析結果から得られ、データに基づきながら柔軟に判断できるからです。
市場のニーズは常に変化しており、それに合わせて自社の提供する価値やサービスも変化させなければなりません。
そのため、データを収集・分析し、顧客や利用者の行動や嗜好を把握した上で、柔軟に変更・改善し、顧客や利用者に最適な価値やサービスを提供できると市場の優位性を確保できるでしょう。
DXを推進するデメリットとは?

DXを推進するデメリットには、以下の2つが挙げられます。
- 費用とリソースの投資
- 組織文化の変更
費用とリソースの投資
まず、DXを進めるためには、ITの基盤を構築するための費用とリソースの初期投資が不可欠です。
例えば、最新のITツールを導入したり、現在使っているシステムをアップデートしたりなどです。
また、こうした変更管理の課題(例:既存システムの再評価)にも目を向けなければなりません。
さらに、専門知識をもった人材を採用し、適切なトレーニングを施すことや、日々の運用にかかる継続的なコストも考慮に入れる必要もあります。
組織文化の変更
もう一つの大きな課題は、組織文化の変革です。
DXは単に技術を導入するだけではなく、会社全体の考え方や働き方を変えることを意味します。
そのため、全社員が一丸となって取り組むことが求められます。
新しいシステムへの移行や新しい業務フローが定着するまで、時間と労力がかかることは避けられないでしょう。
関連記事

DX推進における課題

DX推進における課題は、以下の4つが挙げられます。
- 文化と組織の変革
- リーダーシップの不足
- コストと予算の制約
- スキルと人材不足
文化と組織の変革
DXの推進においては、文化と組織の変革の難しさが課題としてよく取り上げられます。従来のやり方や考え方に固執する人や部門が多く存在し、変化に抵抗するからです。
例えば、デジタル化によって業務プロセスや役割が変わることに不安を感じたり、新しいツールやシステムを使うことに消極的だったりする人がいます。また、組織構造や報酬制度がデジタル時代に合わせて柔軟に変えられない場合もあります。
リーダーシップの不足
また、DXの推進では、DXに対する理解やビジョンが不十分なリーダーが多いことで、リーダーシップが不足する課題も挙げられます。DXは単に技術的な問題ではなく、ビジネスモデルや戦略の変革を伴うためです。
具体的には、DXを単にコスト削減や効率化の手段として捉えてしまったり、競合他社の真似をしたりするなどが典型的な失敗例です。また、DXに関する意思決定や責任分担が明確でない場合もあります。
コストと予算の制約
DXの推進で多くの企業が抱える課題として、コストと予算の制約も挙げられます。DXは短期的な成果ではなく、長期的な投資であるからです。そのため、DXに投資する余裕がない場合は検討の時点で進まなくなります。
例えば、DXに必要なハードウェアやソフトウェアの導入や更新には高額な費用がかかります。また、DXに関するROI(投資利益率)やKPI(重要業績評価指標)の設定が難しく、先の見通しが立たない側面もあります。
スキルと人材不足
最後に、多くの組織では、DXに対応できるスキルや人材が不足しているという課題があります。なぜなら、DXは常に進化し続ける技術や市場に対応する能力が求められるためです。
例えば、DXに必要なデータ分析やAI(人工知能)などの専門知識や技術を持つ人材が不足しています。仮に人材がいたとしても、高まる需要に供給が追いついていないことで、確保はそう簡単にはいかないでしょう。
加えて、社内から育成する場合、DXに関する教育や研修の機会や体制が整っていない場合VR(仮想現実)もあります。
DX推進を成功させるためには?

DX推進を成功させるカギは以下の5つです。
- 目的や実行範囲を定める
- 社内の協力体制を作る
- DX人材を育成する
- スモールスタートする
- PDCAサイクルを回す
- 人材育成を外部に依頼する
目的や実行範囲を定める
DXを推進するには、DX導入の目的や実行させる範囲を明確に定めておく必要があります。
ビジネスモデルを変化させる要因にもなるので、どういった成果を得たいのかを考えた上で、実行範囲を決めて導入しましょう。
社内の協力体制を作る
DXを推進するなら社内の協力体制も積極的に整えていきましょう。
DXは一つのチームや個人だけで行うものではなく、事業や企業全体で取り組むものです。
既存のビジネスを継続させながら社内環境を整えることとなるので、全分野の社員からのサポートは必須と考えておいてください。
DX人材を育成する
DXは、今後の市場競争力も見据えた上で実施する必要があるため、自社の強みや弱みを理解した社内DX人材がいると良いでしょう。
そのためには、自社のマインドを継承したDX人材を育成していく必要があります。
スモールスタートする
DX推進を成功に導くためにも、DXはスモールスタートすることを鉄則としてください。
DXは、既存のビジネスモデルを大きく変える場合もあるので、推進メンバーをはじめ社員がきちんと変革に対処できるよう配慮する必要があります。
また、DX推進している間に市場が変化してしまう場合もあるので、DX推進は段階を決めながら地道に進めていくことをおすすめします。
PDCAサイクルを回す
DXの導入は、PDCAサイクルを回しながら常にDXが最適化されているか確認する必要があります。
PDCAとはPlan(プラン)、Do(実行)、Check(検証)、Action(行動)を意味します。
DXは導入後もビジネスモデルとの適合性、ビジネスの商流に合致しているかどうかを確かめなければなりません。
人材育成を外部に依頼する
DXを推進するために、人材育成を外部に依頼する方法も有効です。外部に依頼すると、DXに関連する最新のトレンドや知識・技術を学ぶことができ、従業員のスキルや知識を効率よく高められるためです。
また、外部の専門家からのアドバイスやフィードバックを受けることで、DX推進における課題やボトルネックを特定し、改善策を見つけることもできます。
例えば、経験豊富な講師やトレーナーのサポートを受けつつ、組織のニーズに合わせたカスタマイズされた研修プログラムを利用するなどが挙げられるでしょう。
外部の人材育成プログラムを活用することで、対象者のモチベーションやエンゲージメントを高めることもできます。このように、人材育成を外部に依頼する方法は、組織がDX推進におけるスキルと人材不足に対処するための効果的な手段です。
関連記事

まとめ

DXの導入によって変革した事例は身近なところに溢れています。
オンライン会議のように仕事にまつわるものから、スマート家電やフードデリバリー、オンラインスクールのように私生活に関連する分野にもDXは浸透しています。
こうしたDX推進にはDXに必要な知識やスキルを身に付けたDX人材の存在が欠かせません。
身近な事例を念頭に置いたうえで、自社の課題やDXによって成し遂げたい目的を理解した人材を獲得できれば、今後のDX推進について明るい未来が見えるでしょう。
ディジタルグロースアカデミアでは、こうしたDX知識とスキル、そして導入事例を深く理解したDXエキスパートを育てるお手伝いをしています。
自社でDX人材を育成したいと考えている人はぜひ一度お気軽に問い合わせください。
【監修】
日下 規男
ディジタルグロースアカデミア マーケティング担当 マネージャ
2011年よりKDDIにてIoTサービスを担当。2018年IoTごみ箱の実証実験でMCPCアワードを受賞。
2019年MCPC IoT委員会にて副委員長を拝命したのち、2021年4月ディジタルグロースアカデミア設立とともに出向。
デジタル人材育成にお悩みの方は、
ぜひ一度ご相談ください。